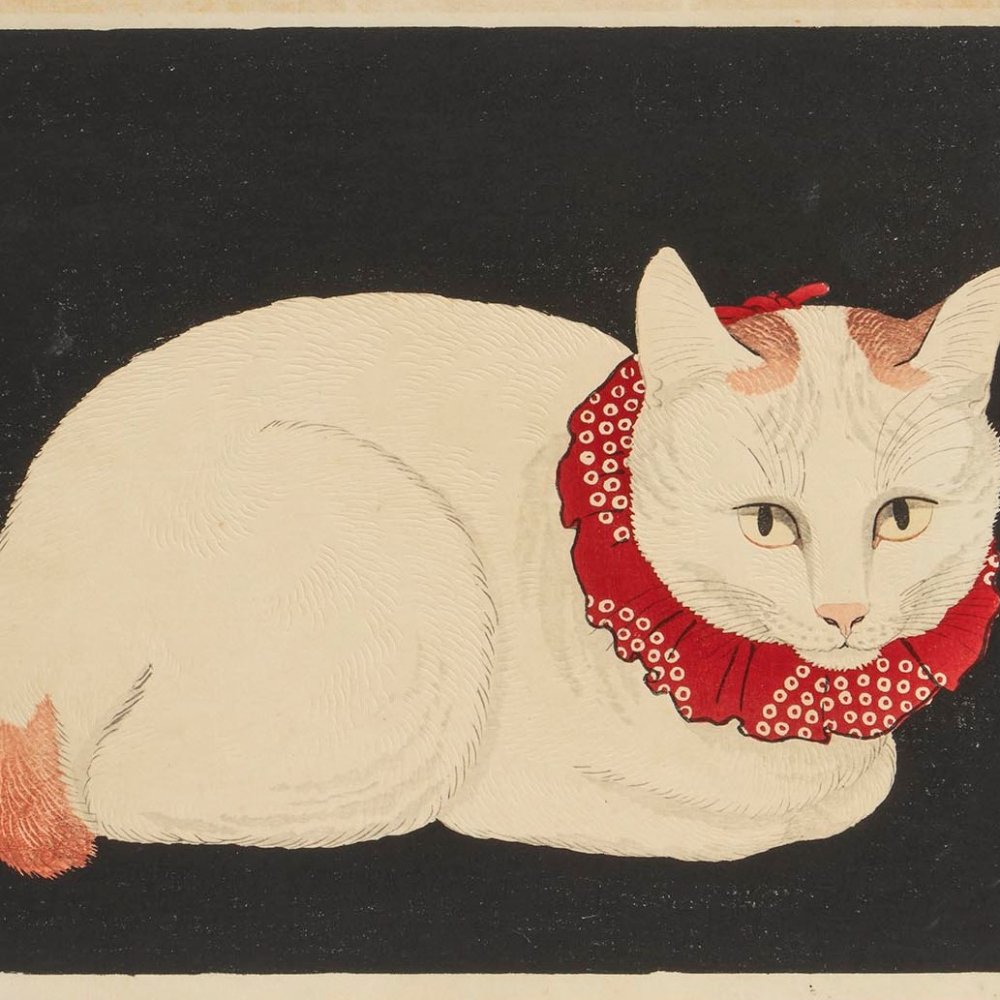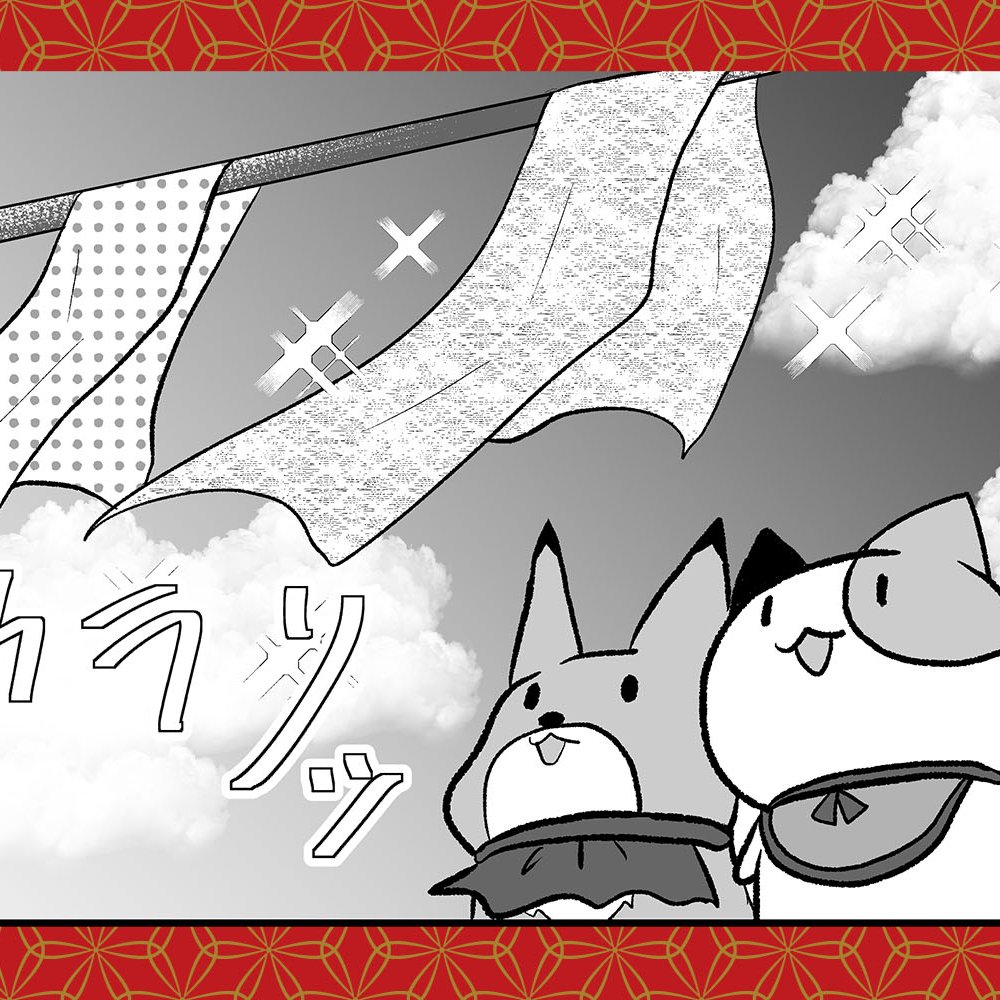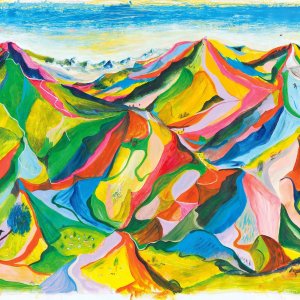新着記事
新着記事
61〜90件(全102件)

武蔵野の谷戸を貫く4つのトンネル、都内に残る水道局の軽便鉄道~羽村山口軽便鉄道跡その1
都内には道路へと姿を変えた廃線跡がいくつかあります。そのうちの1箇所、西東京の武蔵村山市には、自転車道となった水道局の工事用軽便鉄道、羽村山口軽便鉄道跡が残っています。この工事用軽便鉄道は、西武ドーム付近にある村山貯水池(多摩湖)と、山口貯水池(狭山湖)建設工事の資材運搬や、羽村の多摩川で採取された砂利を運搬する目的で、大正時代中頃から太平洋戦争が激化した1944(昭和19)年まで活躍しました。

海岸の戦争遺構。岬の自然公園には遺構が点在する。大房岬に残る東京湾要塞の痕跡。~大房岬砲台・海岸編~
前回、前々回と大房岬のレポートを続けてきました。今回はお伝えできなかった箇所を紹介します。前々回訪れたモーリー池へ戻り、道なりに進みます。林の中を歩くとほどなく前方に、丘が見えてきます。随分と立派な木がすくすくと育っており、その背後に柵で覆われたコンクリート構造物が見えました。「要塞跡発電所施設」 柵にはそう書いていあります。ここは探照灯用の発電施設がありました。インフォメーションセンターで貰った大房岬戦争遺跡には、50馬力27kwのディーゼル発電機が2基設置されていたとのことです。

遺跡のような入り口に祭壇?大房岬に残る東京湾要塞の痕跡、第1探照灯掩灯所~大房岬砲台後編~
前回は大房岬の砲台跡を巡ってきました。後半はこの遺構の目玉を紹介します。と思って記事を書いていたら、紹介するところが多くて長くなってしまいました。メインは今回紹介し、次回はおまけとその他を紹介します。すいません。

岬の自然公園には遺構が点在する。大房岬に残る東京湾要塞の痕跡。~大房岬砲台前編~
「廃なるもの」では、神奈川県横須賀市の観音崎砲台群や千葉県富津市の元洲堡塁砲台と、しばし砲台跡を巡ってきました。それらは東京湾要塞として明治13(1880)年から建設、砲台が配備されたもので、他にも神奈川県と千葉県には要塞跡や砲台跡が公園となって点在しています。比較的安全に“廃なるもの”を観察するには、こうした砲台跡は手ごろであり、いわゆるラピュタ的世界も味わえるので、廃墟散策の百戦錬磨からルーキーまで様々な方が訪れるのです。そのうちの一つが、千葉県の大房岬砲台です。南房総市大房岬自然公園内に遺構が点在し、さながら宝探しのオリエンテーションのように巡ることができます。東京湾要塞は昭和に入ってからも建設され、東京湾の南に突き出ている大房岬は、首都防衛のために昭和3年(1928)から4年の月日をかけて建設された砲台です。岬の地形を活かして砲台と付帯設備が築かれ、終戦間際には海岸部に魚雷艇の基地も配備していました。今まで巡ってきた砲台跡は明治期の日露戦争前の遺構で、レンガ構造物が多かったのですが、大房岬砲台は昭和初期に建設されたため、遺構はコンクリート構造物となります。

鉄道開業150年、東京・横浜で鉄道遺構を訪ねる
今年2022年は、1872年(明治5)に日本で鉄道が開業してから150年の節目です。150年は一世紀半。4世代前、いやそれ以上か。あまりにも長い年月でピンときません(笑)。長きに渡って街も鉄道も成長し変貌しました。そこでこの節目の年に、東京・横浜で鉄道遺構を訪ね、鉄道開業150年の歴史に触れてみましょう。

海底に眠るプラットホーム。関東大震災で沈んだ根府川駅の遺構をスクーバダイビングで巡る
今回は11年前、2011年に訪れた関東大震災の遺構です。震災遺構を廃なるもの(=廃墟)として括るのはどうなのかなとも考えてしまいますが、この読み物では戦争遺構も紹介しており、歴史の遺構の括りとして紹介します(では城跡は?というと収拾つかなくなるので、明治以降の近代遺構としています) 。今回の場所は地上ではなく、ましてや空からでもなく……海です。11年前の撮影ですが、おそらく現在も変化ないでしょう。JR東海道本線根府川駅は相模湾に迫り出す山腹にあります。ホームからは大海原が望め、温暖な気候と相まって長閑な空気に包まれている大幹線の駅です。駅は大正11(1922)年、東海道本線の前身である熱海線開通と共に誕生しました。駅舎は大正13(1924)年築。その間には関東大震災がありました。大正12(1923)年9月1日の関東大震災は、多くの被害がありました。熱海線の被害も甚大で、数箇所で山津波や地滑りによって、鉄橋を含む線路設備がズタズタに破壊されました。中でも根府川駅は、ちょうど進入してきた下り旅客列車と駅が地滑りによって海中へ没する大惨事となってしまい、駅の西側に架かる白糸川橋梁も地震による土石流によって流され、駅周辺の集落も土石流に飲まれました。

監的塀(かんてきへい)と射入窖(しゃにゅうこう)に出合う。陸軍富津試験場の遺構~その3
前回は旧ザクの頭かと思った監的所の跡を見て終わりとなりました。今回はその続きです。監的所のある場所から駐車場方面へ歩を進め、親子がワイワイとキャッチボールをする憩いの広場へ出ました。南側にある茂みへ向かい、その先にある富津試験場の遺構を目指します。

監視台編その2。千葉県富津市の松林に埋まる旧ザク~富津の砲台跡は陸軍富津試験場となり、現在も遺構が点在する
前回はのっぺらな監視所を紹介したところで、ボリュームいっぱいになったので終了しました。今回は続きです。監視所を離れて次の場所へ向かいます。小型の見張り施設、監的所(警戒哨)です。これもコンクリート構造とのことで、監視所と同時期に造られたと考えられます。来た道を戻り、ちょうどジャンボプール付近の松林へ入ります。散策道になっているから安全ですね。しばらく東方向へ歩いていると「監的所(トーチカ)」と記載された戦争遺構ガイドの看板がありました。警戒哨、監的哨、監的所、トーチカ。言い方はそれぞれ異なりますが、廃なるものでは監的所で統一します。

富津の砲台跡は陸軍富津試験場となり、現在も遺構が点在する~監視台編その1
前号は元洲堡塁砲台を紹介しました。この砲台は除籍後の大正8年(1919)、陸軍技術本部に移管され、第一研究所富津試験場(注)として兵器の試験射場となりました。(注:昭和17年に陸軍兵器行政本部第一陸軍技術研究所富津試験場へと整理統合)研究所となった砲台跡は、近距離の兵器を試験する射場となります。扇状の砲台跡の周囲に射場の設備や、数カ所に監的所(警戒哨)や監視所のコンクリート建築物が設置されました。それらの設備は1940年代はじめに建設されたそうですが(続しらべる戦争遺跡の辞典 柏書房による)、富津試験場となった大正時代からポツポツと建設されていったかもしれません。

東京湾要塞の痕跡を辿る。富津公園の元洲堡塁砲台跡
東京湾は、江戸時代末期に外国からの防御のため台場が築かれました。外国船舶の往来が増した明治時代になると、海防の要として、浦賀水道を防御するように要塞が整備されました。

公園に残存する国内初の常設型西洋式競馬場「根岸競馬場一等馬見所」。
新年早々の根岸森林公園は、数日前に積もった雪が広場に残り、子供たちが雪やボールで遊び、笑い声の絶えない憩いの場となっています。時刻は西日が眩しい夕刻時。子供たちの歓声の向こうに、背の高い建造物のシルエットが逆光の光から浮かび上がります。公園内には不釣り合いなほど巨大な建造物。近づいてみると、柵に囲まれて入れない廃墟です。いよいよ不思議な光景に出会しました。正体は「根岸競馬場一等馬見所」。そう、ここは競馬場の跡地だったのです。

茨城県『竹内農場西洋館』。田畑の先の林には、レンガ造りの洋館が眠っていた。
年末、この時期になると取引先の挨拶回りに出かけます。茨城県竜ヶ崎市には空撮でお世話になる竜ヶ崎飛行場があり、そこへ行くついでに何気なくネット地図を眺めていると「竹内農場西洋館」という史跡マークを見つけ、「あ、いつも空撮へ行くときに走るバイパス道路のすぐ近くだ。どれどれ」と史跡マークをクリック。「ヲお……」思わず声を漏らしてしまいます。PC画面に映し出されるのは、朽ちたレンガの建物! 林の中に屋根が崩れ落ちたレンガの廃屋が佇んでいる。ああ、江戸川乱歩の小説に出てくるような「繁栄した一族の栄華が染み込んだ洋館の廃墟」のような風格です。かつては瀟洒な洋館であった廃墟。それが、身近なところの近くにあるとは。飛行場への挨拶の前に、さっそく訪れてみました。

奥多摩に眠る都内随一の廃線跡を道路から愛でる 小河内線跡その2
前回は第三氷川橋梁までの探索でした。後半は終点の水根まで「奥多摩むかし道」を歩きながら巡ります。緑茂る奥多摩とはいえ、夏場だとかなり暑くなります。訪れたのは6月と11月で、6月はまぁまぁ汗だくになりました。11月はまだ身震いするほどの寒さではなかったから、落葉に近い紅葉と遺構の対比が美しかったですね。奥多摩むかし道は、車一台分の幅の生活道路と合流します。小河内線は第四氷川トンネルで抜けています。むかし道の整備で設置されたトイレで小休止。ここから先はこの生活道路がむかし道となります。たまに車が来るので気をつけましょう。

奥多摩に眠る都内随一の廃線跡を道路から愛でる。小河内線跡その1
東京都奥多摩には、遺構がしっかりと残存する廃線があります。その名は小河内線。奥多摩湖となる小河内ダム建設のために敷設された貨物線で、青梅線の終点氷川(現・奥多摩)駅からダム建設現場の水根まで6.7kmの路線でした。小河内線は途中に交換設備のない単線非電化で、東京都が運行する専用線でした。都が国鉄からC11形蒸気機関車と乗務員を借り受けて運行し、専用貨車も製造され、ダム建設資材のセメント輸送に活躍したのです。

2021年10月の高輪築堤を、上空から観察してみよう~高輪築堤見学会レポ総まとめ~
高輪築堤見学会レポの連載、3回に渡って紹介しました。今号は締め括りとして先月(2021年10月)に空撮した模様を紹介します。前回までの地上編と今回の空撮編と、二つの視点から高輪築堤の現在の様子をご覧ください。なお見学会レポはこちらになります。

9月の高輪築堤見学会レポート3部作~後編。出土遺物の目玉は双頭レールと枕木
高輪築堤見学会レポは今回でラストです。最後は出土遺物を紹介します。出土品は鉄道遺物よりも生活品などが多かったのですが、この度の高輪ゲートウェイ駅前の記録保存作業では、大変興味深いものが出土されました。どんなものが出土されたのか見てみましょう。

高輪築堤を地上から見てみた!移築保存される信号機跡と石垣構造。9月の見学会レポート3部作~中編
高輪築堤見学会レポ2回目は、信号機跡と築堤構造細見です。では、高輪ゲートウェイ駅目の前で発掘された、信号機跡の土台を含む築堤部分を見ましょう。信号機跡はニュースにもなったので記憶ある方も多いかと思います。信号機跡部分の長さ30mは、第一京浜沿いに移築保存されることになりました。信号機跡はまだナンバリングだけで発掘状態のままです。築堤から少し迫り出した、城の見張り台のような感じになっています。

高輪築堤を地上から見てみた。9月の見学会レポート3部作~前編
今月14日は鉄道の日です。1872(明治5)年に日本初の鉄道が開通してから149年目となり、来年は150周年となります。前回「廃もの」横浜空撮編では「次回も空撮で」と紹介しましたが、ちょうど「高輪築堤」の見学会に参加する機会がありましたので、その模様を先にお伝えします。今回は前置きが長いです(笑)高輪築堤とは、この数年で注目されている鉄道遺構です。2021年は日本初の鉄道が新橋〜横浜間を結んで開通するとき、品川付近は陸ではなく海上に築堤を築きました。その海上築堤の遺構のことを指します。田町〜品川間の旧車両基地と山手線・京浜東北線の線路跡地再開発中、線路跡地を掘ったら海上築堤と石垣がほぼ完璧な姿で現れたニュースは、人々の注目を浴びることになりました。2019年に最初の確認がされてから、もう2年前近くになります。

【前編】空撮で見る、横浜博覧会後の臨港線廃線跡
遠い記憶の彼方の話になります。横浜港で開催された「YES’89・横浜博覧会」に、家族で訪れたことがあります。おぼろげなのですが、仮設の駅からディーゼルのレトロ車両に乗って、鉄橋や高架橋を走っていきました。その鉄道は横浜博覧会用の輸送列車で、1986年に廃止となって間もない横浜港の臨港線を使用したものでした。走っていた車両は三陸鉄道へ譲渡され、ミャンマーへ渡ったのち、いまはどうなっているか存じません。横浜博覧会後の臨港線廃線跡は1997年に「汽車道」として整備され、現在は手軽に散策できます。今年4月にはヨコハマエアキャビンというロープウェイも開業し、ゴンドラからドローンと同じような高さで汽車道を観察することができます。

【前編】日本初の溶接鉄道橋が残存する横浜港米軍専用線跡
人々がにぎわう横浜みなとみらい地区。そこから横浜港を挟んだ瑞穂埠頭には在日米軍基地があり、基地へは在日米軍専用線の線路が残っています。2回に分けてこの在日米軍専用線を追います。瑞穂埠頭の大部分は在日米軍基地「横浜ノース・ドック」となっており、東海道本線支線の高島貨物線から分岐し、基地へと伸びる在日米軍専用線があります。在日米軍専用線は国鉄が編纂した専用線一覧表によると、東高島貨物駅が接続駅、距離は5.0kmとなっています。もともとは米軍専用線ではなく、戦前の瑞穂埠頭は貿易港で、線路は輸出入品を輸送する貨物線でした。戦後に米軍が接収し、長らく基地間輸送に使用していたのです。

十字状滑走路跡の先の田んぼに残された2基の掩体壕。旧海軍香取航空基地 その2
前回は香取航空基地の保存飛行機と滑走路の雰囲気を見ました。今回はより廃ものらしく、残存する掩体壕(えんたいごう)を見学します。香取航空基地は戦争末期に100基以上の掩体壕がありましたが、現在は3基の掩体壕が残るのみです。そのうち1基は個人宅の敷地内にあるため、見学は差し控えました。掩体壕は第2回調布飛行場掩体壕でも紹介しました。掩体壕とは主に航空機を攻撃から守る防空壕みたいなもので、カマボコ状のタイプや土塁をU字状にしたものなど、いくつか種類がありました。2基の掩体壕は、ブレーキテスト場滑走路跡の北西端の延長線上にあります。前方の畦道を見やると、カマボコ状の物体が二つ、田んぼの中から生えているように見えます。

黄色い海自練習機が保存される場所は十字状滑走路の廃飛行場~旧海軍香取航空基地 前編
千葉県の旭市に十字の滑走路が残る海軍飛行場跡がある。そう聞いたのはずいぶん前のこと。それから20数年。やっとのことで訪れました。旧海軍香取航空基地。場所は千葉県北東部、匝瑳(そうさ)市と旭市の境界です。電車だと総武本線干潟駅が最寄り。ここには海上自衛隊の練習機が保存され、周囲に掩体壕(えんたいごう)も残存しています。今回はちょっと短めですが、海自練習機を見学しつつ香取航空基地跡の全体を観察し、次回は掩体壕を紹介いたします。

碓氷峠の中間駅であった熊ノ平。いまはアプトの道終点である。~碓氷峠その4
碓氷峠は3回に分けてお話しするつもりでした。案の定、話が延びてしまい、4回目の今回がほんとにラストです。話が延びるほど、アプトの道には見るものがたくさんあるということですね。さて、前回まで「熊ノ平(くまのだいら)」と述べているけれども、そもそも熊ノ平とはなんぞやと言うと、アプト式時代は山中にある中間駅でした。新線に切り替わってしばらくした昭和41(1966)年に信号場となりました。駅とはいっても周辺は鉄道関係者か、玉屋の「峠の力餅」(第2回のレポに登場した力餅)の店舗くらいで、変電所と上下列車の交換設備が狭い山肌にへばりつく形であったのです。

高さ31mの4連レンガアーチ「めがね橋」を渡ると、トンネルと橋梁が連続する~碓氷峠その3
前回は旧国道18号のクロスするところまでお伝えしました。第3回目は、いよいよ「アプトの道」が佳境となります。旧国道を潜ります。上り勾配は延々と続いていますね。アプト式終焉の日まで、ラックレールに歯車をしっかりと噛ませたED42形機関車が、客車や気動車を押し上げていた道です。目の前に短いトンネルが連続してあります。第3と第4トンネルです。ここは直線ですね。石積みのポータル(出入り口)に吸い込まれ、てくてくと歩いて行きます。

「アプトの道」は旧線跡へ。レンガのトンネルや橋梁が出迎える~碓氷峠その2
前回のその1では、丸山変電所の手前までやってきました。今回は変電所を観察しながら、アプトの道を登って行き、旧線跡の途中までお伝えします。

廃止から約四半世紀、「アプトの道」というハイキングコースになった信越本線の難所~碓氷峠その1
碓氷峠。その名を耳にするとき、JR信越本線横川〜軽井沢間を登り下りするEF63形電気機関車と特急あさま号、おぎのやの駅弁「峠の釜めし」を思い出します。おそらく読者の皆さんのなかにも、碓氷峠のEF63を追いかけたという方がいらっしゃるでしょう。そこで“廃なるもの”碓氷峠編は、じっくりと紹介したく、3回に分けて語ります。来月までかかりますが、しばらくお付き合いください(笑)

散策道を進むと日本初の西洋式砲台が眠っている。観音崎砲台群<後編> ~廃なるものを求めて 第14回~
前回は「三軒家砲台跡」と「腰越堡塁(ほうるい)」を散策しました。まだ日が暮れるには早い時間帯、せっかくなので観音崎公園に点在する砲台群を見て回ります。神奈川県立観音崎公園は、砲台跡がいくつか点在しています。案内板にもしっかりと記されているし、道も舗装されて歩きやすいので、草木をかき分けて見つける廃墟とは違って気軽に散策できます。さらに、遺された砲台跡は遺跡のような佇まいをしており、かなり見応えあります。観音崎には、前回巡った三軒家砲台跡を除くと、北門第一、北門第二、旧第三、北門第三、北門第四、南門が存在しました。そのうち旧第三と北門第四は海上自衛隊敷地内にあるため見学不可です。今回は第一、第二、第三の三ヶ所を巡ります。これらの砲台は三軒家砲台よりも古く、とくに北門第一と第二は、日本初の西洋式砲台として整備されたので、明治初期の砲台をよく観察することができます。砲台は、日清戦争や日露戦争時に敵の上陸を阻止するため造られたものです。やがて大正時代となると、役目を終えるものや、関東大震災によって被災したものもありました。観音崎にあった砲台の全てが第二次世界大戦終了時まで現役だったわけではありません。また海上自衛隊敷地内にある旧第三砲台は、貴賓船用の礼砲台として現役です。砲は戦後に設置されたものですが、衛星写真を見ると馬蹄状の砲台跡と礼砲用の砲座が判別できます(余談ですが、数カ月前のテレビ番組「鉄腕ダッシュ」でこの礼砲台が紹介されました)。それでは巡っていきましょう。

美術館の裏手は砲台跡だった――。岬の丘陵には砲台がたくさん。観音崎砲台群<前編> ~廃なるものを求めて 第13回~
桜が満開となった麗(うら)らかな春の日。観たい展示があったので、横須賀美術館へ行きました。初めて行く美術館なので、周りには何があるだろうかと何気なく美術館周囲の地図を見ていると、「三軒家砲台跡」という単語を見つけてしまいました。なに?砲台跡?砲台跡。この単語に興味が惹かれ、美術館を拝観し終わったら散策してみよう。いや、そうするべきだと決めました。横須賀美術館は三浦半島の東側、神奈川県立観音崎公園内にあります。観音崎は東京湾の湾口部にあり、一般的には観音崎灯台や海原が望める丘陵地帯の公園が有名ですが、私にとっては明治期に配備された観音崎砲台群を連想させるものです。明治初期から1945年の終戦にかけ、東京湾要塞のひとつとして、三浦半島の沿岸部には砲台などの防衛施設が多数配備されました。とくに観音崎は日本初の西洋式砲台として旧陸軍が整備することとなり、第一砲台が明治17年(1884)に竣工し、続いて第二砲台、第三砲台と、丘陵地帯の沿岸部のあちこちに砲台が配備されました。「三軒家砲台跡」もその砲台群のひとつで、明治29年(1896)から昭和9年(1934)まで稼働しました。