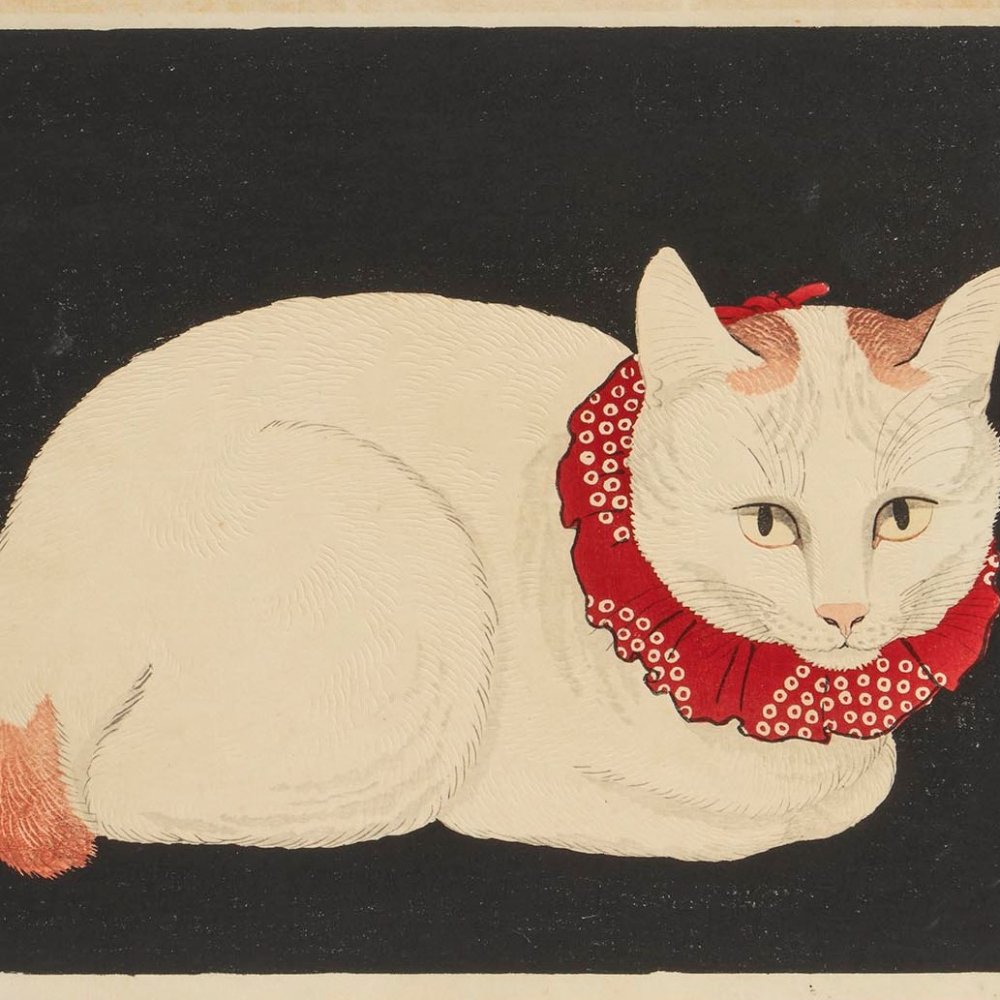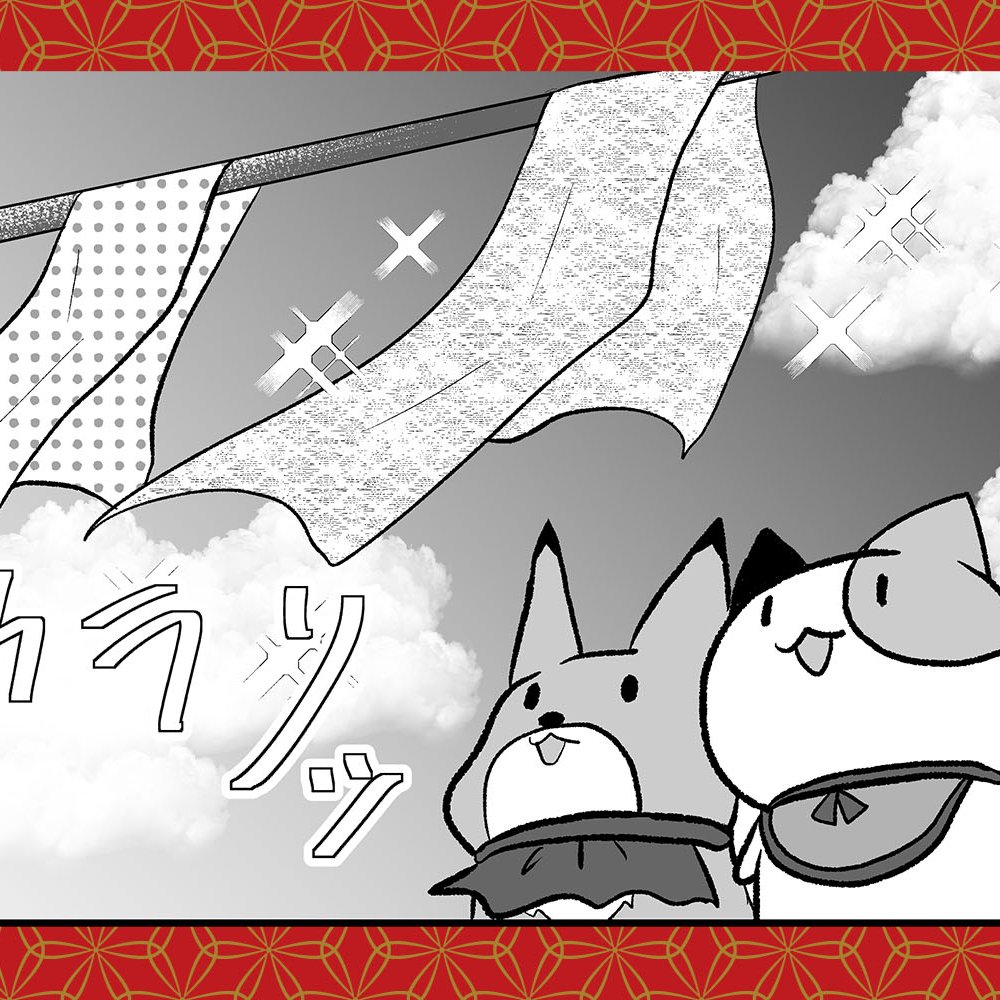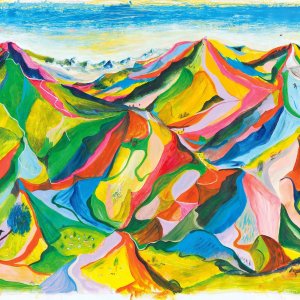新着記事
新着記事
1〜30件(全102件)

現役の製糖鉄道の先にある遊歩道は少々スリリングな“廃”鉄橋【台湾“廃”めぐり】
台湾中部の虎尾という場所には、現役の製糖鉄道があります。現在活躍する線路以外にも廃線が多く、大河を渡る廃鉄橋は遊歩道となっています。撮影は全て2025年3月です。

台中市の“廃”。入場料を払った先にあるのは廃墟となった遊園地だった【台湾“廃”めぐり】
廃墟となった施設は大変魅力的ですが、ほとんどは立入禁止です。それが入場料を払って触れられる“廃”だとしたら最高ですね。そんな廃遊園地があります。ただし台湾の台中市ですが……。

台中市の刑務所跡地の廃屋は木の根に飲み込まれ、廃ビルはまだ営業していた【台湾“廃”めぐり】
台湾“廃”巡りシリーズ、今回は台中市の緑空鉄道1908旧線跡の近くにあった旧台中刑務所跡地の廃屋と、有名スイーツ店の目の前に聳(そび)える廃ビルです。外観だけでも一見の価値があります。

【台湾“廃”めぐり】台中駅後編。幹線の高架化線路付け替え区間は緑とアートを取り入れた廃線跡へと変身した
台湾の”廃”へ訪れた第2回目は、前回と引き続き縦貫線の台中(Taichung)駅の後編です。台中駅は高架化されましたが、日本統治時代の旧駅舎とホーム一部が文化財として保存され、地上区間の旧線跡は遊歩道となりました。ただの遊歩道かと思ったら遺構が点在し、緑とアートの場「緑空鉄道1908」として変身しました。

【台湾“廃”めぐり】台中駅前編。日本統治時代の駅舎とホームには車両も「停車」して保存されている
台湾の廃線跡は遊歩道となるケースが多いです。縦貫線の台中(Taichung)駅は高架化されましたが、日本統治時代の駅舎とホーム一部が文化財として保存されています。先日、その旧台中駅と地上区間の旧線跡遊歩道を訪ねました。台中駅の現在の様子を前後編でお伝えしましょう。

歓声飛び交う休日の千葉公園。ひっそりとたたずむ旧陸軍鉄道連隊の残り香
千葉駅から徒歩でも行ける千葉公園は、大勢の人が遊ぶ憩いの場です。その公園内には旧陸軍鉄道連隊の遺構が点在し、コンクリート構造物が静かにたたずんでいます。2024年10月14日の鉄道記念日に、鉄道連隊の遺構に出合いました。

レンガ積みのトンネルを愛でながら長い長い道のりを散策【山梨県甲州市の大日影トンネル後編】
前編では勝沼ぶどう郷駅の旧スイッチバック駅構造と、大日影(おおひかげ)トンネルの入り口まで到達しました。後半はトンネル遊歩道を散策します。このトンネルは漏水と経年劣化対策工事で2016年から長期間閉鎖されていましたが、2024年3月に再開しました。トンネル内の遊歩道は見どころも多く、往復1時間以上はかかりました。

役目を終えたホームは残りトンネルは遊歩道とワインカーヴとなった。【山梨県甲州市の大日影トンネル前編】
JR中央本線甲斐大和〜勝沼ぶどう郷駅間には、開業時からのトンネルが線路付け替えによって役目を終え、ワインカーヴとなった深沢トンネルとトンネル遊歩道となった大日影(おおひかげ)トンネルが遺されています。そして勝沼ぶどう郷駅はスイッチバック構造をいまに残し、旧ホームなどが残されています。前半はスイッチバック遺構を観察しながら、大日影トンネルの入り口まで行きましょう。

まだまだ現れる高輪築堤、田町駅周辺でも発掘された!見学会参加レポ
高輪築堤は、新橋〜横浜間を結んだ日本初の鉄道が開業する際、品川駅から北側の海に築かれた海上築堤です。JR東日本田町車両センター跡地「品川開発プロジェクト」大規模再開発の2019年に発掘され、高輪築堤と命名されました。高輪築堤の第七橋梁など一部の遺構は国指定史跡として現地保存され、その後も田町駅の山手線付近と品川駅側でも発掘されました。品川駅側で公開された見学会へ参加した模様をお伝えします。

長野の街中にいきなり現れる“廃もの”。岡谷市の製糸業を支えた丸山タンクに出合う
全く予期しないところで遺構を見つけると、胸が高鳴ってしまいます。中央本線岡谷駅の観光案内板で遺構の表記を見つけ、ドキドキしながら訪れたら、素晴らしい情景に言葉を失いました。

空襲の痕跡を無数に残す「旧日立航空機株式会社変電所」は、公園の一角で静かにたたずむ
終戦からもうすぐ80年。東京都内の戦跡遺構は戦後の復興と成長で瞬く間に消え、遺されているものは、わずかに形状を留めているものや地下壕などが主ですが、東大和市には空襲と機銃掃射に遭遇した変電所が当時の記憶を留めて保存されています。

千葉市の大学敷地内にひっそりたたずむ明治の息吹。鉄道連隊材料廠煉瓦建築(煉瓦棟)の一般公開レポ
現代に残る戦跡の中には、関係者以外立入禁止となっている場所にひっそりとたたずむものがあります。遺構に触れられるのはごく限られた関係者のみのため、保存状態が良好だったり、当時の状態が色濃く遺されたままだったりと、状態の良いものが多いです。

東京都府中市の、街に刻まれた砂利運搬貨物線の痕跡を空から眺める
廃線跡は空から見ないとわからないことがあります。地上を散策するときは、遺構が残っていれば良いのですが、唯一残っている遺構が線路から道へと転用されたものだと「ああ、この細い道がそうかなぁ」と、旧版地形図を見比べながら納得していくことになります。先日、府中市内の建物を空撮する案件があり、調布飛行場から飛び立って、いくつもの建物を空撮していました。そのとき、チラチラと視界に入ってくる細い道があり、「あれはどう見ても廃線跡だよなぁ」と直感しました。

さまざまな仕掛けが出迎える廃トンネルと車窓から見える廃線跡。大井川鐡道の大井川ダム旧線と長島ダム付け替え区間【後編】
井川線アプトいちしろ駅を下車し、長島ダムで廃止となった旧線散策のスタート地点へ。そこには「ミステリ~トンネル」と書かれた看板があり、真っ暗なトンネル(大加島トンネル)へと歩みを進めると……。前回の大加島トンネルの闇でいきなりの挨拶に驚きつつ、トンネル内で煌々と輝く明かりへと近づいていきます。が、その手前には「扉を開ける勇気がありますか?」のロッカー。勇気はあります。少し腰が引けていましたが。

真っ暗闇のトンネルに、何かがいる……?大井川鐡道の大井川ダム旧線と長島ダム付け替え区間【前編】
大井川鐵道井川線は全線非電化で、千頭駅を起点に大井川の上流へと上っていきます。もともとは電源開発のために敷設された線路で、中部電力の専用貨物線でした。1959年に大井川鐵道へ運行が委託されて旅客化され、ナローゲージ規格の車体の列車が1067mm軌間の線路を走り、全ての列車が機関車+客車の編成となっています。「廃なるものを求めて」では、以前に終点井川駅から先の廃線跡を紹介しました。今回はもうひとつの廃線跡区間、アプトいちしろ駅〜接岨峡温泉駅間の長島ダム建設に伴う、線路付け替え区間です。前回の吾妻線に引き続き、ダム付け替え線路の紹介となります。

八ッ場ダムに水没した吾妻線の旧線をそっと遠くから見つめる。生まれ変わった遺構にレールバイクも
山間部を縫う鉄道路線のなかには、ダムの建設によって水没するために線路を付け替え、旧線は水底へと沈んだ区間があります。北上線の錦秋湖や飯田線の佐久間湖、注目を集めている旧士幌線のタウシュベツ橋梁もそうですね。前回紹介した吾妻線(旧長野原線)は、2014年に八ッ場(やんば)ダム建設によって岩島〜長野原草津口間の線路が付け替えられ、旧線跡は八ッ場あがつま湖へ没しました。前回までは旧長野原線の太子駅跡まで追うのに精一杯でしたので、吾妻線の旧線跡はここで紹介します。

萌えすぎて後悔。突如として現れるホッパーと鉄道公園! JR吾妻線の前身、旧長野原線をめぐる<後編>
2回にわたって群馬県長野原線の遺構をじっくりと探索してきました。締めくくりは、みんな大好きなホッパーの遺構です。

向かい合う双方のトンネル。真っ暗な第二愛宕トンネルを行く。JR吾妻線の前身、旧長野原線をめぐる<中編>
群馬県の旧長野原線をめぐる旅、前編では第一愛宕トンネルに入ったところで終わりました。気になるその先へと足を進めましょう。第一愛宕トンネルの壁面は、吹き付けたコンクリートに、ツーっと涙跡のような白い線が数本垂れています。何も知らなければ眉をひそめる姿ですが、廃なるものに慣れてくれば「あー、コンクリートの白華現象か」と、いたって冷静になれます。白華現象を簡単に言うと、コンクリートの石灰石成分が水分などによって表へ染み出したもの。鍾乳石みたいなもので、ひび割れた部分などによく現れます。石灰石の涙と言ってもいいのかな。白い線が多すぎるとひび割れも多くなり、耐久性は大丈夫かと別な怖さを感じてしまいますが、とりあえずこのトンネルは大丈夫そう。

蒸し暑い真夏のひととき、霧も出る漆黒のトンネルへ。JR吾妻線の前身、旧長野原線をめぐる<前編>
関東は梅雨明けしました。途端に35度以上の酷暑日が続き、どこか涼を求めて彷徨(さまよ)いたい。こんな暑さには廃トンネルです。廃トンネルは崩落の危険があったり閉塞していたりと、閉鎖されているところが多いです。そういうところではなく、生活道路としては現役だけれども、鉄道としては遺構となった廃線跡を訪れました。JR吾妻線の前身、旧長野原線の廃線跡です。生活道路へ転用された廃線にトンネルがあるのです。前編は廃線跡をめぐりながらトンネルへ、中編はトンネルとその先、後編は終点へとめぐります。

中央本線の線路付け替え区間を陸路と空撮写真で追う【後編】信濃境〜富士見間・立場川橋梁の雄姿に見とれる
前回は中央本線の線路付け替え区間を中心に、信濃境〜富士見間を空から観察しました。後編の今回は、同区間の旧線へ近寄って観察します。撮影は特記以外2024年6月11日です。なお立場川橋梁は現在線の名称にもなっており、旧線の立場川橋梁と混同しないためにも、このレポでは“旧橋梁”とします。旧橋梁には信濃境駅寄りに乙事トンネルと姥沢トンネル、富士見駅寄りに瀬沢トンネルが残存しています。それらの遺構も訪れましょう。と、その前に、富士見町役場へ旧線の情報を聞きに行きました。旧線の敷地や施設は、1980年に国鉄から富士見町へ移管されたので、どこまで見学できるか確認します。旧橋梁は道路からは見学可能で、橋梁に続く築堤は立入禁止になっているとのこと。架線柱倒壊のおそれや土砂崩れなど、不測の事態が懸念されているからだそうです。

中央本線の線路付け替え区間を陸路と空撮写真で追う【前編】スイッチバックの名残りも見られる初狩~富士見間
鉄道路線は、長年の歴史の中で線路を付け替えた場所があって、ときには旧線の痕跡がしっかりと残っていることもあります。そういうところを探して巡るのは、廃線跡探索の醍醐味のひとつ。2回にわたって、JR中央本線の線路付け替え区間にスポットを当てていくのですが、今回は例によって、私の十八番の空撮を多用して紹介します。中央本線は東京駅を起点に塩尻を経由し、名古屋駅へ至ります。大正8年(1919)に東京〜名古屋間が開通し、通称では東京〜塩尻間を中央東線、塩尻〜名古屋を中央西線と呼び、東線がJR東日本、西線がJR東海管内の路線です。

大阪城の堀とオフィス街のはざまで緑にのまれた旧陸軍のレンガ建物【廃なるものを求めて】
前回に引き続き、2024年5月に大阪を空撮した際、市内中心部で出合った廃なるものを紹介します。後半の今回はレンガ建築の建物です。場所は大阪城の北西、お堀と寝屋川が接近するあたりです。そのような場所に、廃墟となって草むしている建物がひっそりと残っています。大阪中心部のビル街にどどんと構える大阪城。伊丹空港へ着陸する旅客機の左窓からでも、その勇姿はしっかりと見えます。「ナニナニ何個分」の広さというのはピンとこないですが、野球場やサッカー場が、余裕で10以上並べられるほどの広さがありますね。このエリアを空撮するときは、旅客機の着陸の合間に行います。空港管制圏内の申請や、管制官との調整はパイロットを通じて行い、念入りに事前の準備をするのですが、それでも実際に飛行して旅客機が近づいてきたら離れなければなりません。すんなり時間通りに撮影できない、空撮にとってはシビアな場所です。

大阪・淀川に残るレンガの橋脚、かつての「本庄水管橋」を空撮する【廃なるものを求めて】
先日、大阪市を空撮しました。様々な案件を抱えて、市内中心部をあちこち。伊丹空港管制圏内での空撮であったため、パイロットと打ち合わせて事前申請をしたり、飛行中もパイロットが管制官と交信して撮影地点の飛行許可をもらったりと、何かと忙しない空撮でした。大阪市内中心部は伊丹空港の空路となっているので、東京よりも自由に飛行できず、シビアなのです。……と、関係のない話でスタートしちゃいましたが、市内中心部を飛行していると、眼下に“廃なるもの”と遭遇することもあります。今回と次回は「大阪の空から廃」と銘打って、上空から遺構を観察します。普段とは違う視点でお楽しみください。

子供たちの歓声に包まれた谷戸に、ひっそりと残る弾薬庫の面影~田奈弾薬庫 後編【廃なるものを求めて】
神奈川県横浜市青葉区にあるこどもの国は、多摩丘陵の谷戸地形を利用した陸軍田奈弾薬庫でした。戦後米軍へ接収され、朝鮮戦争では弾薬の保管に使用されましたが、1961年に返還となりました。1959年に皇太子殿下ご結婚の際に、全国から寄せられたお祝い金の基金や多くの団体などの協力によって、1965(昭和40)年5月5日にこどもの国が開園。敷地約100ヘクタール(約30万坪)の広大な敷地は、自然の中で子供たちが沢山遊べる施設となっています。

こどもの国線の線路沿いには軍用線時代の面影~田奈弾薬庫 前編【廃なるものを求めて】
神奈川県横浜市青葉区にある『こどもの国』は、多摩丘陵地帯の谷戸地形を生かし、牧場、乗り物、芝生や遊具といった、自然の中でのびのびと遊べる児童遊園施設です。渋谷駅から東急田園都市線に乗り、長津田駅からこどもの国線に乗り換えて約1時間で到着できるアクセスと、近隣地域から車で来園できるため、平日休日関わらず親子連れや、学校のオリエンテーションなど多くの人々でにぎわっています。

散りかけた桜の下で佇む祠のような廃駅、旧谷汲線更地駅へ【廃なるものを求めて】
いまから数年前のこと。岐阜県の樽見鉄道を訪れた帰りに車を走らせていると、「そういえば名鉄谷汲(たにぐみ)線の廃線跡が近くにあるね」と友人が思い出し、もう暗くなりつつあった県道を走って、旧谷汲線更地駅へ行きました。読み方は「さらぢ」です。谷汲線は2001年に廃止となり、この駅も運命を共にしました。谷汲線前身の谷汲鉄道によって、大正15年(1926)に開業した駅で、当初は列車交換機能が備わっていたそうです。

土佐電伊野駅から分かれる留置線跡。終点から分岐して住宅地をヘロヘロと延びる線路へ【廃なるものを求めて】
私は線路が好きです。線路の何が好きなのかといえば一言で語れないのですが、形状であったり、集まって分岐する姿であったり、「この先はどこへいくのだろう」とか、小さい頃からワクワクしながら線路を見つめてきました。

やがて消えゆく渋谷駅の山手線旧外回りホーム【廃なるものを求めて】
今回紹介するのは解体途中の物件です。「廃なるもの」に入るか、ちょっと疑問かもしれませんが、大都会に残り、普段から目にできるものなので載せます。場所はJR渋谷駅、山手線外回りホームの名残です。解体途中で、なおかつ立ち入ることが不可能な場所ゆえ、現行のホームから眺めるに留める存在ですが、いつかは消えていくものです。

一部が生活道路となった高速道路。その廃道を堪能する【廃なるものを求めて】
高速道路は都市間交通と流通を支える重要な交通路です。名神高速道路の開通を皮切りに今日でも全国へと路線網を伸ばしており、衰退することを知らないのではないかと思われますが、高速道路にもわずか2か所だけ廃道があります。