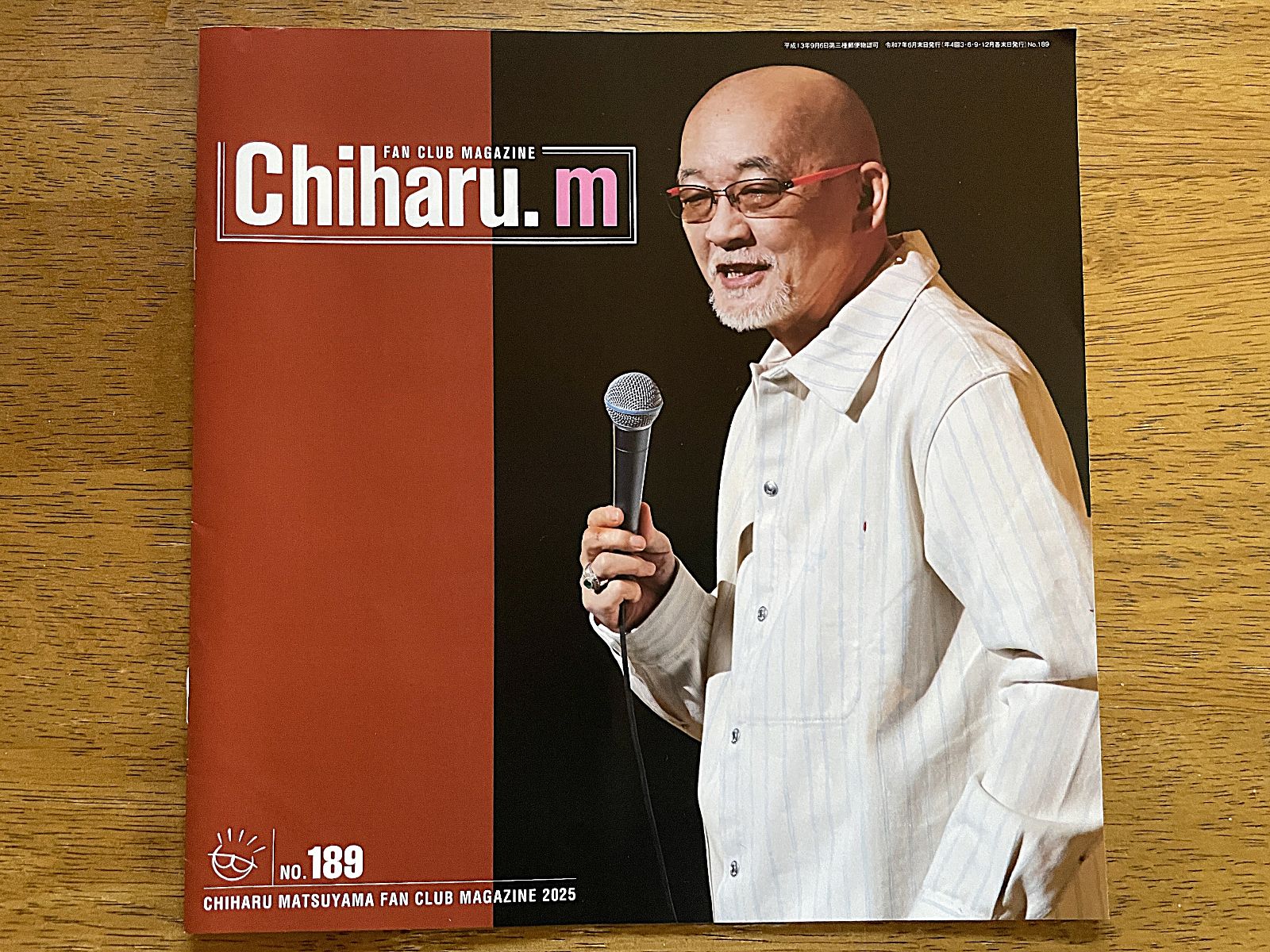史跡の記事一覧
1〜20件(全341件)

【東京散歩コース】湯島・本郷〜東大と天神さまと文人ゆかりの街だから、知的好奇心満開!〜
湯島は歴史ある飲食店街であり、ラブホ街でもある。とはいえ、街の代名詞となっているのが湯島天満宮。祭神は学問の神様・菅原道真公。びっしり埋まった絵馬掛けを見ると、受験生の思いが伝わってくる。麟祥院には徳川家光の乳母・春日局の墓がある。春日通りの名の由来になった寺で、通りを見守るように春日局の像が立つ。春日通りの北側には東京大学本郷キャンパスが広がる。本郷通り沿いには古書店が連なっていたが、店を開けているのは数店のみ。学生街の変容の一端がうかがえる。炭団(たどん)坂から菊坂へ。樋口一葉をしのぶ散歩道には、文豪が好んだ宿も残り、ぶらぶら歩きも楽しい。

【東京散歩コース】飯田橋・神楽坂〜上って下ってまた上る……路地という名の迷路をさまよう〜
神楽坂という粋な町名の由来には諸説あるが、坂の途中に高田穴八幡の旅所があり、祭礼のときにこの地で神楽を奏したからという説が有力。明治中期から昭和初期にかけては東京屈指の繁華街となり、花街としても栄え、毘沙門天 善國寺の縁日でにぎわった。いまでは雑貨屋やカフェが並ぶおしゃれタウンとなり、個性的な書店のある本の街としても注目される。さらに、花街の面影を残す横丁や坂道などとあいまって風情のある景観をつくり出している。外濠を挟んだ飯田橋側に目を向ければ、「東京のお伊勢さま」と呼ばれる東京大神宮がある。縁結びの御利益で知られ、お守りや絵馬、おみくじなども縁結び関連が多い。

古墳に甘味も。宿場町の記憶をつなぐ群馬県玉村町で、散りばめられた魅力と出合う【徒然リトルジャーニー】
埼玉県に接する群馬県南部に位置する玉村町。高崎市・前橋市・伊勢崎市・藤岡市と県内屈指の市にぐるりと囲まれるなか、いかにして輝きを放とうとしているのか。孤高の存在とも評すべき小さな町の様子が気にかかり、足を運んでみることにした。

田沼意次ゆかりの地・静岡県牧之原市相良で、幕府の財政を好転させた名君の足跡をたどる。大河ドラマ『べらぼう』ゆかりの地を歩く【其の六】
ひと昔前の教科書では、田沼意次(たぬまおきつぐ)は“賄賂政治”という言葉と対になって記述されていた。だが大河ドラマ『べらぼう』では、近年見直されてきた改革者としての田沼像に寄せていると思われる。しかも演じているのが渡辺謙なので、切れ者感が半端ない。田沼意次は16歳の時、のちに九代将軍となる徳川家重の小姓となり、父の遺跡600石を継いでいる。家重が将軍職に就くと、意次も江戸城本丸に仕えるようになった。それとともに順次加増され、宝暦8年(1758)には1万石を拝領、大名に取り立てられる。家重が逝去した後も、十代将軍徳川家治から厚く信頼され、出世街道を歩み続けている。そして明和4年(1767)、側近としては最高職の側用人へと出世を遂げた。加えて2万石が加増され相良(さがら)城主となり、さらに安永元年(1772)になると、遠州相良藩5万7000石を拝領し藩主となった。そして幕政を担う老中にまで昇進したのだ。わずか600石の小身旗本が5万7000石の大名になり、しかも側用人から老中になった、初めての人物だ。そんな意次の足跡が残る相良を歩いてみた。

令和の北陸大返し【後編】~長良川から利家の妻・まつ生誕の地、そして名古屋城へ、五日間の旅路踏破じゃ!~
皆々、息災であるか。前田又左衛門利家である。我が金沢城から名古屋城まで歩く「令和の北陸大返し」、此度はついに完結編である。美濃国から名古屋まで、尾張に住む皆々には馴染みの場所を歩いて参ろう。

【東京散歩コース】御茶ノ水・神保町〜本・グルメ・スポーツ・楽器、とりどりの顔を持つ趣味人の街〜
御茶ノ水駅の北には神田明神と湯島聖堂があり、街並みにも落ち着きが感じられる。一方、南は明大、日大、専修大などを擁する学生街であり、楽器店街でもある。若者の姿が多く、街に活気を感じられる。線路を隔てて南北でまったく表情が異なるのが面白い。明大通りの坂を下れば靖国通りに出る。通りの南側は本好きを魅了する神保町古書店街。周辺は人気の飲食店も多いグルメタウンでもある。神田方面に進めばスポーツ用品店が立ち並ぶ。このエリアは、歩を進めるたびに街の様子が変化する。食いしん坊なら、神田須田町一帯に残る老舗飲食店も見逃せない。グルメ雑誌の常連ばかりで、店選びも迷ってしまいそうだ。

錦糸町から西大島へ、まっすぐな川をゆく。竪川~横十間川~小名木川【「水と歩く」を歩く】
錦糸町駅から南に5分ほど歩いた首都高速7号小松川線の高架下で毎年夏に「すみだ錦糸町河内音頭大盆踊り」が開催されている。私も最近は毎年参加していて、2024年は私が描いている漫画のタイトル『東東京区区(ひがしとうきょうまちまち)』が書かれた提灯を献灯した。会場は「竪川(たてかわ)親水公園特設会場」で、来るたびに高架下にこれだけ巨大な空間が広がっていることが不思議だった。以来暗渠(あんきょ)となっている竪川の歴史についてもいつかきちんと調べたいと思っていたのだが、先日たまたまこの竪川を歩くまち歩きツアーが開催されるということを知り、参加することにした。そのツアーとは旧本所区周辺の水路を研究する「旧水路ラボ」による「堀の記憶を歩く」と題した4回連続のイベントで、最終回の第4回「川跡と鉄道編」が錦糸町駅から大横川親水公園を経由して竪川を歩くものだった。案内人の暗渠マニアックスのお二人の解説とともに竪川に架かる橋(暗渠に架かる橋なので“暗橋”)を巡る行程は大変楽しく、勉強になった。そこで今回は勝手にそのツアーの復習も兼ねつつ、竪川の橋の他に見ておきたいと思っていた横十間川と小名木川が交差する地点まで歩いてみることにした。

令和の北陸大返し【中編】~越前府中城から余呉湖、姉川、関ケ原へ、日本史の要所を歩く!~
皆々、息災であるか。前田又左衛門利家である。儂が治め築いた地、金沢から、我が生まれの地、尾張へと250kmの距離を五日間で歩き抜く「令和の北陸大返し」。中編となる此度は越前から美濃を目指し進軍して参るぞ!改め、いざ出陣である。

令和の北陸大返し【前編】~金沢から福井県・鯖江へ、道中の史跡を紹介致す!~
皆々、息災であるか前田又左衛門利家である。此度の戦国語りでは前回に引き続き、金沢城から名古屋城まで歩き、道中の史跡を紹介致す!名付けて「令和の北陸大返し」、五日間で250kmを進んで参るぞ!

【東京散歩コース】皇居・丸の内・東京駅~江戸城の遺構のすぐお隣は洗練されたオフィス街~
皇居は徳川将軍の居城・江戸城だったところ。広さは皇居外苑を含めると230万平方メートルあり、東京ドーム49個分に相当する。皇居周辺散歩の楽しみは、江戸城の遺構と、それらと一体となった庭園や植栽の美しさにある。丸の内は日本を代表するオフィス街。ブランドショップが並ぶ丸の内仲通りは洗練された街並みで、人気の散歩コース。昼どきに現れるキッチンカーは丸の内の名物だ。隣接する商業ビルでショッピングやティーブレイクを楽しむのもいい。コースの終点の東京駅丸の内駅舎は、建物を見るだけでも価値がある。『東京ステーションギャラリー』のレンガ壁の展示室に、駅舎の歴史がしのばれる。

前田利家、我が金沢城を紹介致す! 多種多様な石垣から重要文化財まで、見どころ満載じゃ
皆々、息災であるか前田又左衛門利家である。儂が歴史のおもしろき話を紹介致すこの戦国がたり。此度の題目は久方振りの史跡探訪であるぞ!これまでは大高城や長篠古戦場、長久手古戦場や関ケ原などを紹介致しておる。此度は儂、前田利家に深い関わりを持つとある城を紹介致そうではないか!!

現役の製糖鉄道の先にある遊歩道は少々スリリングな“廃”鉄橋【台湾“廃”めぐり】
台湾中部の虎尾という場所には、現役の製糖鉄道があります。現在活躍する線路以外にも廃線が多く、大河を渡る廃鉄橋は遊歩道となっています。撮影は全て2025年3月です。

江戸の出版業界を席巻した「耕書堂」、店を構えた日本橋界隈を訪ねる。大河ドラマ『べらぼう』ゆかりの地を歩く【其の伍】
ドラマ『べらぼう』も中盤に入り、個性的な登場人物が次々に登場。現代でも高い評価を得ている芸術家や文化人と、彼らが生み出す作品を世に送り出した稀代のプロデューサー蔦屋重三郎(以下・蔦重)のアイデアが、一気に花開いていく様子が描かれている。その小気味の良い展開に、すっかり虜(とりこ)となってしまった人も多いようだ。安永2年(1773)、吉原五十間道に立っていた「蔦屋次郎兵衛店」を間借りして、書店「耕書堂」を始めた蔦重。本屋としての地歩を着実に固めた後、天明3年(1783)にはついに日本橋の通油町(とおりあぶらちょう)に耕書堂を構えた。“ついに”と表現したのは、ここは鶴屋喜右衛門といった江戸の名だたる地本問屋が軒を連ねる書店街だったからだ。まさしくこの時に、出版界に「耕書堂あり!」となったのである。

台中市の“廃”。入場料を払った先にあるのは廃墟となった遊園地だった【台湾“廃”めぐり】
廃墟となった施設は大変魅力的ですが、ほとんどは立入禁止です。それが入場料を払って触れられる“廃”だとしたら最高ですね。そんな廃遊園地があります。ただし台湾の台中市ですが……。
史跡のスポット一覧
1〜12件(全216件)

東大赤門(とうだいあかもん)
国指定重要文化財となっている東大赤門で、正式名称は「旧加賀屋敷御守殿門」。この地にはかつて加賀藩の上屋敷があった。加賀藩13代藩主前田斉泰が、徳川11代将軍家斉の娘の溶姫を正室に迎える際に、住まいの御守殿とともに文政10年(1827)に建立したという歴史を持つ。

樋口一葉旧居跡(ひぐちいちようきゅうきょあと)
24年の生涯で『たけくらべ』などの名作を残した作家・樋口一葉が、明治23年(1890)から約4年間、母・妹と住んだ地。生計の足しにするため、他人の洗濯物を洗ったという共同井戸が残る。住居地区なので静かに見学しよう。

法務省赤れんが棟
明治28年(1895)に、司法省として竣工されたネオ・バロック様式の庁舎。一時は戦災の影響でレンガ壁を残して消失したが、1994年に創建当時の姿に復元された。いまでは一部の部屋が法務史料展示室として公開されている。館内では司法や赤れんが棟の建築に関する資料の展示を見ることができる。