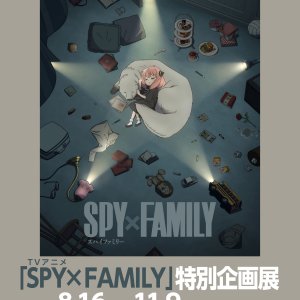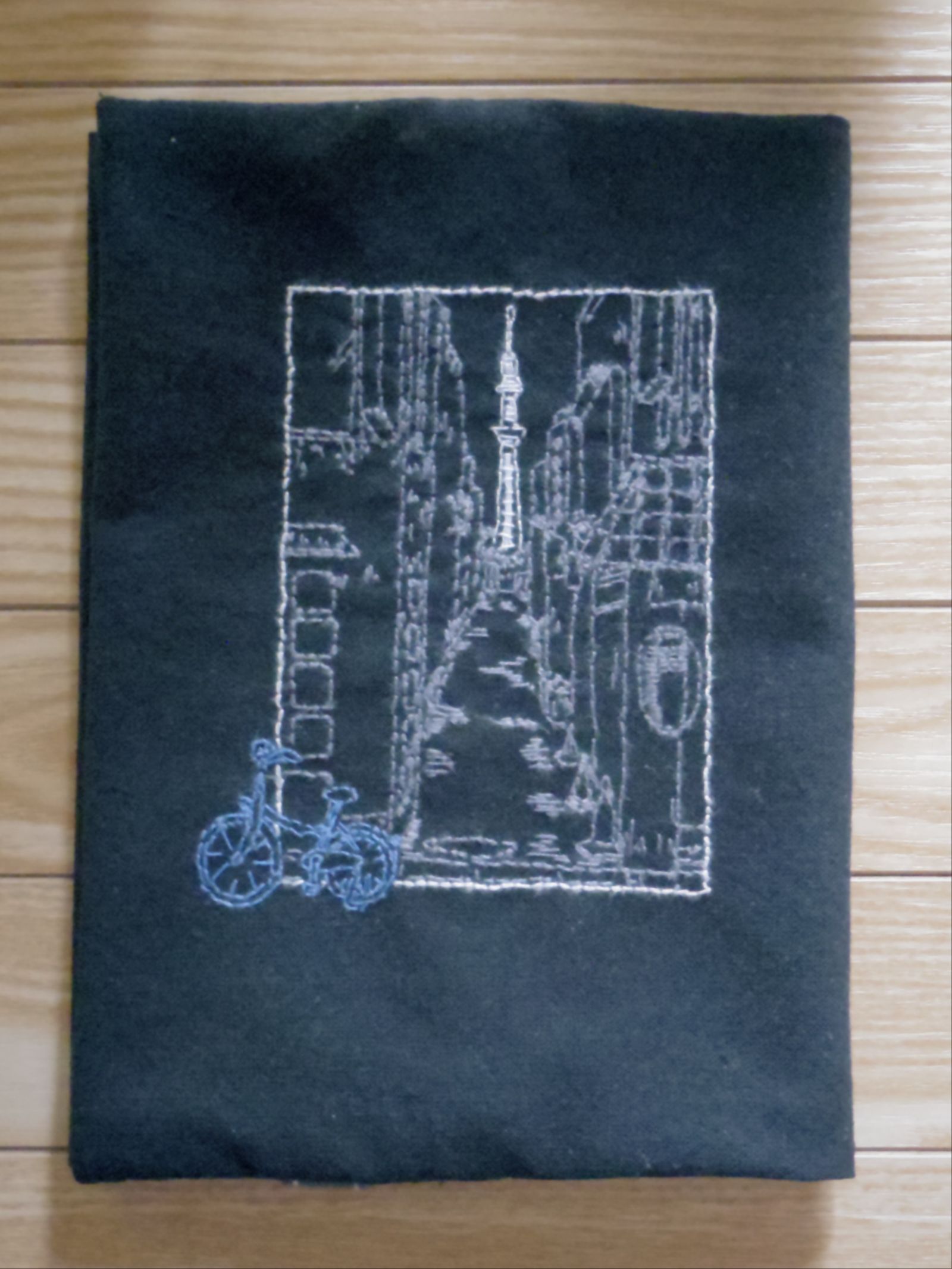栃木県
栃木県の記事一覧
1〜20件(全47件)

七福神ってどんな集まり?御利益や特徴を出身国別で紹介! 大黒天・弁財天・毘沙門天【インド出身の神様編】
縁起物として人気の「七福神」。絵画や置物としてよく見かけたり、飲食店の名前にもなっていたりして身近ですよね。しかし、7人(本当は7柱と数えます)の神様がいること以外、詳しく知らないという方もいるのでは?実は、日本だけでなくインドや中国の神様もたくさん混ざっているんです! というわけで、七福神の神様それぞれを「出身国別」で詳しくご紹介します。今回は、インド出身の3人から!

荒井良二の「いままで」と「これから」に迫る「new born 荒井良二 いつも しらないところへ たびするきぶんだった」が7月20日~9月23日、『宇都宮美術館』で開催
絵画や絵本原画とともに、新作のインスタレーションや愛蔵の小物たちなどを通して、荒井良二氏の「いままで」と「これから」をたどる巡回展「new born 荒井良二 いつも しらないところへ たびするきぶんだった」が2025年7月20日(日)~9月23日(火・祝)、栃木県宇都宮市の『宇都宮美術館』で開催される。 TOP画像=《POSTじゃあにぃ いったことのないたびにでよう》 2020年(C)Arai Ryoji。

栃木県壬生(みぶ)町の新旧町並みを北へ南へ。「おもちゃのまち」とはどんな町?【徒然リトルジャーニー】
栃木県央南部に位置し、宇都宮市と栃木市に挟まれた壬生町。地名は室町時代に壬生城を築いた壬生氏に由来するが、その謂(いわ)れは定かでない。片や気になる「おもちゃのまち」とはどんな土地柄なのか。起伏の少ない町内を、北から南へと訪ね回った。

栃木県・湯西川温泉の秘湯宿へ。木も心遣いもふんだんに仲よし親子が磨く『上屋敷 平の高房』
平家が落ち延びた深山幽谷の地に佇む、質実剛健な木の館。栃木県湯西川温泉『上屋敷 平(たいら)の高房(たかふさ)』。「父母が魂を込めてつくってきた宿」を3代目若女将が守り、引き継ぐ。

かんぴょう生産量日本一の栃木県下野市で、「東の飛鳥」「グリムの里」のゆえんを探る【徒然リトルジャーニー】
栃木県中南部に位置し、県内最少面積の市である下野(しもつけ)市。JRが市内を南北に貫く利便性の一方、農作物の一大産地としての顔も併せ持つ。加えて「東の飛鳥(あすか)」「グリムの里」を標榜するゆえんはどこにあるのか。謎を解きながら市内を訪ね回った。

『ステーキ宮』の肉なんて飾りです。宮はたれなんです。【絶頂チェーン店】
栃木県足利市出身のツクイさんが好きなタレントは照英だ。埼玉県鴻巣市出身。熱くて、男らしくて、趣味がよい。出会いはとあるグルメ番組だ。「これまでの食レポで一番美味(おい)しかったグルメは?」という問いに、まっすぐな瞳で「宮のたれ」と答える彼の姿を見た瞬間「この人のことは一生信じられる」と、遺伝子レベルで解(わか)りあえてしまったそうだ。宮のたれ。

戦国時代の医療事情と、天下人にも認められた名医・曲直瀬道三殿について語ろうぞ!【前田利家戦国がたり】
皆々、息災であるか。前田又左衛門利家である。これよりは儂(わし)の戦国がたりの刻である!!此度の題目は「戦国時代の医療について」である!いざ参らん!

都内から日帰り可能! 超仏像マニアのツバキングが関東の素晴らしい仏像のあるお寺を紹介!【後編】
こちらの連載では、前回【関東にある仏像の素晴らしいお寺】をご紹介いたしました。しかし、まだまだ関東圏内には素敵な仏像がたくさんあります!都内から気軽にでかけられる鎌倉の名仏をはじめ、関東地方に素晴らしいお寺をさらにご紹介しましょう。京都や奈良まで出かけなくても堪能できる素敵な仏像を、是非ご堪能ください!
栃木県のスポット一覧
1〜12件(全106件)