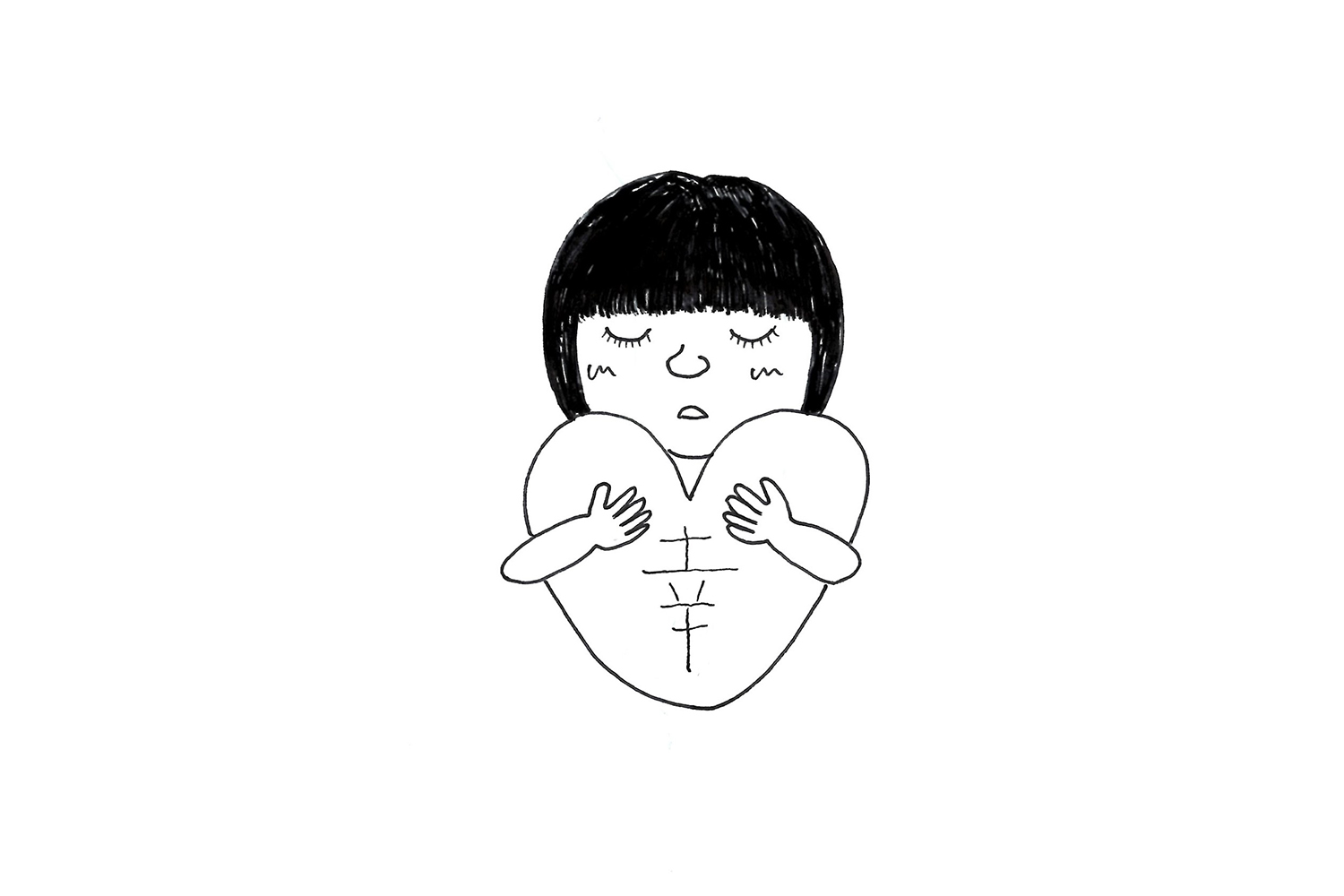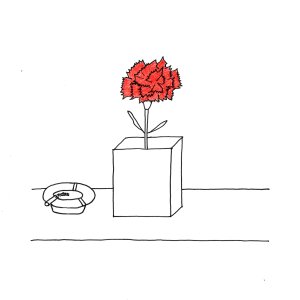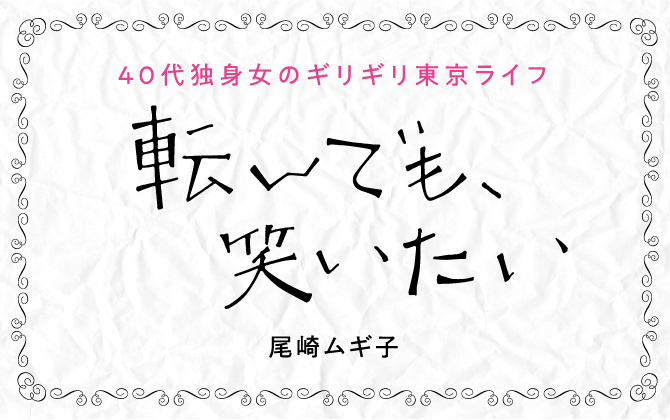週1回、アルバイトをしている『荒井屋酒店』の角打ちで酒を注ぎながら、飲みに来ていたかなえちゃんに「もうなにもかも嫌だ。工場でバイトしたい」と言うと、かなえちゃんはその場でアルバイト情報サイトを検索し、わたしの家から徒歩10分の場所にある工場のアルバイト募集を見つけてくれた。さすがかなえちゃん。グダグダ言ってなにもしないわたしとは違って、行動が早い。
7年前にも工場で働いたことがある。だれとも喋らず、黙々とベルトコンベアに流れてくるお菓子を手で軽くトントン叩き、音がおかしければはじくという仕事だ。「気が狂う」と言って辞めていく人が続出するなかで、わたしは意外と平気だった。時給800円だが交通費が自己負担のため、実質時給740円。それでも接客業などに比べて圧倒的にストレスが少なく、半年くらいは続けた記憶がある。
かなえちゃんが見つけてくれた工場は、時給1150円。最低賃金が上がったため、7年前と比べて実質時給410円アップだ。なんとも魅力的だが、工場のアルバイトは自己肯定感が爆下がりする。ベルトコンベアに向かいながら、「せっかくそこそこいい大学を出て、そこそこいい会社に入ったのに、なにをやっているんだろう」という考えがふと脳裏をよぎるのだ。応募すべきかどうか躊躇(ためら)った。

以前この連載で「これまでお付き合いした男性は5人」と書いたが、実はもうひとりいる。マッチングアプリで知り合い、一瞬だけ付き合ってすぐに別れた人だ。「違うなと思ったらすぐ別れていいから」と言われて付き合い、本当に「違うな」と思ってすぐ別れた。嫌なことをされたわけでもなく、嫌いになったわけでもなく、なにかが決定的に“違う”。恋愛経験が乏しいくせに(乏しいからか?)、わたしはそういう小さな違和感に敏感だ。
3年振りにその彼から連絡があり、会うことになった。「仕事は順調?」と聞かれ、わたしはマシンガンのように愚痴をぶちまけた。やる気が出ない。仕事に情熱を持てない。もう生きているのも嫌だ! ひとしきりぶちまけたらスッキリして、久々に楽しく酒を飲んだ。別れ際、「また付き合わない?」と言われ、ああ、それもいいかもなと思った。
1週間後、またその彼に会うと、「男性が苦手なんだね」と言う。「そんな話したっけ?」と不思議に思いながら男性嫌悪について話していると、なぜか彼はわたしがレズビアンバーに行ったことも知っていた。さらにはなぜかガールズバーに勤めていたことも知っていた。まずい。この連載を読まれた……。
2023年4月にこの連載が決まったとき、なにもかも曝(さら)け出そうと決めた。もう嫁には行けないだろう。それでもいいと思った。ライターになって16年。ようやく持てた雑誌・Webの連載なのだ。すべてをこの連載に捧げるつもりで1年間記事を書いてきた。「恋愛したい」だのなんだの書きながら、もう二度と恋愛できない覚悟はしていた。その連載を読まれてしまった。THE・ENDだ。
ところが彼の口から出た言葉は意外なものだった。「また付き合うっていうことでいいよね?」——。耳を疑った。この連載を読んだのに、わたしと付き合いたいというのか。もう辞めたが40過ぎてガールズバーに勤め、酒と煙草と睡眠薬に依存し、彼氏ができてもセックスをすると一方的に振ってしまい、男に懲りてレズビアンバーに行き始めたこのわたしを、受け入れようというのか。「でもいつもみたいに1カ月半で振られちゃうかもね」と笑う彼を見て、この人は仏かなにかなのだろうかと呆然とした。
「弱っているときに決断してはいけない」と人は言う。いまのわたしは明らかに弱っているのだから、決断してはいけないのだろう。それでもなんだかいろいろなことに疲れてしまい、流れに身を任せたいと思った。

5月、わたしは工場で働き始めた。そして仏のような元カレとまた付き合い始めた。工場も恋愛もいつまで続くかわからない。書くことへの情熱を取り戻し、また元の生活に戻るかもしれない。次の回には「彼氏と別れた。やっぱりセックスが無理だった」などと書くかもしれない。それでもいまは、この不安定で曖昧な幸せに浸っていたいと思う。
文・イラスト=尾崎ムギ子