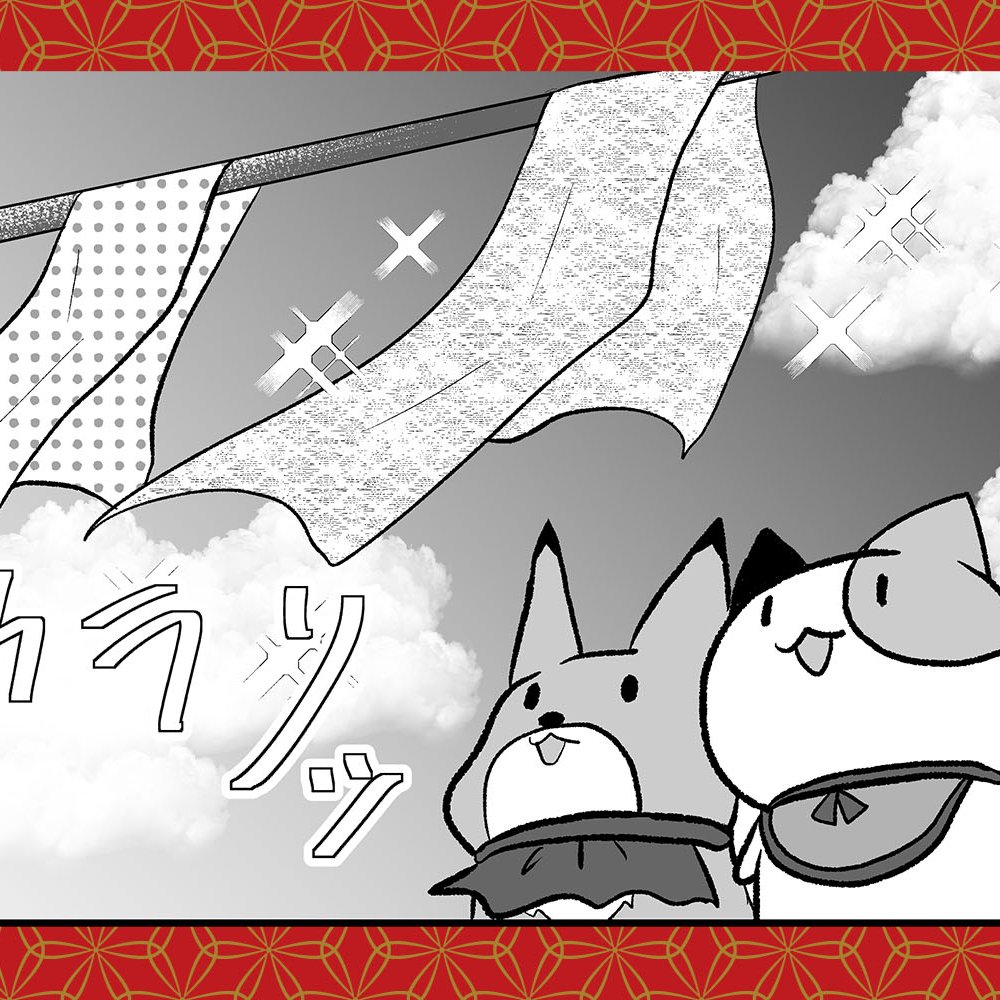終戦直後に祖母がはじめた屋台がルーツ
それにしてもどんな経緯でこの餃子は生まれたのだろう。以後どうしても戦後史的な話になっていくが、お許しいただきたい。
『萬里』3代目店主の福田さんによれば、創業者である祖母・八重子さんは、「引揚者(ひきあげしゃ)」であった。少し前までわれわれの周りにも身近にいた元引揚者。筆者の周りにも何人もいたが、いまは多くの人が鬼籍に入っている。いまの若い方など、この言葉自体、知らない人もいるかもしれない。
おもに中国大陸や朝鮮半島などの日本の旧植民地から、終戦を期に帰国した(引き揚げてきた)人々を指している。侵攻してきたソ連軍、戦中まで圧迫していた現地住民から、敗戦するや攻撃や略奪を受け、またほとんど公助がなかったことで、引揚船に乗るまでの逃避行、極寒の地での仮暮らしは悲惨を極め、多くの人が命を落とした。運よく帰ってこられても現地で得た資産をすべて失い、わずかな現金や証券の持ち込みさえも制限され、皆さん、ほとんど裸一貫で帰国した。
そうした人々が、帰国して食うためにはじめた仕事は、各地の駅前にできたマーケット街、いわゆる「闇市」での露店商売だった。これは大きな元手がなくてもはじめやすい商売だったのだ。
「祖母は、終戦後に野毛で屋台で商売をはじめたと聞いています」
福田さんは言う。『萬里』の創業は1949年だが、それは現店舗の位置で店を構えて商売をはじめた時期で、ほんとうはその前——終戦直後に屋台を引き、そこで売る商品として焼き餃子を開発したのだという。しかし、それ以上に詳しいことを祖母は語らなかった。
横浜・野毛の変遷と根付いた引揚者料理
終戦直前、昭和20年(1945)5月の横浜大空襲で市内の8割が被害を受け、市街地はほとんど焼け野原になってしまった横浜。戦争が終わると進駐軍(アメリカ陸軍第8軍)の司令部も置かれたことから、関内や伊勢佐木町の焼け残っためぼしい建物は接収されてしまい、また福富町あたりには、半円筒形の形状から、カマボコ兵舎と呼ばれた組み立て式の軍用住宅が次々に建てられてしまった。終戦後まもない時期のハマには10万人近い米兵がいたと言われている。
これだけのモノや人がハマの街に殺到したその割りを食うかたちで、もともとの住人たちはところてんのように大岡川を渡った野毛へ押し出されてきた。そこには大勢の仕事を求める日雇い労働者も集まり、かつてないほど野毛には人があふれた。そして通り沿いには彼らを相手にする露店街ができたのである。「カストリ横丁」「くすぶり横丁」なんて名前の飲み屋街もあれば、物販の露店街もあった。
このいずれかに福田さんの祖母はいたはずだ。そうして売ったものが焼き餃子だった。中国の南のほうは昔から主食は米がメインだったが、北部は小麦が多い。古くから北部ではマントウや餃子(主に水餃子)など小麦料理が食べられてきた。ここから考えても、おばあさんがいつの時点で海を渡ったかは伝わっていないものの、中国東北部、旧満州のどこかで暮らしていたとは想定できる。
そして引揚者は、帰国しても引き揚げ時代のことを子や孫になにも語らなかったケースが多い。悲惨な体験、心に刻まれた暗い影を話したくなかったのだ。福田さんの祖母もそうした思いがあったのかもしれない。
だが、楽しかった日々、懐かしい日々も記憶にはあっただろう。その明るい光が、日本各地に、さまざまな形の料理となって残された。現地の料理そのままではなく、引揚者たちがそのエッセンスを抽出して、日本で手に入る食材、日本人の味覚にあう料理、そして庶民が気軽に食べられる価格帯の「引揚者料理」として昇華させた。祖母もまさに、その一人だった。
とはいえ、生まれて80年近くが経過している。これまでにテコ入れというか、なにか変更しようとしなかったのだろうか。福田さんはうなずく。
「ええ、じつはさまざまな研究や試作を行ったことがあります。でも結局改良の余地はなくて、原料・価格のところからもオリジナルに戻ってしまったんです」
つまり、戦後最初に生まれたシンプルな餃子は、最初から完成された料理だったのだ。それは、混乱の時代を生き抜かねばならなかった世代の、商売への命がけの集中力が生み出したものだったと筆者には思える。
書物や記録だけが後世に残る遺産ではない。そして歴史証言はいつか消えてしまうこともあるけれど、この味は、いつまでも消えずに残ってゆく。ということで、野毛の味覚遺産、おかわりお願いします! あとビールも!
取材・文・撮影=フリート横田