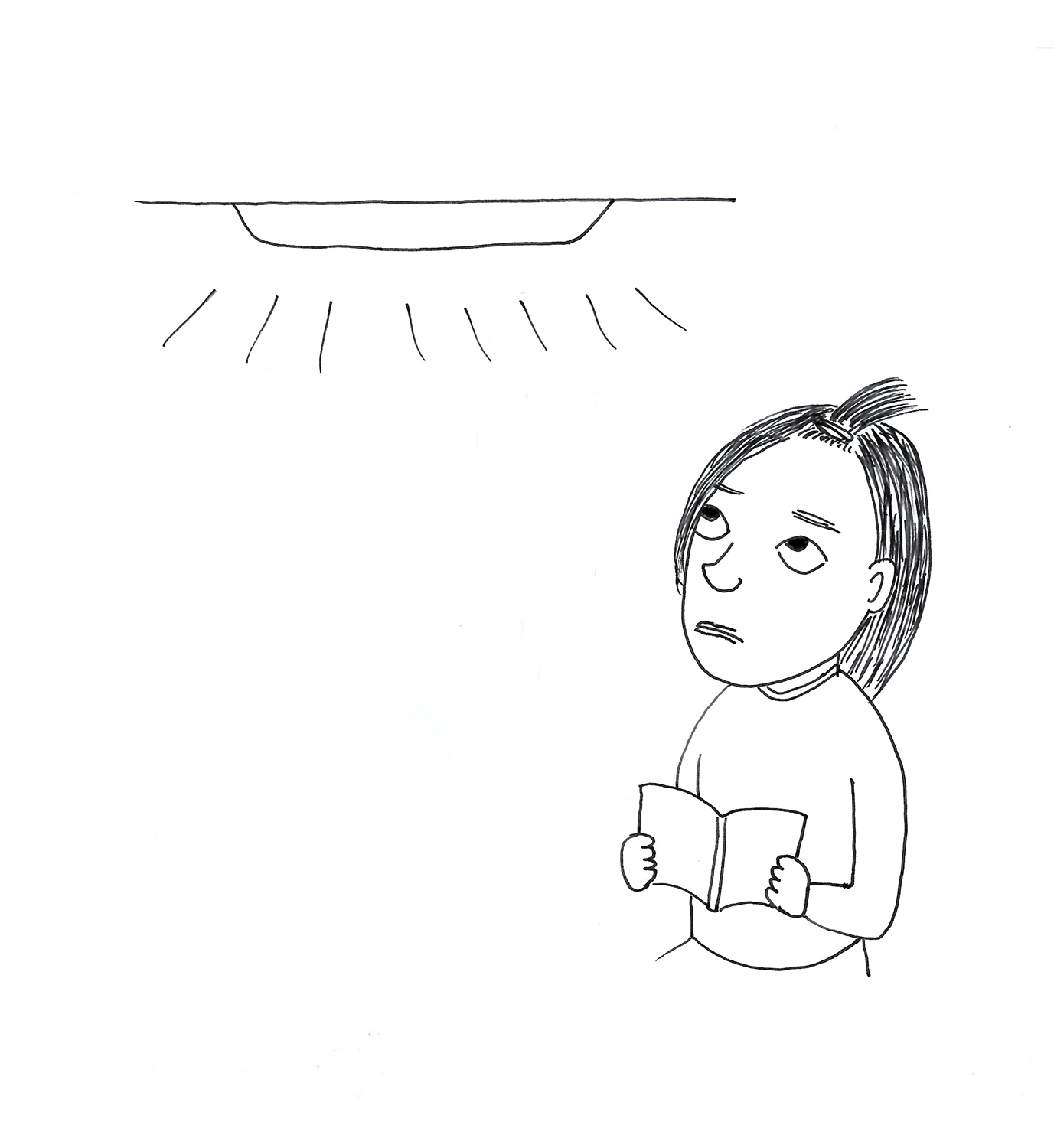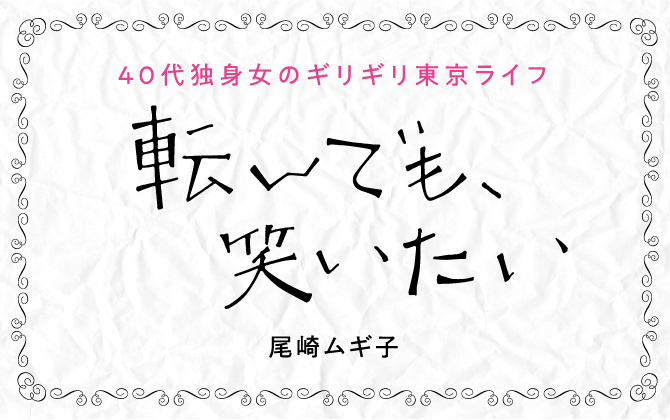顕著なのは本を読んでいるとき。視界に入る蛍光灯が気になって、まったく読み進められない。「蛍光灯を見てはいけない」と思うと、余計に気になってしかたなく、少し読んでは蛍光灯を確認し、また少し読んでは蛍光灯を確認するという行為を繰り返してしまう(「確認症」とも言うらしい)。当然、本の内容が頭に入るわけもなく、長時間かけてなんとか読み終えても、なにを読んだかイマイチ覚えていない。文章を書く仕事をしているのに、わたしは読書量が圧倒的に少ない。インプットできなければアウトプットもできないもので、執筆活動もすぐに行き詰まる。
人と話していても、相手の話をウンウン聞きながらべつのことを考えてしまう。例えば、会話中につい夕飯のことを考えてしまうといった経験はないだろうか。普通はそこでハッとして会話に戻れると思うのだが、わたしの場合は「いま夕飯のことを考えている」ということに意識が向いてしまい、そうなるともうなにを話しているのかわからなくなる。集中しなければいけないシチュエーションであればあるほど雑念が湧いてくるため、取材中はとくにひどい。あとから録音を聞いて「こんな話をしていたのか」と驚くこともしばしばだ。
ライターに向いていないとつくづく思う。ライターというより、人間に向いていない気がする。

そういう事情があってプロレス観戦を控えていたのだが、先日、センダイガールズプロレスリングの大会に誘われて観戦に行ってきた。案の定、目の前の試合に集中できない。「集中しなければ」と思えば思うほど、「いま集中していない」ということに意識が向いてしまい、まったく集中できない。それでもプロレスラーたちの迫力、叫び声、リングに叩きつけられる音――。そういったものに感動と興奮を覚えた。
メインイベントはタッグ選手権のタイトルマッチ。キャリアの浅い岡優里佳選手が、王者・橋本千紘選手に対して大健闘した。岡選手はデビュー当時から見ているが、こんなにいいレスラーになるとは思っていなかった。負けて号泣する岡選手を見て、「なにも恥じることはない」と思った。
橋本選手がマイクを持つ。
「わたしたちがチャンピオンになっても頑張り続ける理由は、こうやって、意味わかんないくらい練習して、必死に追いかけてくる二人がいるから」
涙が止まらなかった。感動したというより、自分が情けなかった。プロレスラーは日々、過酷な練習を積んでリングに上がっているのに、わたしはライターとしてなんの努力もしていない。雑念恐怖症を言い訳にして、本だって読んでいない。わたしも岡選手のように“意味わかんないくらい練習”しよう。そうすればきっと成長できるはずだ。
帰宅して、さっそく本を読み始めた。しかしどうしても、蛍光灯が気になって読み進められない。電気を消して懐中電灯を点(つ)けてみたが、今度は懐中電灯が気になってしかたない。わたしはなんて情けないのだろう。しかし岡選手の勇姿を見て、こんな自分を変えたいと思った。
翌日から、集中できなくてもなんでも、1日1時間、読書に時間を充てるようにした。相変わらず蛍光灯が気になってしかたない。「蛍光灯が気になっている自分」が気になってしかたない。普通の人なら1時間のところを、わたしは10分も本を読めていないだろう。だったら人の何倍も時間をかけるしかない。もどかしいけれど、そうするしかないのだ。

2022年4月、『女の答えはリングにある』(イースト・プレス)という本を出版する際、ダメ元で西加奈子さんに帯文をお願いしたところ、面識もないのに快く引き受けてくださった。「この荒野で戦い続けることを決めた彼女たちに、ありったけの拍手と祝福を送りたい」――。“彼女たち”の中に、おそらくわたしも含まれている。以来、つらいときは西さんの帯文を思い出し、自分を奮い立たせてきた。
「1日1時間読書」を始めるにあたり、真っ先に手に取ったのは西さんの新刊『わたしに会いたい』(集英社)だった。コロナ禍以前の2019年より、自身の乳がん発覚から治療を行った2022年にかけて発表された作品を集めた短編小説集だ。主人公たちは、「体」になんらかの不都合、あるいは違和感を抱いている。しかし「体」と向き合うことで、彼女たちの人生は確実に豊かになっていく。
素晴らしい本だった。帯に「この本を読んだあと、あなたは、きっと、自分の体を愛おしいと思う」とあるが、わたしはまさにこの本を読んだあと、自分の体を愛おしいと思った。雑念恐怖症であることも全部含めて、自分という人間が愛おしいと思った。雑念恐怖症というのも、捉え方によっては可笑(おか)しいようにも思えるし、不都合は多々あれど、わたしはこの「体」と一緒に生きていきたい。

人はだれしも、口にしないだけでいろいろなものを抱えている。そういう人間たちが、傷つきながら、寄り添いながら、この世の中に生きている。
文・イラスト=尾崎ムギ子