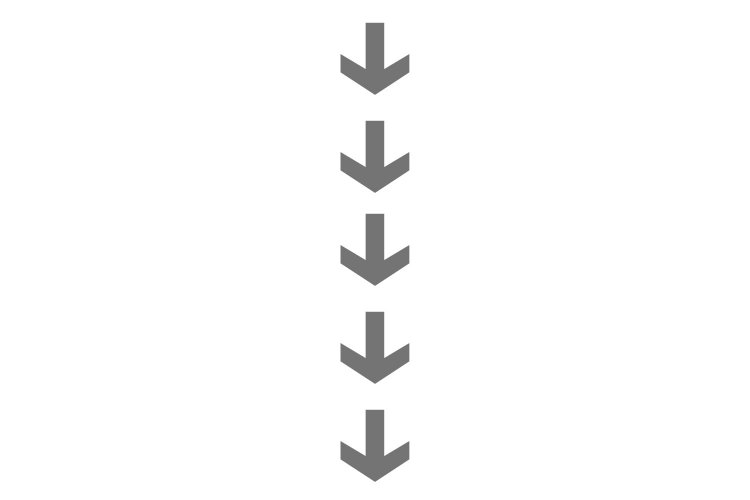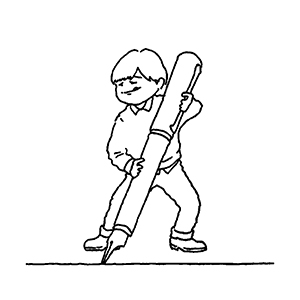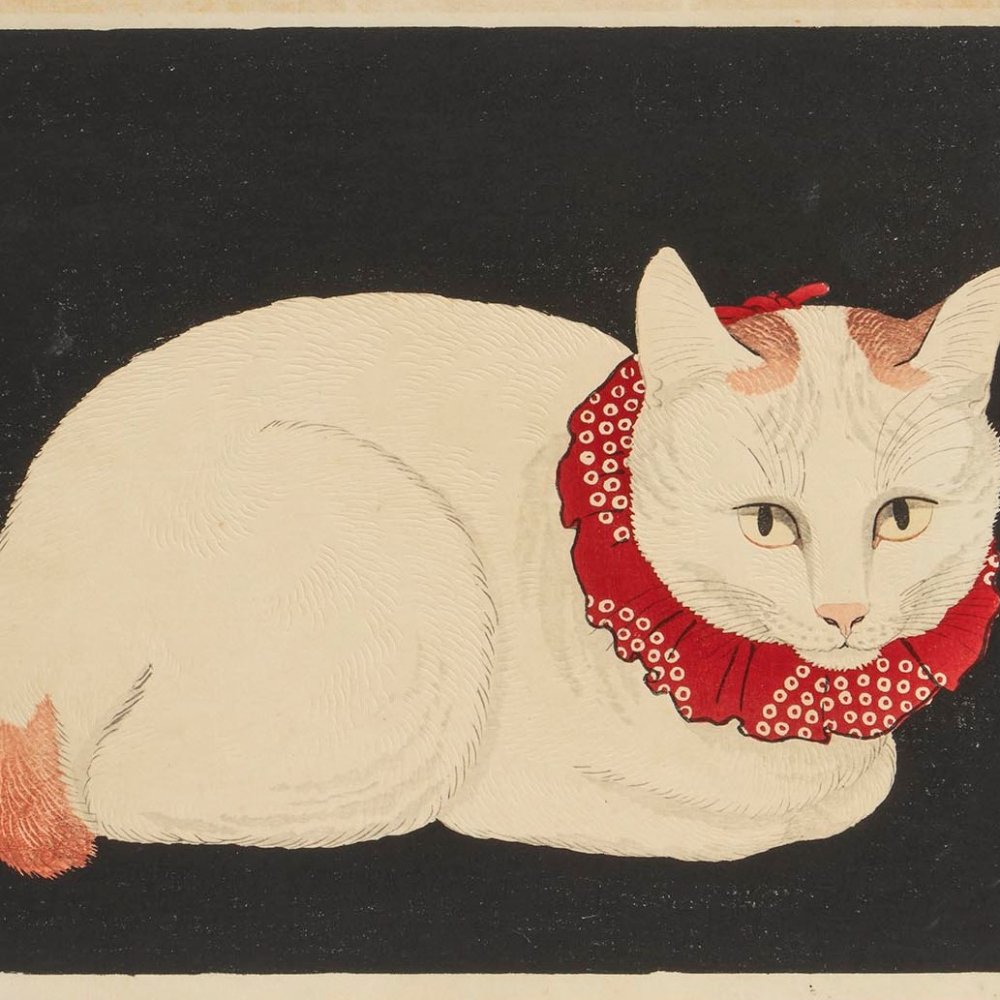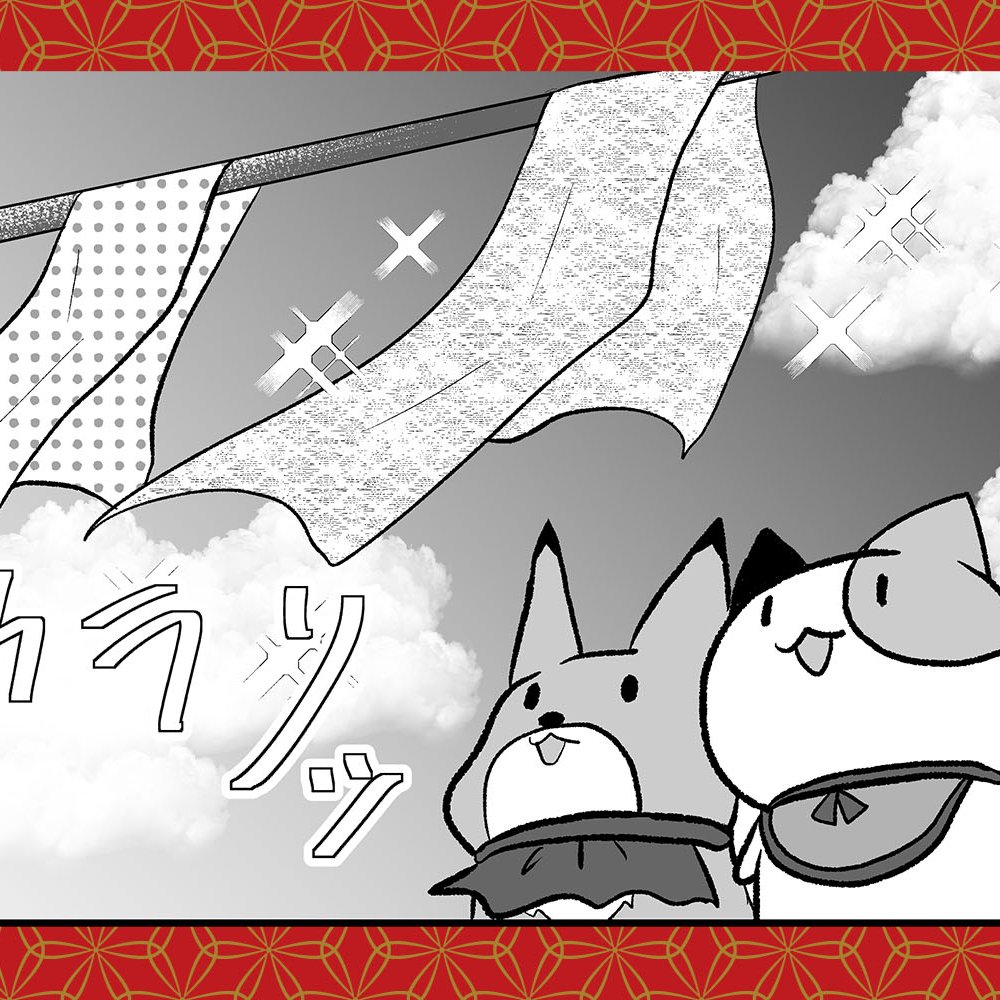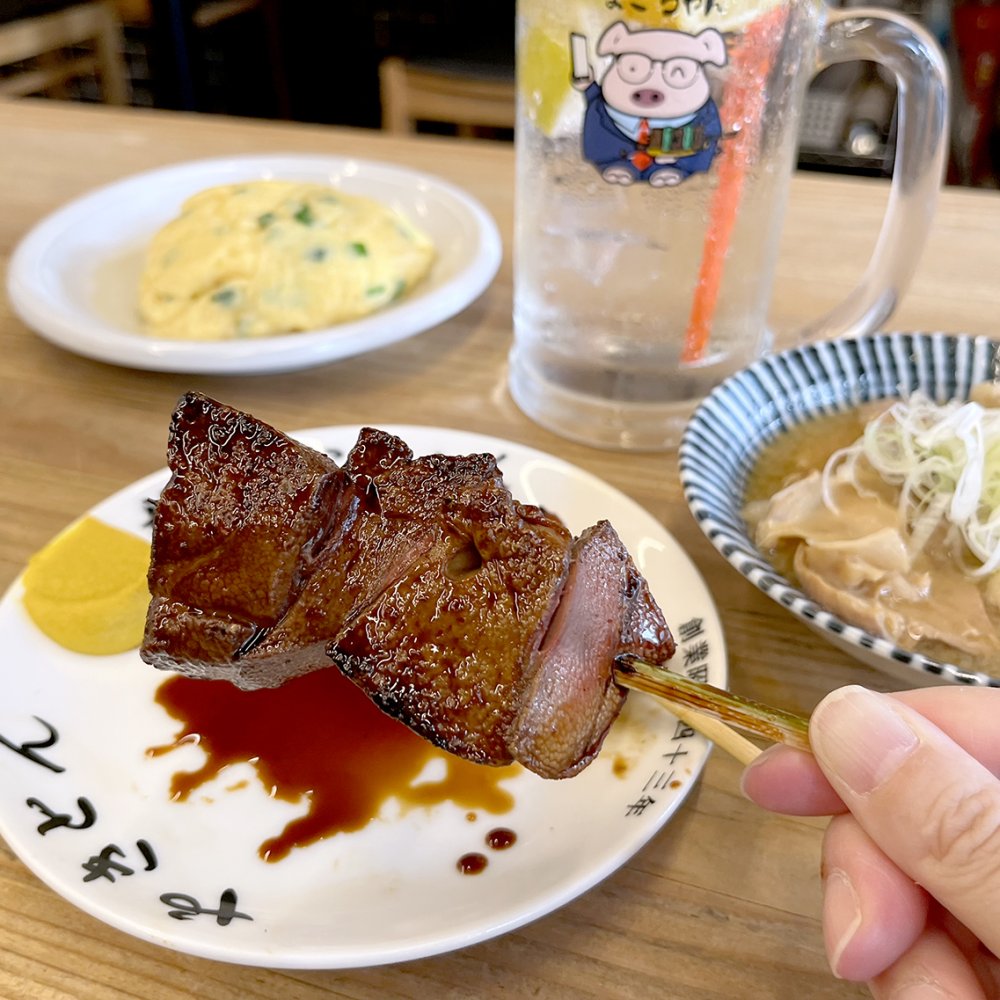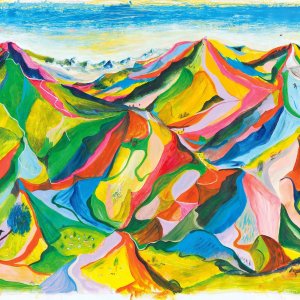第1問
ヒント
あまりに有名!
正解は……新宿(青梅街道ガード)
東京で最も有名な架道橋なのではないかと思われる、通称「新宿大ガード」。中央線や山手線、埼京線、湘南新宿ラインなどが通る線路の下には、計10車線もの車道が並ぶ。西には青梅街道、東口には靖国通りが延びているといった具合に、いくつもの道路の起点になっている。交差点にも「新宿大ガード西」という名前がついているし、付近の飲食店は「新宿大ガード店」という店舗も多く、一大ランドマークといって差し支えないだろう。写真は橋の西側からの眺めで、中央・総武線各駅停車の車両の黄色いラインが写っているほか、橋の奥には「西武新宿ペペ」の茶色いビルや歌舞伎町の繁華街が見える。
歩道部分の壁面は一部がギャラリーとして整備され、筆者が訪れた際には昔の新宿の風景写真が掲示されていた。これがまた見応えあって最高に楽しいので、散歩好きにはぜひとも訪れてみてほしい。
第2問
ヒント
橋の脇にはレンガのアーチが続いている。
正解は……神田(千代田橋ガード)
神田駅のすぐ南にあり、中央線、山手線、京浜東北線の線路が通る橋。ちょうど橋を渡っているオレンジ色のラインの車両は言うまでもなく中央線だ。下を通る道路はここから東が神田金物通り。写真は西側(山手線の内側)から見たところで、反対側には新幹線の架道橋も架かっている。また、すぐそばには神田駅ホームの下にあたる新石橋架道橋もある。
このあたりの特徴はなんといっても、何連もアーチが連なる赤レンガ。明治から大正時代にかけ、新橋駅~上野駅間で竣工した高架の一部だ。山手線の内側、橋の西側では古い橋台の石と思われるものを見られる。
第3問
ヒント
国道1号を跨ぐ。
正解は……五反田(五反田架道橋)
五反田駅のすぐ北側、山手線や埼京線の線路が通る橋。写真は東側(山手線の内側)から見たところで、下をくぐる道路は桜田通りと呼ばれる区間の国道1号だ。橋の上には五反田駅のホームドアや屋根が写っているので、これが駅だとわかればある程度絞り込むことができたかもしれない。
橋の東側は高輪台に向かって上り坂になっていることもあり、最大8車線がずらりと並ぶさまが圧巻の景色だ。
第4問
ヒント
橋(ガード)には付近の坂の名前がついている。
正解は……西日暮里(間之坂ガード)
西日暮里駅のすぐ北、山手線や京浜東北線の線路が通る橋。写真は西側から見たところで、五反田同様に橋の上は駅のホームだ。ちょうど京浜東北線の車両が停まっていて、水色のラインが写っているのが大きなヒントになったはず。橋の下を通る道は道灌山通りで、反対側には新幹線の高架、さらにその先には東北本線などの高架も並んでいる。
上野駅~赤羽駅あたりにかけて京浜東北線の線路は武蔵野台地の際を走るのだが、ここは台地を切り通した部分。道灌山通りは、ぎゅっと掘り込まれた谷底の地点で線路をくぐるというわけだ。ちなみに間之坂(あいのさか)というのは、南から線路に沿って道灌山通りに下る坂の名前。
第5問
ヒント
そばに大きな池がある。
正解は……洗足池(洗足池第1架道橋)
第6問以降のヒントにもなるが、今回の出題で唯一JRではない路線の架道橋だ。東急池上線の洗足池駅のすぐ西にあり、写真はそれを南側から見たところ。白い欄干の形がしゃれていて、大規模な架道橋ではお目にかかれないであろう意匠。道幅はなかなかの狭さだが一方通行ではなく、歩行者と車が譲り合いながら行き交う場所でもある。
このすぐ近くには、東京で最も低いガードといわれている場所がある。桁下の高さが1.5m程度しかなく、しっかり屈まないと通れないほど。厳密には「架道橋」ではないようだったため出題からは外したが、個性的なガードの1つとして欠かせないスポットだ。
第6問
ヒント
かつて「橋」があった場所。
正解は……東京・丸の内(呉服橋ガード)
東京駅の北側にあり、駅から北へと延びる数々の線路が通る橋。写真は線路の西側(丸の内側)から撮ったもので、山手線の車両が写っている。手前にあるかなり高い高架橋は中央線の線路だ。
このあたりの旧町名は呉服町。かつてはここに外堀を渡って丸の内と八重洲を結ぶ呉服橋がかかっていて、そこに呉服橋門と呼ばれる門があった。現在の橋(ガード)とは90度向きが違うものの、そのままガードの名前に「呉服橋」が受け継がれているというのもおもしろい。架道橋やガードの名前には古い地名が残っていることが多いのだが、ここはまさにその一例といえる。
第7問
ヒント
以前は駅ホームがあったが、今はない。
正解は……飯田橋(飯田橋通ガード)
飯田橋駅の東側、総武線や中央線が通る橋で、下の道路は目白通りだ。写真は南側から見たところで、通過する中央線のオレンジ色のラインがわずかに写っている。線路のすぐ北側には外堀と神田川の合流地点があり、そこに架かる橋が飯田橋。神田川を渡る橋/通る道/越える橋(ガード)……という、解体してみると幾重にも重なった名前であるというのもおもしろい。
2020年に飯田橋駅のホームが西側へ移設されるまでは、この橋の上もホームだった。線路がぐいと曲がっている地点で、飯田橋通ガードはまさにそのカーブのど真ん中。カーブのせいで電車とホームの間に隙間が空いてしまうため、移設工事がされたというわけだ。厳密に言うと2025年2月現在はまだホーム自体は残っているのだが、橋上に電車が停まることはもうない。
第8問
ヒント
開かずの踏切問題の解消のためにできた。
正解は……東中野(桐ヶ谷ガード)
東中野駅の東側、中央線(や中央・総武線各駅停車)が通る橋で、神田川がつくった谷に向かって下り坂になっているところに架かっている。写真は南から見たところで、下を通るのは神田川とゆるく並行する区検通りだ。
桐ヶ谷は近辺の旧地名で、ガードの地点より少し西側には、かつて桐ヶ谷踏切という開かずの踏切があった。渋滞緩和のために線路をくぐる迂回路がつくられ、現在の姿になったというわけだ。区検通りがこの場所でひょいと東側に曲がっているのはそのためで、もとの道筋は行き止まりになっている。
第9問
ヒント
地下鉄の駅がこの地下にある。
正解は……両国(亀沢町架道橋・亀沢町ガード)
両国駅の東側、総武線が通る橋を南側から見た写真。橋をくぐる道路は清澄通りで、地下には地下鉄大江戸線の両国駅がある。すぐ目の前は『江戸東京博物館』という場所だ。
両国橋駅(現・両国駅)~本所駅(現・錦糸町駅)間は、当時の総武鉄道が明治時代に建設。神田駅の項で触れた新橋駅~上野駅間と同じく、日本で最初期の高架鉄道の区間だ。現在の地名は墨田区亀沢だが、架道橋(ガード)の名前になっている亀沢町というのは旧地名である本所亀沢町から来ているもの。
今回出題した高架橋のなかでは、のっぺりした見た目が特徴的だ。実は高架下にある居酒屋の看板を見れば両国とわかるのだが、そのヒントなしですぐに見抜いた達人がいたらなかなかの実力!
第10問
ヒント
反対側には新幹線の高架もある。
正解は……大崎(百反架道橋・百反ガード)
大崎駅の東側、山手線や横須賀線が通る橋を北側から見たところ。南側には東海道新幹線の高架も並んでいる。周囲には工場が多いこともあって人通りは少なく、なかなか通る機会のなさそうな場所だが、この道自体は線路が通る前からあったものだ。写真ではわかりづらいが、橋の下の壁にはかわいらしい壁画があり、2010年の壁面美化整備の際に品川小学校の児童の作品をもとに描かれたものだとか。
架道橋(ガード)の名前になっている「百反」は「ひゃくたん」と読み、大崎駅の西側には百反坂や百反通りもある。百反坂はもともと坂が階段だったため「百段」から転じた……というのが通説のようなのだが、明治時代の地図には駅の東側に百反と書かれているのが見てとれる。当時周囲は田んぼだらけだったことから、「反」は五反田と同様に田んぼの面積の単位で、この一帯を表す地名が「百反」だったのではないかと筆者はにらんでいる。

以上で、全10問終了! おつかれさまでした。街歩きの達人はもちろん、鉄道好きであればより好スコアを狙えるクイズだったのではないだろうか。
解説でも触れたように、架道橋やガードの名前には古い地名がついていることが多く、それをたどるだけでも十分たのしい。土地や鉄道の意外な変遷がわかることもある。今回も現地を歩くうちに謎が生まれ、古地図や資料をあさって納得したことがいくつもあった。架道橋やガードを起点に歴史をたどる散歩、ぜひお試しあれ。
文・撮影=中村こより