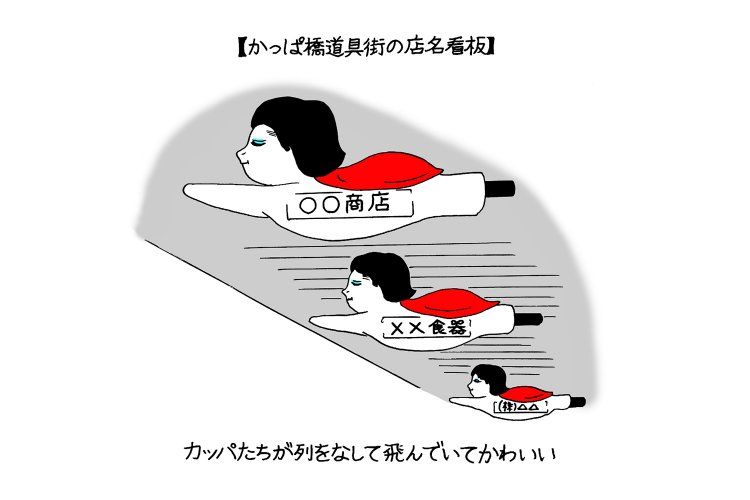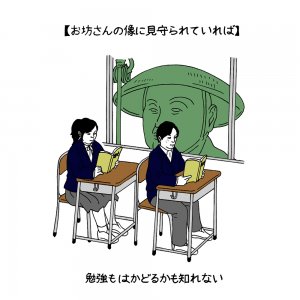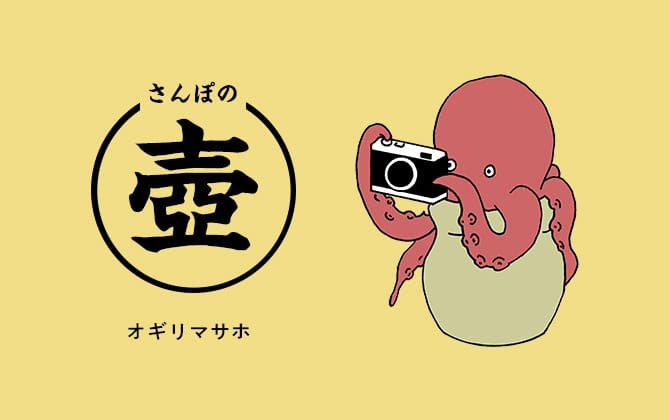サビ置き看板のサビ具合を見ていきたい
しかし、なぜ置き看板がサビゆくままにされているのだろう。ブロック塀に固定されたサビ看板は取り外すのも一苦労だろうが、置き看板ならすぐに撤去・交換できるはずだ。ところが多くのサビ置き看板はそのまま放置され、サビ放題にサビた結果、中にはもはや看板としての役割を果たさないものまで存在する。そうしたサビ置き看板のサビ具合を見ていきたい。
まず、サビはわずかな箇所からスタートする。

まだまだサビなさそうなカラオケ店看板。しかしサビは油断したところから拡大していく(奈良)。
そのうち全体をうっすら覆うようになり、小麦色に焦げていく。

トーストならば丁度よい焼き具合の看板(下北沢)。

置き看板に多く見られる、駐車禁止の看板(王子)。
全体的に塗装がしっかりしている置き看板はサビの侵食具合が少なめになる傾向にある。

ところどころサビてはいるが、原型を保っている看板。しかし実際稼働しているかは確かではない(千歳船橋)。
全体に塗装がされているからといって、安心してはいけない。よく見る「たばこ」の置き看板も、

今はまだ綺麗なたばこ看板(館林)だが……
長い時間が経てば全面真っ茶色に変わってしまうのだ。

いずれこうなってしまう。字体を見ると、舘林のものより時代は古めだろうか(東村山)。
中には設置年が異なるのか、同じ場所にありながらサビ具合が異なっている看板もある。

「キケン物等収集」に先立って、「ごみ収集」看板が置かれたのだろう(館林)。

内容は全く同じ看板だが、左に行くに従ってグラデーションになっているのが芸術性が高い(調布)。
こうしたグラデーション看板は、サビゆく経過を一目で眺められて楽しい。
サビが進んだ結果、本来の色遣いから反転してしまう看板もある。酒店の店先に置かれた郵便看板は、当初はおそらく白地に赤だったものだろうが、白地のサビが進み、赤が退色したことにより、見事に反転してしまっている。

現役で稼働する置き看板。〒マークにうっすら赤みが残る(上用賀)。
反転しても退色しても、看板に書かれた内容がはっきり読み取れる場合は、まだ看板としての機能は果たしている。

ぴちょんくんは本当は水色だが、全く別のキャラになっている(柴崎)。

もとの字の色が比較的残っているので、これはこれで美しい看板(館林)。
そもそも看板に書かれている内容が、現在の状況に合致しているか否かというのはまた別の話となるわけだが。

今フィルムカメラがブームだというので、写ルンですもフィルムももしかして売っているのだろうか(大山)。
「サビ看板」鑑賞の心得
ここからは、判読すら困難になっていく重度のサビ看板を見てみたい。サビ具合が少なくても、そもそもの文字が薄い場合や、サビに隠れてしまう色の場合、判読は難しくなる。

店名ははっきり分かるが、「ここに駐車しないでください」という肝心の文字が消えている(神田)。

老朽化で閉館した渋谷図書館の看板。文字にサビが出てしまったタイプ(渋谷)。
さらに焼きすぎのトーストのような色になっていくと、次第に文字も絵も見えなくなり、

なんとなくニュアンスは理解できるが、下部は判読不能に(下北沢)。
ついに真っ黒焦げになる。真っ黒焦げになっても文字だけは残る特殊なケースもあるが、

トーストなら食べられないほどの真っ黒焦げだが、奇跡的に文字が残った(調布)。
大抵はもはや何が書いてあったのかすら分からない状態になってしまうのだ。

パッと見は真っ茶色の板であるが、近寄ればかろうじて判読できる(北砂町)

もはや何が書かれていたのか分からない。存在意義を問いたい(神田)。
こうなれば、もはや看板の意味を全くなさなくなってしまう。
それでも街中には、サビ置き看板は今日も存在し続けている。これは看板というより、一種の芸術作品なのではないだろうか。現に世の中には、鉄サビを自身の作品の特徴としている芸術家も多く存在する。われわれは街中の彫刻作品を鑑賞するのと同じような心持ちで、サビ置き看板を眺めていくべきなのかも知れない。
誰もが一度は落とし物をしたことがあるだろう。これが財布やスマホなどを落としたのであれば一大事である。しかし、全てがそのようなわかりやすい価値のある落とし物ばかりではない。他の人から見れば取るに足らないようなものであっても、落とした本人にとってはダメージが大きいものもある。街を歩いていてそのような落とし物に出くわすと、「落とした人はきっとすごくがっかりしているんだろうな……」と、何だかとても切ない気持ちになってしまう。今回はその「切ない落とし物」を、切なさの度合いに応じて見ていきたい。
これまで全国のデザインマンホール蓋をスルーしてきた、という話を以前書いた。そのことを私は深く反省し、以降外出するたびにマンホールを撮影し、マンホールカードを集めるように心がけるようになった。ようやく20枚ほど集まってホクホクしている一方で、新しいマンホールカードは次々と発行され、今や第19弾・941種まで増加している(2023年4月28日現在)。集めるスピードは全く追いつかない。ところで下を向いて歩いているうち、マンホールとは異なる存在が目に入るようになった。それが消火栓蓋である。消火栓とは、火災の時に消火活動に用いる水を供給する設備であり、地下に設置されているものには鉄蓋が被せられている。この鉄蓋がマンホール蓋と同じような作りになっているため、一括りに「マンホール」と呼んでしまうのであるが、消火栓はマンホールのように作業員が出入りできるわけではない。ところがこの消火栓蓋も最近、マンホール蓋と同様にさまざまなデザインが施されてきているのである。今回はこの消火栓蓋に焦点を当てていきたい。
以前も当コラムで述べたが、基本的にいつも下ばかり向いて歩いている。そんな私も、たまには上を向くことがある。それはアーケード商店街を歩いている時だ。