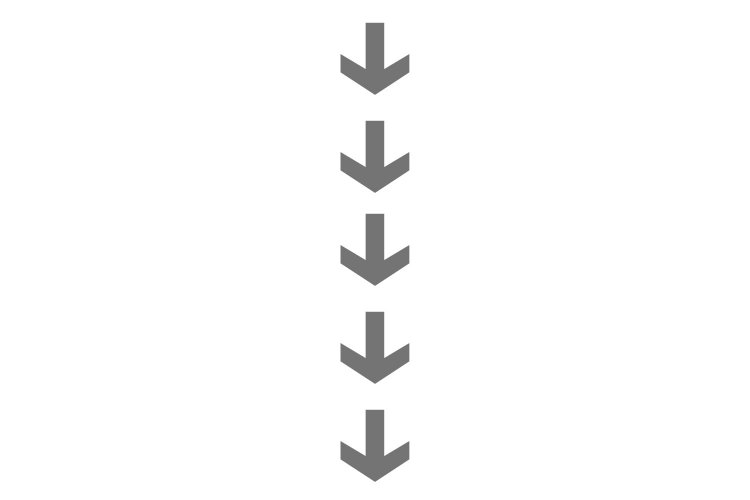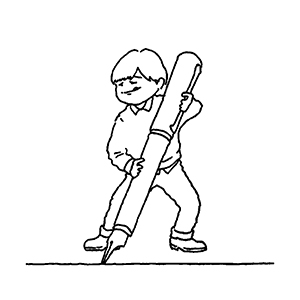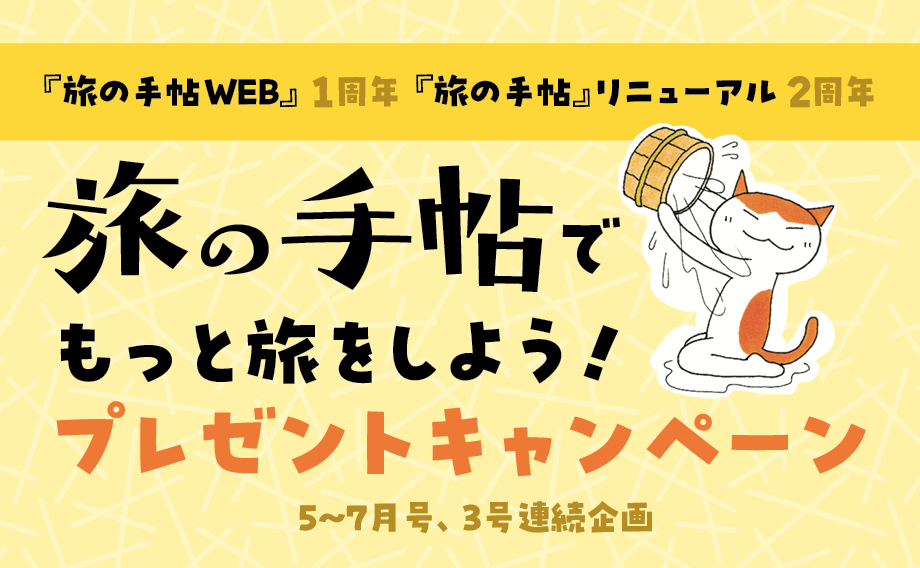第1問
ヒント
『さんたつ』編集部から最寄りの階段。
正解は……千代田区神田駿河台・神田猿楽町(御茶ノ水駅・神保町駅)
第1問というよりは例題にしたほうが適切かもしれない。駿河台と神保町方面とを結ぶこの男坂は、すこし北西にある女坂とセットで東京の階段といえば名が挙がることが多い場所。駿河台と猿楽町の境界一帯は台地の際で、いわば崖っぷちだ。関東大震災の復興事業で男坂・女坂が造られるまでは、台地の上と下を行き来する通路がなかったのだとか。
その姿は、神社の参道にありそうな一直線の急な石段。途中に1カ所踊り場があり、上る人はたいていここで一度「ふう!」となる、しっかりキツい階段だ。
神社の参道には直線的な坂や階段に男坂、ゆるやかでカーブがあるような階段に女坂と名付けられることが多く、神田明神や湯島天満宮、愛宕神社、高尾山薬王院など挙げればきりがない。しかし、ここは参道ではないのに男坂・女坂と名前がついているという、ちょっぴり珍しい場所でもある。
第2問
ヒント
すぐ脇は神社。
正解は……大田区山王(大森駅)
大森駅西口を出ると、目の前に鎮座するのが神明山天祖神社(八景天祖神社)。その脇にある階段だ。
大森駅西側に広がる山王、馬込などの一帯は、関東大震災後に芸術家や文士が多数移り住み交流を深めていた地域。馬込文士村と呼ばれ、居住跡などゆかりのスポットをめぐる散策もたのしい。階段の壁には文士村の説明や人物を紹介するレリーフがあり、ここから答えを導き出すことができた人も多いはず。
なお、東京23区内の京浜東北線の線路は武蔵野台地の東端に沿うように走っていて、大森駅も東側は低地、西側は台地。地形による街の色のコントラストが強い場所だ。
第3問
ヒント
高級住宅地にある。
正解は……品川区北品川(五反田駅・品川駅)
住所でいうとギリギリ北品川なのだが、いわゆる北品川(品川宿の北あたり)ではなく、品川区東五反田と港区高輪に挟まれた地点。城南五山と称される高級住宅地の高台のひとつ・島津山のあたりだ。地名ではイマイチ思い浮かばないという方は、五反田駅と品川駅を結んだ線のちょうど中間あたりと考えてもらえれば、だいたいの位置がおわかりいただけると思う。付近には「まぼろし坂」と名のついた坂や、品川の高層ビル群を望む「高輪で一番長い階段」と呼ばれる階段もある。
余談だが、学生時代に筆者が山手線を歩いて一周した際、品川駅~大崎駅間で線路とはぐれてこの一帯に迷い込んだ。田舎から上京してきた世間知らずの学生が、そうと知らずに足を踏み入れた高輪台。家々の高級感とは対照的に細く曲がりくねった坂道や階段が連続する複雑な景色を前にして、思いがけず感じたときめきはいまだに忘れられない。
第4問
ヒント
階段の上からは団地が見える。
正解は……北区赤羽西(赤羽駅)
大森駅につづく、武蔵野台地の東端・京浜東北線シリーズの2つ目! 赤羽も、東側に低地、西側に台地が広がり、崖や谷も多い凸凹地形が興味深いエリアだ。この階段は、弁天通りが走る谷に向かって下る階段で、付近は階段や坂の宝庫。
現在静勝寺があるあたりには、かつて太田道灌が築城した城があったといわれている。山や丘が天然の要塞として活用されている例は多いが、こうして階段の上から谷を見渡すと、たしかに完璧な要塞になるであろうことが実感できる。
第5問
ヒント
大ヒットしたアニメの聖地。
正解は……新宿区須賀町(四谷三丁目駅)
大森駅前の明神山天祖神社と同様、台地の際にある須賀神社。その脇にある一直線の階段だ。神田駿河台と同様に男坂と呼ばれ、すこし西には傾斜の緩やかな女坂がある。
写真を見ただけではちんぷんかんぷんという人でも、ヒントで察しがついたかもしれない。階段の上から見下ろした風景ならばすぐに気づいたという人もいるだろう。というのも、ここはアニメ『君の名は。』で登場し、聖地として人気を博した場所だから。今回撮影に向かったのは平日の昼間だったにも関わらず、階段には観光客がわんさか集まってアニメのワンシーンと同じ画角で写真を撮ろうと試行錯誤していた。
第6問
ヒント
踏切が近い。
正解は……渋谷区円山町(神泉駅)
神泉駅の北口を出てすぐ、踏切のそばにある階段。石垣のような古い壁、古い階段と手すり、その手前に新しめのタイルの階段が並んでいて見応えがある。タイルの階段はおそらく写真左の建物の敷地内なのだろう。古い階段はあるにもかかわらず、新たに並べて階段を造ったところに優しさを感じられる。
渋谷川へ流れ込む宇田川の神泉支流がつくった谷に位置する神泉駅は、周辺も起伏に富んだ地形が広がっている。井の頭線の線路は神泉駅の前後でトンネル内を走るが、駅と踏切部分だけひょっこり地上になるので、この地点が窪地であることがわかりやすいだろう。かつての湧水地で地名にも「泉」がつくという、なんとも親切な地形と地名なのである。
第7問
ヒント
尾根道から下る階段。
正解は……文京区大塚(新大塚駅)
新大塚駅の南、春日通りから西へ下っていく路地にある。この付近の春日通りは台地上の尾根を走っていて、道の両脇は谷。どちらへ行っても坂や階段を下ることになり、谷とその向こうの台地を見渡す景色が待っている。
写真1枚に収まりきらなかったが、この階段は3段階になっていて、緩やかながらかなりの高低差をつないでいることがわかる。実際、階段の上と下では10m近い標高差があり、これは第1問の神田駿河台の男坂に匹敵。今回出題する階段のなかでもトップクラスだ。
第8問
ヒント
川が近い。
正解は……中野区東中野(東中野駅)
新大塚と少々雰囲気が似ているこちらは、東中野駅の東側の階段で、下っていった先には神田川が流れる。踊り場が3つあって緩やかだが長く、台地の上から神田川のほとりと同じ程度まで下るため、高低差は全10問中で最も大きい。
ここから少し南に下れば、もうそこは神田川。川にかかっている橋は南小滝橋という名前で、より下流に小滝橋がある。この小滝橋というのはかつて堰があって小さな滝のようになっていたことから名前がついている。紹介した階段があるあたりも、旧地名は小滝町(小瀧町)だ。
第9問
ヒント
「⚪︎坂」という名前がついている。
正解は……新宿区神楽坂(神楽坂駅・牛込神楽坂駅)
日本のモンマルトルと称されることもある神楽坂は、言わずもがな美しい階段の宝庫。なかでも神楽坂通りと大久保通りが交わる神楽坂上の交差点からすぐの場所にあるこの階段には、小さいながら駒坂という名前がついている。趣ある手すりのデザインが特徴的だ。
階段の上の地面の一部は扇状に石が並んだ鱗張りの石畳になっているのも、神楽坂らしさ満点。そばには瓢箪(ひょうたん)坂があり、ひょっこり現れる小さな階段なので「ひょうたんから駒」を意識して名付けられたような気もしなくもないが、由来は不明。
第10問
ヒント
山手線の線路がすぐ近くを走っている。
正解は……台東区谷中(日暮里駅)
日暮里駅の南、山手線などの線路脇にある台東区立芋坂児童遊園のそばの階段だ。もはやおなじみ、京浜東北線シリーズの3つ目で、付近は崖になっている。一段一段が高く斜めで歩きづらい部分もあって歴史を感じさせる石段と、その隣に整備された新しい階段が並んでいる。よく見ると古いほうの階段も一部補修された跡があり、複数の世代の階段が並んでいるものと思われる。両脇の壁も、片方は古い石垣、もう片方はコンクリートと対照的だ。
公園の名前についている芋坂とは、この階段のそばにある、台東区谷中から荒川区東日暮里に向かって下る坂。その間を山手線などの線路が横断しているため、坂は途中で途切れて跨線橋になっている。
ちなみに、一般的にGoogleマップでは階段の表示もあるのだが、なぜかここは普通の道として表示されてしまっている。惑わされて車で入ってくると行き止まりになるというトラップ階段である。

全10問、踏破! おつかれさまでした。道路や店などのランドマークになりうるものが少なかったので、歩いたことがないと推測が難しかったかもしれない。
坂が多いというのはしばしば「不便」「面倒」という文脈で触れられることも多く、車や自転車で通れない階段は特に嫌われがち。でも、地方の広大すぎる平野で育った筆者にとって階段とは屋内にあるものであり、上京するまでは「街なかに階段がある」風景に出合う機会など皆無だった。街にある階段は、実は東京らしい重要な風景のひとつであり、立体的で変化に富んだ風景を作り出してくれる魅力的な構造物なのだ。
文・撮影=中村こより