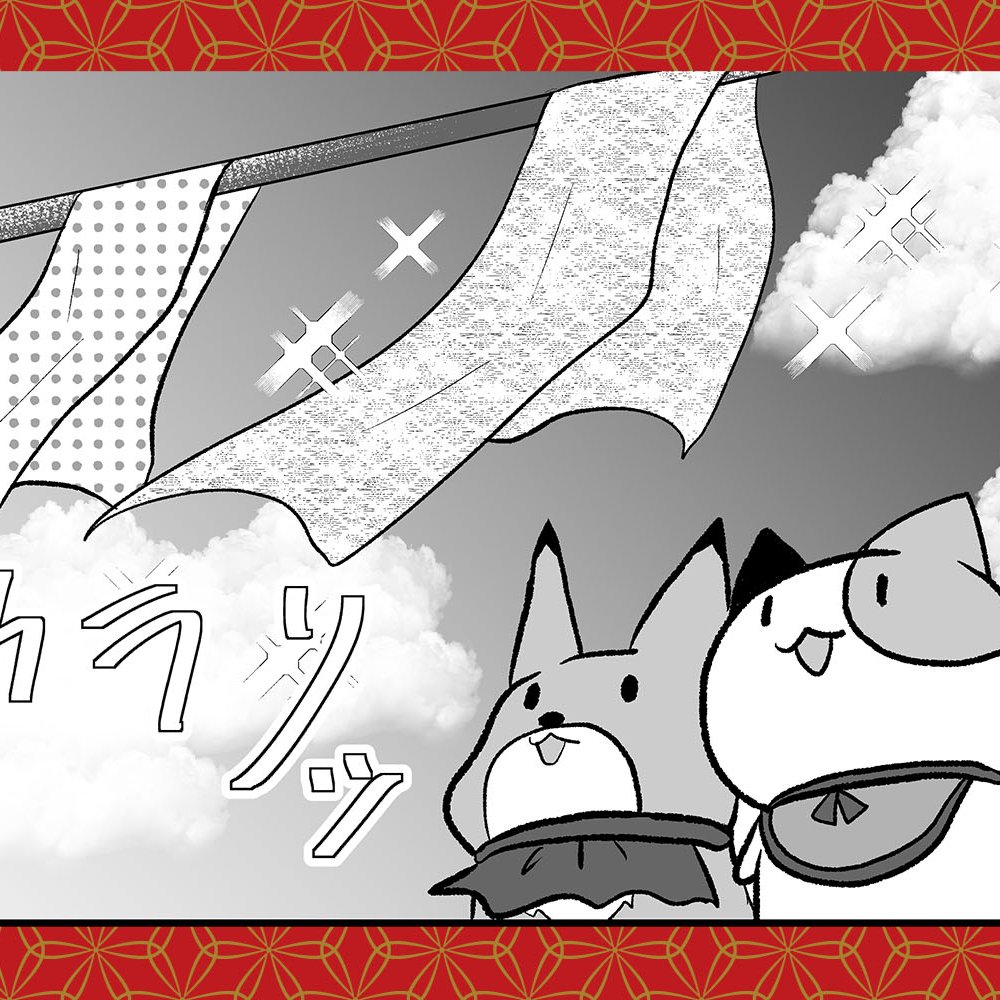先日もとある番組でラッパーの呂布カルマさんとディベート対決をするという仕事が舞い込んだ。ディベートなどろくに経験がなくてもいざやってみれば自分は案外イケそうな気がした。なぜそんな風に思ったのか。過去に他人のディベートを傍観したときも、「なんでそこで言い返さないんだ」「今の主張は矛盾してるだろ」など突っ込むポイントを私は把握していたからだ。ところが外野からゴチャゴチャ言うのと自分が実際にやるのとでは全く違う……と気づいた時にはもう遅かった。私はすでに舞台に上がっており、呂布カルマさんの圧倒的なディベート力に為す術もなく蹂躙(じゅうりん)されていた。鋭い指摘にしどろもどろになり、返答するのが精一杯で、自分が今何を喋(しゃべ)っているのかすらよくわからない。終了の笛が鳴ったのは開始から15分後。体感時間はその倍はあった。4人の判定員による結果は4対0。もちろん私の完敗であった。
負けるにしても負け方が情けなかった。バラエティー的な見せ場もなく、最初から最後までただボコボコにされ続けた。きっと視聴者は「こいつ何しに出てきたんだ」と思っただろう。期待に応えられなかった申し訳なさと、番組スタッフに気を使われているような空気を察し、そそくさとスタジオを後にした。
「言葉売り」という救い
外に出ると昼過ぎの日差しが照りつけていた。歩いて地下鉄の駅へ向かう途中、後悔の念がどっと押し寄せた。昨晩、友人と軽くディベートの練習をしてはいたが、もっと入念に準備しておくべきであった。別にその道のプロではないとはいえ、お金をもらって出演するからには最善を尽くす義務がある。今回の自分はプロとしての仕事ができていなかったと言わざるを得ない。いつもの失敗をまた繰り返してしまった。
多少心の救いとなったのは、その日の夜、「言葉売り」の予定が入っていたことだ。言葉売りとは、お客さんに悩みを聞かせてもらい、その場で格言風の一言を考え色紙に書いて売るという活動である。以前フリマで売るものがなくなり、相田みつをっぽい言葉を路上に並べて売っている人たちのパロディとしてやってみたら、思いのほか需要があったので、それ以来なし崩し的に続けてきた。
その日は友人主催のイベントに出店することになっていた。たくさん売って人と交流すれば、ディベートで負った傷も少しは癒えるだろう。夕方会場入りしフロアの片隅でお客さんを待つ。場内は徐々に人が増えてきたが皆ライブパフォーマンスを見て盛り上がるばかりで、言葉を買いにくる様子はない。私はバーカウンターに何度も酒を買いに行っては自分の場所に戻りひとりで飲んでいた。
全ての催しが終了し、そろそろお開きの時間。張り切って色紙を30枚も買ってきたが、そのほとんどが売れ残ってしまった。仕方なく帰り支度を始めていたところに女性2人組がやってきた。彼女たちは以前も私の言葉を買ってくれたそうで、色紙は現在も部屋に飾ってあるとのこと。私は久しぶりに人と話せたのがうれしく、自ら話題を振って会話を引き延ばしていた。そこに突然2人の友人らしき女性が割り込んできた。「ちょっと、成田凌いるよ!」彼女の指さす方を見ると、確かに今をときめく俳優・成田凌さんがバーカウンターに寄りかかって飲んでいた。先ほどから高身長で異常にルックスの良い男性がいるなとは気づいていたが、まさか成田凌だったとは。たちまち女性陣は私の存在を忘れ、すごい勢いでバーカウンターに走り成田氏を取り囲み始めた。
成田氏はまるでふらっとコンビニに行くついでに立ち寄ったかのような、部屋着にサンダルといった出で立ち。いっぽう私は勝負Tシャツを着用し頭髪をジェルで整えて臨んでいた。いくら身なりを整えても、またいくら付け焼き刃的な言葉で衆目を引こうとしても、人として圧倒的魅力を備えた成田凌の前で、私は本当に無力だった。
ひとりぼっちで所在をなくしている自分と、輝かしいオーラを放ち人々に取り囲まれている成田凌との対比を、誰の目からも認識されたくなかった。私は急いで色紙をカバンに詰め、誰に挨拶することもなくその場を立ち去った。
帰宅し湯船につかっても敗北感が残っていた。もっとも、冷静に考えてみれば、今をときめく超イケメン俳優がそこにいれば人が集まってくるのは当然だ。最初から同じ土俵にいないのに、何を変なプライドを持って張り合っているんだ。まさか自分が成田凌より人気者だとでも思っていたのか……違う。きっと問題の本質は、今日の自分に誇りを持てなかったことだ。ディベートをやっても言葉売りをやっても何も結果を残せなかった。成田凌さんは確かに超人気俳優だ。ただ、自分にはまた別の魅力があるはずだ。今日一日結果を残し自分に自信を持てていたら、「成田さん、本物だ!会えてうれしいっす!」とてらいなく話しかけることもできただろう。
たとえばもし呂布カルマさんなら、どんな芸能人を前にしても臆することはないだろう。彼にしかできない仕事を全うし、他者にない存在感を確立しているからだ。私も自分にできる仕事を誇りを持ってやっていくしかない。そう考えても一体何から手をつければいいのか、答えはすぐには見つからなかった。
文=吉田靖直 撮影=鈴木愛子 写真=(C)相田みつを美術館
『散歩の達人』2023年1月号より