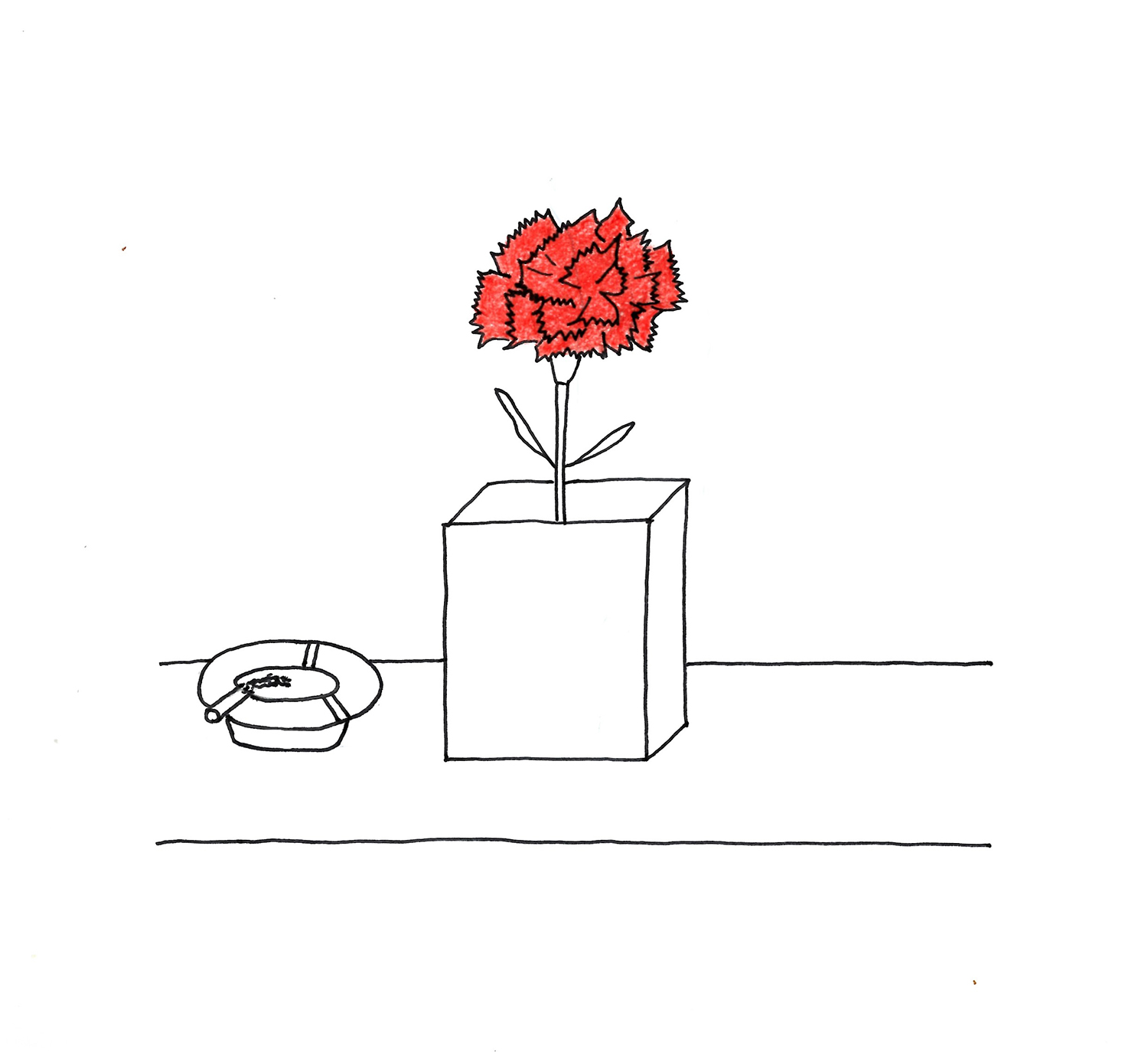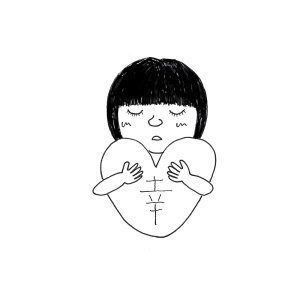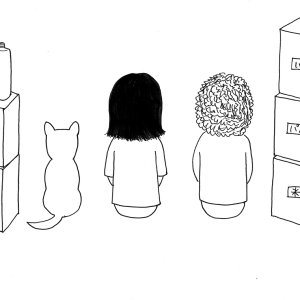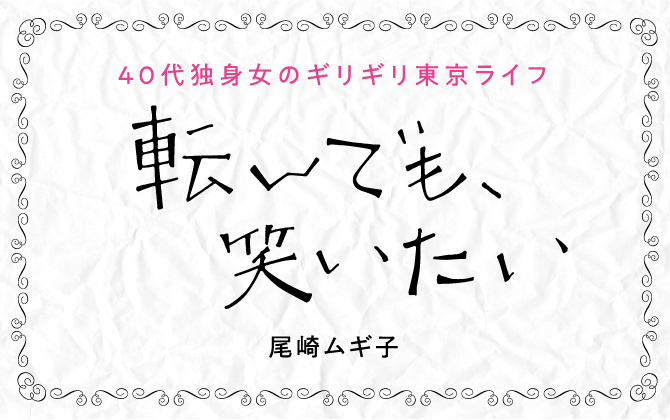母にはこの連載のことを内緒にしてきた。わたしが自分や家族のことを赤裸々に書いていると知ったら、母はショックで死ぬかもしれない。どうにか隠し通すつもりでいたものの、いつかこの日が来るとどこかで覚悟はしていた。
母はわたしの前で初めて声を出して泣いた。人は本当に怒り悲しむと、大根役者の演技のような泣き方をするのだなと思った。実の親にこんな泣き方をさせてしまい、なんて親不孝なんだろうと思った。最終的に「縁を切るから出て行ってくれ。殺人事件が起きかねない」と言われ、わたしは家を出ることになった。
引っ越ししようにも、金がない。こういうとき、人を頼れないのがよくない性格だと思う。友だちにも彼氏にも相談できず、区役所に電話をかけた。事情を話すと「とにかく荷物をまとめて来てください」と言われた。小さなスーツケースに入るだけの荷物を詰めて、翌朝一番に区役所に行った。

区役所の人に連れられて、とある女性専用アパートに向かった。DVを受けた女性など、行くところがない人がとりあえず生活できるシェルターのような施設だ。惨めだった。わたしはどこまで落ちていくのだろう。
アパートの外観はかなり古いが、部屋にはバス、トイレ、洗濯機、キッチン、食器類、テレビまである。さすがにベッドはないものの、新しい布団を一式支給してもらった。落ち込んでいてもしかたがない。この部屋から這(は)い上がっていくしかない。無心で拭き掃除をしてから、近所のスーパーで買い物をして夕飯を作った。
夜、一段落してテレビをつけると、近藤真彦が満面の笑みで『ギンギラギンにさりげなく』を歌っていた。その瞬間、昨日からずっとこらえていた涙がドバドバと洪水のようにあふれてきた。「ギンギラギンにさりげなく そいつが俺のやり方 ギンギラギンにさりげなく さりげなく 生きるだけさ」——。
この連載にすべてを賭けようと、1年間なにもかも赤裸々に書いてきた。ライターの師匠には「そんなに身を削っていたら、潰れるぞ」と言われている。結果、親に縁を切られたのだから、わたしは間違っていたのかもしれない。それでもそいつがわたしのやり方。マッチの歌が、ギリギリのわたしを肯定してくれた。
この歌の出だしは、「覚めたしぐさで 熱く見ろ」。そして「涙残して 笑いなよ」と続く。「ギンギラギンにさりげなく」もそうだが、すべてが相反する言葉になっている。人生なんて、相反することだらけ。人間なんて、矛盾だらけの生き物だ。そういう人間の物悲しさや、いじらしさを絶妙に表現した歌のような気がした。
人生、楽あれば苦あり。山あれば谷あり。いまのわたしは間違いなく「谷」にいるけれど、いつか山の頂上に登れる日が来るかもしれない。

悪いことは続くもので、翌日、工場のバイト中に脚がつったような感じになり、病院へ行くと膝の靭帯を痛めていた。わたしは膝が後ろ側に反っている(反張膝〈はんちょうしつ〉という)らしく、長時間立っているとどうしても膝が痛むとのこと。立ち仕事は難しいと判断し、バイトを辞めることにした。
飲まずにはやっていられない。久々に『居酒屋とんぼ』を訪れた。ママに家を出たことを話すとえらく心配された。カウンターには、母の日にわたしがママにプレゼントしたカーネーションがまだ飾ってある。5本あったカーネーションが、いまは1本。独りぼっちで寂しそうに見える。しかしこの花のように、寂しくてもなんでもしぶとく生きようと思った。
一刻も早く、いまのアパートを出なければいけない。朝から晩までスマホで物件を探し、不動産屋に問い合わせて内見させてもらう日々だ。しかし貯金がないため、初期費用を払える物件がほぼない。膝が治ったらすぐに新しいバイトを探さなければいけない。先のことを考えると不安でたまらないが、これまでだってどうにかなってきた。生きてさえいればきっとどうにかなる。
いまのわたしに神様から与えられた課題はひとつ。「死なないこと」。課題はたったひとつなのだから、きっとうまくこなせるはずだ。
文・イラスト=尾崎ムギ子