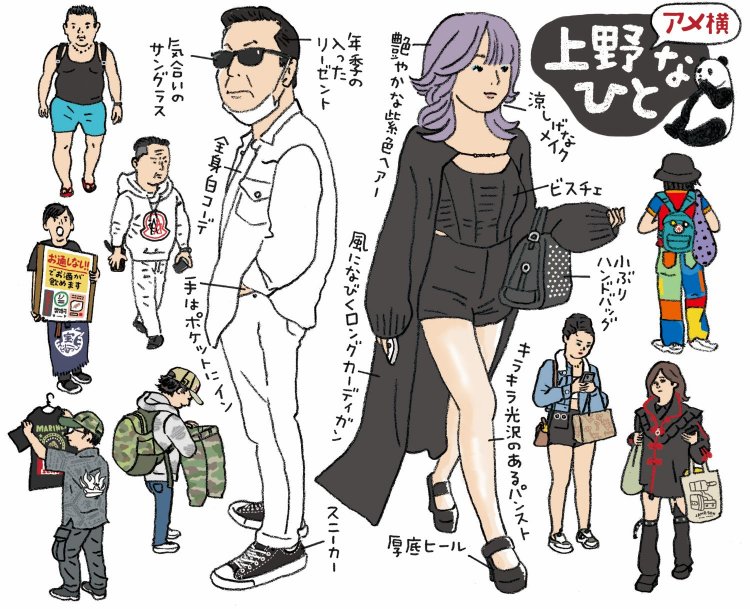店を救った妻のひと言。3代目夫婦が築いたとんかつの名店
アメ横と平行して走るほんの数十メートルの裏路地「たぬき小路」に、昭和22年(1947)創業のとんかつ専門店がある。戦後間もない頃から現在まで、地元住民に親しまれる『とん八亭』だ。いまは3代目店主の細川秀巳さんと和枝さん夫妻が切り盛りし、ランチタイム限定でオープンしている。平日もさることながら、土日は行列必至の名店だ。
物心ついたころから家業を継ごうと思っていたという細川さんは、高校卒業後、フレンチレストランで料理人のキャリアをスタート。その後ほどなく、海外のレストランで働くチャンスが訪れる。持ち前の行動力でソウル、ドイツと渡り歩き、スイスでは鉄板焼きレストランで料理長を務め腕を磨いた。
そうして30歳で帰国した秀巳さんは、ご両親とともに店に立ったのち夫婦でこの店を継いだ。「おふくろが14、5年ほど前に亡くなったんですけど、そのとき親父も引退するってことでかみさんと2人でやることになって」と秀巳さん。それまでほぼ専業主婦として小さなお子さんを育てながら家庭を守ってきた和枝さんに、突如とんかつ屋の女将としての仕事が加わった。
さぞや大変だったのでは、と聞くと「大変でしたよね、もう、半ベソでね」と秀巳さんが笑う。しかし、一方の和枝さんはやさしく微笑みながらもその表情は複雑だ。「結婚したときは義父母と主人の3人でやっていたんですけど、娘が3歳になるときに義母が亡くなってしまって。それで主人がお店をやめるって言いだして……」と和枝さん。
先代と秀巳さん親子の間に入ってお店を切り盛りしてきたお母さんがいなくなってしまったことで、秀巳さんが音を上げたのだ。そのことを聞いた病床の義母が寂しそうだったという話を聞いた和枝さんは決意する「やらなくてどうする!」。
「それでやろうよっていって、やっぱりやることになったって(義母の)病室に言いに行って」と、秀巳さんの隣で和枝さんはそう話しながら笑う。果たして、和枝さんの心意気が『とん八亭』を救ったのだ。女は腹をくくると強い。
以来、和枝さんはご主人の秀巳さんを支え、店を盛り上げてきた。ミシュランに選出されるほどの秀巳さんの料理人としての腕もさることながら、この店が名店といわれるのはこのご夫婦あってこそなのだ。
渾身のロースかつ定食の味噌汁もぬか漬けも、添えられたポテトサラダもすべて丁寧に手作り
一番人気は、赤身と脂身の旨味を堪能できるロースかつ定食。ごはん、自家製ぬか漬け、豚のスジで豚汁風に仕上げた味噌汁付きで、ジャガイモのゴロゴロ食感が残るポテトサラダが添えられている。ふかふかのキャベツとふっくらごはんは、それぞれ1回のみ無料でおかわりできる。「全部おいしいと思ってもらいたい」という想いが定食の1品1品に込められている。
淡いきつね色に揚がったロースかつの、まるでお風呂上がりの赤ちゃんの肌みたいなお肉の断面、脂身のツヤツヤ加減。まずは何もつけずにそのままひと口。「サクッ!」という心地よい音。「あ、旨っ」。思わずつぶやいてしまった。ほんのり桜色の赤身はしっとりやわらかく、衣は軽くてサックサクだ。
小鉢のぬか漬けは季節などによっても変わるが、本日は定番のキュウリに大根、ニンジンと、ぬか漬けには珍しいゴボウ入り。ぬか床は先代の女将さんが漬けていたぬか床をつぎ足しながら受け継がれているもの。「休みでも店に来てかき回す」というほど大切に使われている。やさしいお母さんの味が主役を引き立てる。
ところで、このやわらかいお肉とサクサクの衣にはどんな魔法がかかっているのだろう? まずはお肉。代々つきあいのある精肉店から国産の豚肉を仕入れ、手際よく丹念に仕込む。ロース肉の場合は肉質をやわらかくするために叩いたあと、平たくなった赤身の部分を両手で寄せて成形し再び厚みをもたせる。
このひと手間を加えることで、ジューシーに揚がるという。一方で、脂身の部分は厚くせず、平たいままになるように絶妙なさじ加減で形成されている。脂の旨味を引き出すベリーウェルダン(よく火が通った状態)に仕上がるようにするためだ。
そして豚肉がまとう衣には、粗挽きの生パン粉を使用。衣のサクサク感を出すためには、お肉につける前にパン粉に霧吹きで水をシュシュッ! とパン粉を湿らせる。パン粉つけは必ず注文が入ってから。作り置きはしない。手早くこれら一連の作業をこなす秀巳さんは寡黙だ。次々に入る注文のたびに、精魂込めて魔法をかけている。匠の魔法だ。
おいしく楽しく食べてもらうための心配りが店内のいたるところに
「『とん八亭』さんのとんかつには何が合いますか?」という質問には、調理に集中している店主に代わって店内に掲示してある貼り紙が答えてくれる。「お好みの物をご自由にどうぞ」とまず一筆。卓上に、とんかつソース、ウスターソース、岩塩、しょう油、からし、七味が並び、カウンター脇にはケチャップやマヨネーズもある。
「最後の味つけは、食べる人の自由にしていい。これって広い意味で日本の食文化のよさであり、食を楽しむ工夫でもあると思うんですよ」と、食べ方のこだわりはお客さんそれぞれにあっていいと秀巳さんはいう。
それでも迷ってしまう人がいるだろうと、貼り紙には「とんかつソースが甘いと感じるようなら塩を足してみてください」などと丁寧なアドバイスも添えられている。「おいしく食べてほしい」という店主のやさしさが感じられる、心にくい演出だ。
「こだわりの塩でどうぞ……だなんて、しゃらくせえ」。そういって笑いながら、自分がこだわるのはとんかつ一筋と、元祖下町育ちの店主は今日もおいしいとんかつを1枚1枚丁寧に揚げている。すべては食べに来たお客さん1人1人においしく食べてもらうために。「みなさんおいしいって食べてくれますけど、なんなら“すっげーおいしい”っていってもらいたいですね」と冗談めかして笑う秀巳さん。
しかし、それは冗談などではなく、秀巳さんの本心なのだろうと思う。お客さんにそういってもらえるように毎日真剣にとんかつに向き合い、丁寧な仕事を続けているのだ。
店を出てから、「ああ、すっげーおいしかった!」と心の中で店主にお伝えした。今度は誰かと一緒に食べに来て、この感動を分かち合いたいなあと思いながら上野の雑踏を歩いた。
構成=アート・サプライ 取材・文・撮影=小林博美