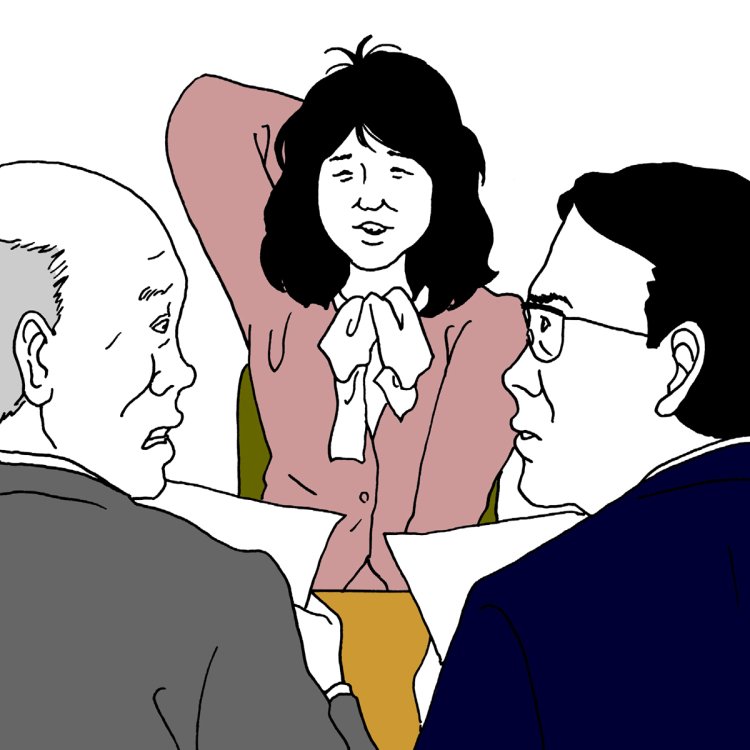登場人物
桂あけみ……タコ社長こと桂梅太郎の長女。高校、専門学校を経て、この春(1980年)、晴れて社会人1年生。それ自体が意外だが、もっと意外な展開が待っているかも……。
桂梅太郎(タコ社長)……あけみの父親で朝日印刷所・社長。この頃、五十路に差し掛かった実年世代。会社は社長本人が逃げ出したくなるほどの不振のピーク。まあ、社長が社長だし……。
【本編】潜入! あけみの職場
出前持ち・梅太郎参上!
「ま、まいどぉ、珍龍軒でぇーす」
あけみの就職から2カ月ほど過ぎた6月のある昼時、白衣、白の前掛けに、白帽を目深にかぶった1人の出前持ちが、あけみの勤める玩具メーカー・タテカツ工業に入ってきた。やや緊張気味の特徴ある甲高い声……。間違いない。誰あろうあけみの父・梅太郎だ。
葛飾区内の零細企業や個人商店には顔が広い梅太郎。偶然、タテカツ工業に出入りする中華屋の主人とは、中学時代、同じ女生徒に心を寄せた仲。そこで当時の秘密を楯に取り、半ば強引に出前持ちにしてもらったのだ。もちろん、あけみを見守りたい一心で……。
「あら? おじさん、新しい人?」
応対に出のは、貫禄のある女子社員だった。雰囲気からすると、この職場で長く勤めているらしいとうかがえた。
「あ、はい。以後よろしく」
挨拶もそこそこにキョロキョロと社内を見回し、あけみの姿を探す梅太郎。不審に思ったベテランOLが聞く。
「どしたの? おじさん」
「い、いやあねえ、この春に入った新人の若い娘さんに……」
「あら、何か用なの? 桂さあん、桂さあん」
気を利かしたベテランOLがあけみを呼びつけようとすると、梅太郎はとっさに彼女の肩口に隠れた。
(桂さんなら、工場におつかい中でーす)
どこからか女性の声が返ってきた。幸か不幸かあけみは不在らしい。
まるでビアホール
「いないんだって。ん? おじさん、なんで隠れてんの?」
「あ、ああ、品物どこに置けばいいのかなあって……」
「そのへんに並べといてよ」
「え~、チャーハン大盛り2つに、レバニラ炒めライス……。で、でも新人って初々しいだろ?」
「笑わせないでよ。このあいだもさあ————
「お待ちぃ。お茶入ったよお」
ある日の午前のこと。若い娘の実に景気の良さそうな声が響く。声の主は湯飲み茶碗をのせたお盆を持ったあけみだ。
「ごめーん、これ向こうのおじさんのとこに回してくれるぅ?」
あけみは無遠慮にも近くの社員に指示する。おじさんと称された人物は営業部長なのだが、言われた本人も言ったあけみも一向に気にしていない。どうやらいつものことらしい。
「なんだかあけみちゃんにお茶いれてもらうと元気が出るねえ」
営業部長がしみじみ語る。
「あけみちゃあん、こっちお代わりもらえないかなあ」
「あいよぉ。営業テーブル3人さん、お茶差し替えねえ」
この数カ月、タテカツ工業のお茶タイムは、さながらビアホールのごときにぎわいだ。
そんな様子を苦々しく思う影ひとつ。それは梅太郎の応対に出たベテランOL……。
「ちょっと桂さん、あなた、ここを飲み屋か何かと勘違いされてない?」
「え? なに?」
あけみが聞き返したとき、またお茶のオーダーが届いた。
「こっちももう1杯ちょうだい」
「あ、はい。今すぐ」
ベテランOLが率先して返事をした。
「あ、あけみちゃんに……」
若手社員は地雷を踏んだ。プライドを踏みにじられたベテランOLの眼光は彼を締め上げる。
「ひっ、や、やっぱりいいです。キャンセルね、キャンセル。お、お勘定おねがーい」
怯えた若手は、逃げるように外回りに出て、結局その日は帰らなかった。
「ええ、行っちゃうのお。まいどー。また来てねー」
あっけらかんとしたあけみの見送りだけが、彼にとって救いだった。
涙の複写機
ーーーーったく、ほとんど飲み屋よ、飲み屋。会社をなんだと思ってるのかしらねえ」
ベテランOLのあけみ口撃に、梅太郎のこめかみに浮いた血管がピクンと反応した。
「こ、これ伝票、ここに置いとくねえ」
話を反らすことで、怒りを収めようとする梅太郎だったが、ベテランOLはいよいよエンジン全開だ。
「それにさあ、聞いてくれる? やることも雑でさあーーーー
「あら、あけみちゃん、それお昼ごはん?」
あけみと同期入社の女性社員が、弁当箱を広げながら声をかけた。
「へへへ、そうなの、デザート代わり。ウチの隣が団子屋でさあ、朝、出るとき、そこのおばちゃんが持ってけって」
「ふぅん」
「おいしいんだよ。1本どう?」
あけみが店名の印字された包装紙を開け、刻み海苔ののった団子を渡そうとした時だった。
「桂さん、手空いてたら手伝って!」
ベテランOLの慌てた声が飛び込んできた。
「あいよ~。何すればいい?」
「コピー! B5、5枚を各30部、大至急で!」
「まかしとき!」
威勢良く応じるあけみ。コピー機はちょうど目の前。その上で広げていた団子の包み紙を手早く片付け、渡された原稿をセットしコピーに取りかかった。
ガチャン、ウィーン、ガチャン、ウィーン……。
複写機は心地よいリズムを刻む。
「世の中、便利だね~。こんな機械があるんだからウチの工場、大変なはずだよ」
「ごめんねえ、ひとりでやらせちゃって……」
団子をもらった女子社員がすまなそうに様子をうかがう。
「いいの、いいの。先に食べちゃってよ」
女子ふたりがそんなおしゃべりをしている時、若い営業部員が慌てた様子でやってきた。
「ゴメン! コピー、5部だけ先にもらうね! 先方、時間にうるさいんだ!」
できたてのコピーをカバンに入れると、小走りで会社を後にする営業部員。
「いってらっしゃあい」
彼を見送るあけみたち。ほどなくして、すべてのコピーが完了した。
「はーい、コピー30部上がりぃ。さっき5部持ってったから25部だよお」
「ありがとう。助かったわ」
ベテランOLは感謝を述べつつできあがった紙面を確認した。その時だった。
「いっ?」
彼女は声なき声を上げて、固まった。そして吠えた。
「な、なんだこりゃあ!」
その声にあけみが手元をのぞき込む。見ると、先ほどあけみが行ったコピーのすべての紙面、その右下の一部分、ダークグレーの下地に白抜きの文字で、
柴又帝釈天参道 とらや
と印刷されているではないか……。
「あ……下に敷いてあった……」
あけみがバツが悪そうに、片付けたはずの「とらや」の包装紙を複写機から取り出した。写り込んでいたのだ。
「や、やり直してっ! いや、追ってえ、彼を追いかけてえ!」
ベテランOLの悲鳴が響く。
平和な昼時が一転して修羅場と化す、そんなできごとであった。
寅で我慢の梅太郎
ーーーーったく、いつも何かしでかしてくれるんだからっ」
「ま、まあ悪気はないんだし……」
「あたしにとっちゃ、すべて悪気よっ。ホント親の顔が見てみたいわっ」
そのひと言に梅太郎の怒りは頂点に達した。
もう我慢の限界……、そう悟ったとき、梅太郎の脳裏に寅次郎の四角い顔が浮かんだ。顔といっても仲良く談笑しているときのそれではない。いがみ合って憎々しい寅次郎の顔だ。
(そうだ。オレは奴から何度も何度も虐げられてきたじゃないか)
そう思うと梅太郎は、これまで寅次郎から浴びせられた数々の罵声や侮辱を反芻(はんすう)してみた。
「けっこう毛だらけ、タコくそだらけだ、この野郎」(第4作)
「こんなボロ工場、辞めちまえよ」(第6作)
「君は労働者を管理しとるのかね?」(第11作)
「タコちゃん」(第13作)
「ねじり鉢巻まいてタコ踊り」(第16作)
「この顔が苦労している顔か? この野郎、風船みたいにブクブクしやがって」(第21作)
「中小企業の恥さらしが」(第23作)
「それと、それと……、ハァ、ハァ、ハァ」
寅次郎の罵声を思い返すうちに、その場の梅太郎の怒りはいくらか収まっていった。
「どうしたの、おじさん? 息荒いわよ」
そう問いかけるベテランOL。梅太郎は無理につくった笑顔で、搾り出すように言葉を投げつけた。
「まぁ いぃ どぉ あぁ りぃ~」

「あけみぃ~、お父ちゃんガマンしたからなあ~!」
今にも泣き出しそうな空の下、梅太郎の怒りの叫びを乗せて出前仕様のスーパーカブが亀有新道を北東に走る。
途中、偶然にもお使いから戻るあけみとすれ違った。梅太郎は気づかない。一方のあけみはハッとして振り返る。
「え? お父ちゃん?」
少し首をかしげ思い直した。
「まっ、そんなハズないっか……」
(つづく)
取材・文・撮影=瀬戸信保 イラスト=オギリマサホ
※この物語はフィクションです。映画『男はつらいよ』シリーズおよび同作の登場人物とは関係ありません。また登場する企業は実在しません。実在していたら転職してみたい気もしますが……。