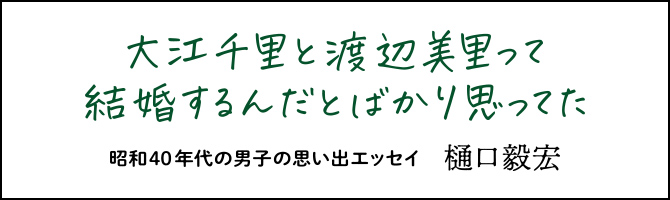怒涛の師走を何とか乗り切る
猫の手も借りたい状況で、毅宏は、時給100 円のわりには役に立ったと言えよう。彼がもっとも嫌だったのは、作業衣のまま配達する姿をクラスメートに偶然目撃されることでも、あたまがおかしなおばさんが口うるさく文句をつけた挙げ句、値切ろうとすることでもなく、閉店後に溜たまった大量の洗い物を片付けることだった。
生肉や揚げ物が載っていたトレイ、ミートチョッパー、深鍋、冷蔵ショーケース内部の器具と引き戸など、ガンコな脂がこびりついている。環境ホルモンに対する意識が根付いた現代ではありえないほどの化学物質が入った業務用洗剤を、これでもかというぐらい使う。耐油性に優れた防水エプロンを着けてもびしょびしょになりながら、すべて洗い終わるまで優に3時間はかかる。あれは本当に骨が折れた。
学校が冬休みに入ると、開店から閉店までフルで働いた。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』を早く観に行きたかったが、悠長なことは言ってられなかった。
毎日お客さんがいっぱい来た。ローストチキンが数百本売れたクリスマスを過ぎると、年の瀬も佳境を迎える。景気が良かったため、すき焼き肉や鍋用の肉がキロ単位で売れていく。
父親に代わって、日によってどの肉をどれぐらい切るかといった裁量を任された石垣さんはぴりぴりしていた。母親もただならぬ雰囲気を漂わせている。その理由を知って驚いた。不渡りを出すかもしれないというのだ。
毅宏は不思議だった。父と母は毎日朝早くから遅くまで働いてきた。学校の給食や食堂などの納めも多い。寂れたあずま通り商店街の中ではいちばんと言っていいほど活気があるし、売り上げもあるだろう。なのになぜ生活がラクではないのか。
お客のおばさんが目尻を下げて言う。
「家族みんなで仲良くやっていいわね」
ふざけるなと心で唾を吐く。しかし毅宏にとって小さな店を営む家族が微笑ましいというか、ちょっと眩しく見えるようになったのは、肉のひぐちが無くなって、家族も減ってから数年が経ってからのことだ。
年内営業最終日、大晦日がやってきた。
毅宏は紅白歌合戦を観た覚えがない。家族揃って紅白歌合戦を観ながら年越しという習慣がなかったため、いまだに興味がない。これは毅宏だけではなく、商人の家の子供に多いのではないか。今年の紅白は誰が出るかなど、今でもかなりどうでもいい。
朝から晩まで働き、何とか師走を乗り切った。石垣さんと支店の社員には感謝の念を込めて、それぞれ30万円のボーナスを支払ったと、後で聞かされた。毅宏は出勤と退勤の時間を店のカレンダーに書き込んできたが、計算したところ1万円を超えた。それを知った母親は激怒した。理不尽だと毅宏は思った。
『生きる』に涙した、 忘れられない夜
年末年始を父親は病院で過ごした。年が明けても毅宏は学校の授業を終えると肉屋に直行し、遅くまで働いた。ひとりだけ店に残って床のタイルをブラシで磨いた後、シャッターを閉めて帰った日もあった。
1986 年1月25日土曜日、忘れられない夜になった。店から帰宅すると、フジテレビは夜9時から『ゴールデン洋画劇場』を放送していた。黒澤明監督の『生きる』だった。胃がんにより余命を知った市役所課長役の志村喬が、何もなかった自分の人生を振り返り、町に小さな公園を作ることで存在証明を残そうとする。
雪の降る夜、ブランコに揺られながら、志村喬は「命短し恋せよ乙女」と口ずさむ。映画史ナンバーワンの名シーンだ。
泣いた。人生の悲哀や、黒澤作品を十二分に理解していたわけではない。いま泣いてみるといいかもしれないと思ったのだ。
自己憐憫なことぐらいわかっていた。
その後、何回か『生きる』を観たが、涙を流したのはそれきりだ。
2月、父親は退院した。自宅のテーブルにつき、思うところがあるだろう。神妙な顔つきに見えた。毅宏は「そりゃそうだ。家族にも散々迷惑をかけたのだからな。さすがに反省しているんだろう?これからは心を入れ替えて生きるか?」と心で問いかけた。
殊勝にもお茶を入れてあげた。父親はひと口飲んで、吐き捨てるように言い放った。
「お茶っ葉を入れすぎなんだよ」
なんだこいつと、毅宏は思った。
文=樋口毅宏 イラスト=サカモトトシカズ
『散歩の達人』2017年11月号より