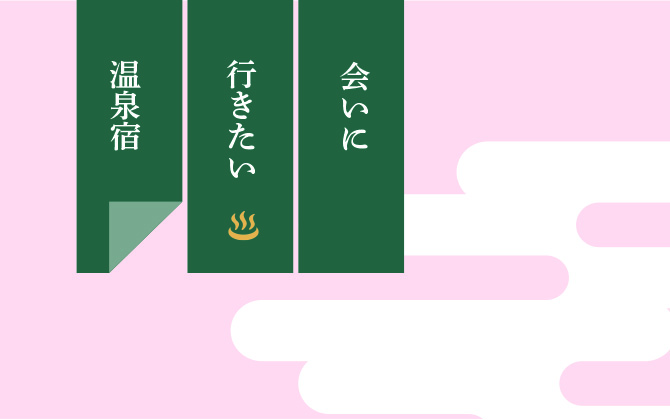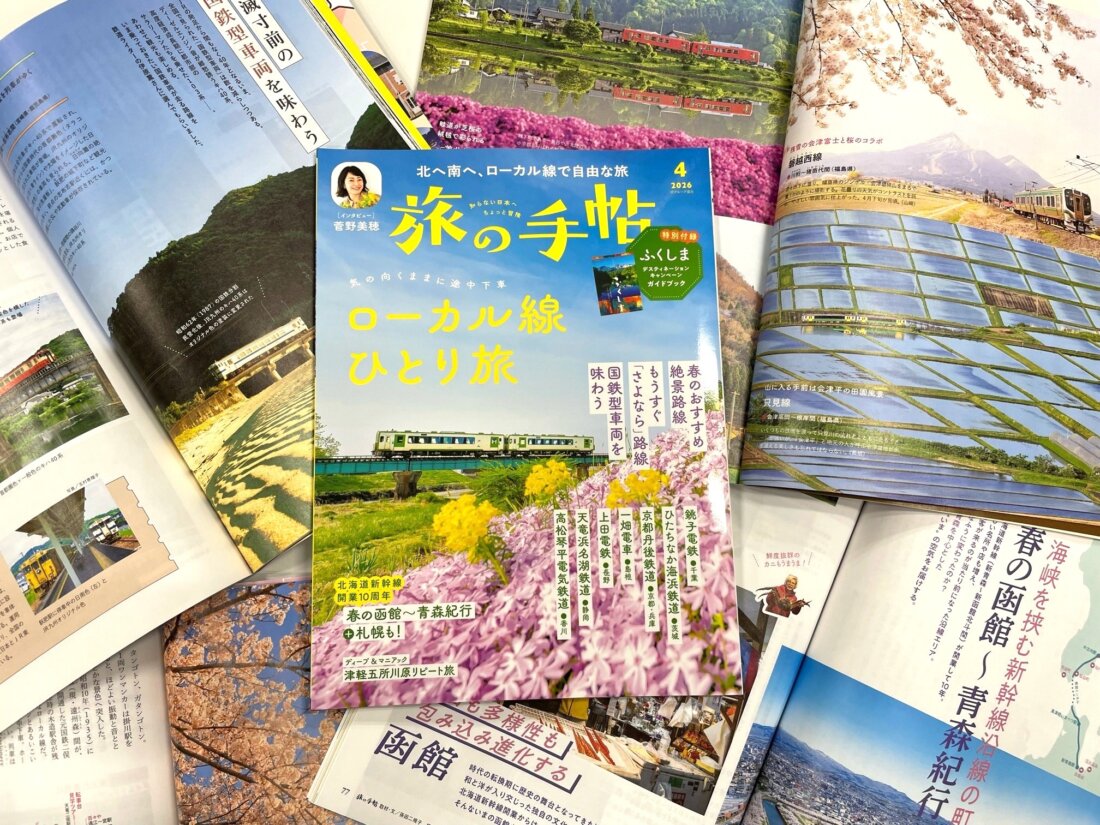今回の“会いに行きたい!”
会長の蔵前壮一さん(左)・社長の蔵前仁宣(ひろのり) さん
丸尾温泉 旅行人山荘(鹿児島県霧島市)
旅館を生家とする蔵前壮一さんと弟・仁一(じんいち)さんは子どもの頃から仲のよい兄弟で、40代の頃、1995年に東京で二人を含めた社員四人の出版社を立ち上げた。
1980年代初頭に世界各地を旅して、『ゴーゴー・インド』や『ゴーゴー・アジア』といった書籍を上梓(じょうし)していた仁一さんから「旅を通じて出会った人たちを世に出すため、出版社をやりたい。兄貴、手伝ってくれ」と言われたのがきっかけだった。
兄弟が紡いだ『旅行人』での素晴らしい時間
その出版社の名前は『旅行人』。社長兼編集長は仁一さん、43歳だった壮一さんは営業を担当することになった。「『旅行人』は私にとって、人生の素晴らしい時間でした」。71歳を迎えた壮一さんがしみじみと回想する。
雑誌『旅行人』の前身は、白黒でコピー用紙を綴じただけの『遊星通信』という名のミニコミ誌。12ページ、たった50部からのスタートだった。しかし1993年に『旅行人』に名を変えると、300部だった発行部数は800部になり、1000部になって右肩上がりで増えていく。
「ちゃちな本ですが、これがすごく売れた。旅先の宿で見るノートのノリで、食べ物やトイレ事情、滞在記など、『読者の体験談』を載せることを貫きました」と壮一さん。
発行部数が3000部になったのを機に、パソコン(Power Mac)を買った。それによって、これまで購読者の住所を筆で手書きしていた手間が軽減するなど、格段に仕事のスピードも上がっていった。
世は“猿岩石”ブーム。アジアへのバックパッカー旅行が激増していたときで、雑誌は発行部数が1万部を超えた。雑誌に掲載していた仁一さんのエッセイをまとめた旅行人初の単行本『沈没日記』の初版も1万2000部で、すぐに重版がかかった。
新潮社から仁一さんの『旅で眠りたい』が出版されたときは、「レジの前に山積みになっているのを見て、うれしくてテーブルの周りを4〜5回、回っちゃいました」と壮一さん。

誰も知らないミニコミ誌が書店フェアを開催するまで
年間購読料4000円で売っていた雑誌を、書店に売り込みに行ったときのこと。「え? これ本なの? パンフレットだと思って持っていかれちゃうよ」と笑われた。「レジの横に置いたら、持っていかれませんから」と頼み込んだ。
小さな出版社であっても、書店に頭を下げることなどほとんどしなかった時代に、物腰がやわらかく、怯まない性格の壮一さんの営業スタイルは受け入れられた。旅館の営業と比べると、書店の営業はすぐに反応が返ってきて、おもしろかった。
「『旅行人』なんて初めは誰も知らなかったけれど、書店の人からすごく大切にしていただきました」
書店から「販促用のイラストや小道具がほしい」と言われると持っていっては喜ばれ、やがて「蔵前仁一が選ぶ旅の本100」のコーナーや「旅行人フェア」を開催してもらえるように。
出版社の仕事は楽しく実家の旅館に戻るつもりはなかったものの、母が病に倒れ、壮一さんは出版と旅館業の二足の草鞋(わらじ)を履いた。鹿児島と東京の往復はさすがに疲れてしまい、その後、父母が亡くなったのを機に1999年には旅館業に専念することになる。
『旅行人』をゼロから立ち上げたときと同じように、宿を磨いて売り込み、やがて『旅行人山荘』は人気旅館の仲間入りを果たしていくのである。

インドに比べたらマシ。だから、頑張れる
5万坪の敷地に点在する貸切風呂がこの旅館の売り。落ち葉を踏み締めて小道を歩き、大自然の中で露天風呂に浸かると「ああ、来てよかった」と思わずにいられない。
“絶景”や“自然とのふれあい”、“リーズナブルな価格設定なのにおいしい料理”など、旅行する人のニーズにうまく寄り添い、父の代に造られた「赤松の湯」に続けて、いくつもの露天風呂を造った。
「切り石を何十回、何百回と軽トラックで運んで、風呂へ向かう遊歩道も造りました」。お金がないときはみずから汗を流して造るのも、出版社時代のスタンスと同じだ。
壮一さんの宿での二十数年間は、大好きな旅行に出かけられないほど激務だったが、「インドに比べたらマシ」と思って乗り越えられた。
バックパッカーの教祖といわれた仁一さんに負けず劣らず、壮一さんもインド好き。新婚旅行はインドで、会長に退いてからも2回、現役で旅行作家を続ける仁一さんと一緒にインドを旅している。
5年前に宿を継いだ長男・仁宣さんも、もちろん旅行好き。新婚旅行先にベトナムやカンボジアを選んだ。『旅行人』のDNAは形を変えて宿にも引き継がれている。
「言葉が通じなくても、伝えたい気持ちがあれば伝わります。聞きたい気持ちがあれば聞こえるんです。それがインドのおもしろいところ。旅館業も同じだと思います」と壮一さん。
ほんわかとした空気を纏いつつ、それでいて芯の強さを感じさせる蔵前親子。その親子がつくり上げてきた旅館だから、温かみがある。
旅館があるのは、天孫降臨の神話が残る霧島神宮のお膝元。忘れていた好奇心や冒険心に出合いたくなったら、訪ねてみてほしい。
『旅行人山荘』の詳細
取材・文・撮影=野添ちかこ
『旅の手帖』2023年12月号より