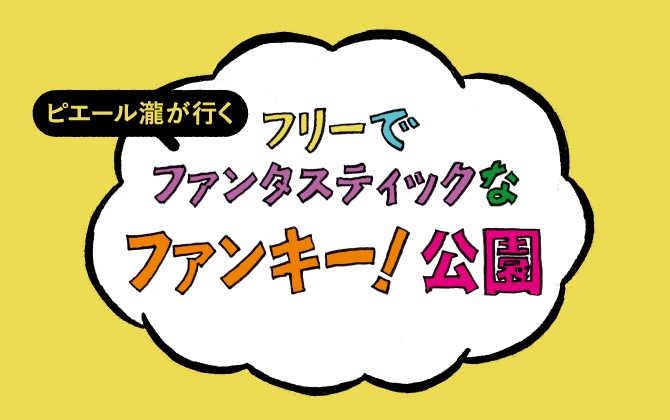気合のフジロック初参加
大学一年の夏、長年憧れていたフジロックに初めて行った。サークルの先輩の車に乗せてもらうこともできそうだったが、先輩たちは夕方から出発し、前夜祭の終わり頃に到着すると言う。初参加で気合の入っていた私は、前夜祭から余すところなくフジロックを体験したかった。だからひとり昼頃家を出て、鈍行列車で苗場に向かうことにしたのである。
東京より北に行くのは生まれて初めてだった。埼玉を北上していくと、だんだん家が減ってきて田舎の風景が広がる。四国から上京して間もなかった私は田舎に飽き飽きしていたが、それでも北関東の田舎は西日本の田舎とはどこか違う雰囲気で、気分が高揚した。
車窓を眺めて考え事をしているうちに、高崎駅に到着した。そこからは新潟方面、水上行きに乗り換えることになる。タイミングよくドアの開いた電車がホームに停まっていたので急いで飛び乗る。間もなく電車は出発した。フジロックの客で混んでいるかとも思ったが意外と空いている。ボックスシートに腰掛けて一息つき、暇つぶしに携帯でニュースを見ていた。
20分ほど乗った頃だろうか、ふと違和感がよぎった。車内アナウンスが、目指している場所と関係ない駅名ばかり告げている気がした。まさか、と思いながら乗降ドアの上にある路線図を確認して、ハァ〜とため息をつく。不安は的中した。やっぱり私は高崎で間違え、全く別方面の電車に乗ったのだ。なんてアホなのか。初めて来た場所なのに、どうして確認もせず適当な電車に乗ってしまうのか。
昔からそういうところがある。携帯で乗換案内を調べたところ、高崎へ戻る電車はあと1時間以上来ないようだ。高崎からここまでの往復時間を考えれば、計画より2〜3時間遅れて苗場に着くことになる。前夜祭の開始時刻に間に合わない。完璧なプランに早くもケチが付いた。自分の間抜けさが今後取り返しのつかない失敗を招く不吉な予感を抱えながら、なす術もなく次の停車駅で降り、ホームのベンチにぐったりと腰掛けて戻りの電車を待った。うるさいぐらいセミが鳴いていた。
そこは改札の駅員すらいない、完全なる無人駅だった。無人駅どころか、駅の周りに民家すらない。山と草地の中に灰色のホームがあるだけ。畑でもないただの原っぱに青い草木がうっそうと生い茂っている。一体この駅で誰が降りるだろう。午後3時のホームに7月末の熱射が降り注いでいた。ベンチの小さな屋根以外に太陽を遮るものはなかった。せめてもう少し栄えた駅なら時間も潰せたのに。とりあえず一本タバコを吸って、それですることはなくなった。しばらくボーッとした後、携帯を取り出し興味のないニュースを見た。
あまりに長い1時間半を過ごし、少し日も傾いて来た頃、ようやくやってきた電車に乗り、冷房のありがたみを感じる。そして今度こそ高崎から新潟方面の電車に乗り、苗場へ向かったのだった。
着いた頃には完全に日が暮れていた。やはり前夜祭の開始には間に合わなかった。遅れて来た分を取り戻そうと精いっぱいはしゃいだ私は、その後全財産の入った財布と3日間通しチケットに当たるリストバンドを紛失し散々な目に遭うのだが、それはまた別の話だ。
もう一度あの駅へ
あのとき無人の駅で過ごした1時間半。やたら暑くて退屈で、ただただ自分のミスが鬱陶しかった。しかし時を経てあの時間を思い出す時、なぜか夢の中で見たワンシーンのようにノスタルジックな気分が記憶を取り巻いている。やむを得ず降りただけの、名も知らぬ駅。誰一人自分を見ていない。ここにいることを誰も知らない。何もすることがないし、何をしても意味がない。どう足搔こうと電車を待つ以上の選択肢はなく、駅から離れても早く目的地に着くわけではない。どこにも行けなかったし、行く必要もなかった。
あれからの人生、何もせずボーッとしている時間など腐るほど過ごしてきた。しかしそんな時でも、「本当は何か今後の役に立つことを始めるべきじゃないか」という焦りが心から完全に消えることはなかった。完全に世の中から隔絶され、宙に浮いた時間は、簡単には訪れなかった。
見渡す限り人がいない場所へ行きたくなり、鈍行で東北を回る一人旅をしたことがある。はっきり意識はしていなかったが、その時もあの無人駅の幻影を追い求めていた気がする。しかし思い描いた場所はついに見つけられなかった。
もう一度あの駅へ行ってみたいと思うことがある。しかしきっと、あの時あの駅を目指したわけではなくたまたま辿り着いたからこそ、特別に感じているのだろうとも思う。調べればおそらく駅の名前はわかるだろうし、実際に行くこともできるだろう。でも多分、もうそこに行かない方がいいのだろう。
文=吉田靖直 撮影=鈴木愛子
『散歩の達人』2021年3月号より