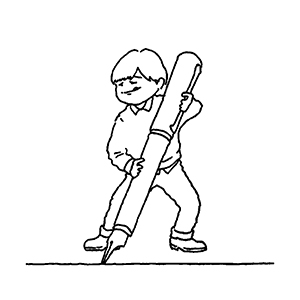再築を経て、ますます愛のこもった街の象徴
国立大学町の開発と併せて大正15年(1926)に誕生した赤い三角屋根の駅は、まさに街のシンボル。中央線高架化に伴って解体が検討されると市民から保存を求める声が上がり、その思いに応えて国立市も奔走。市指定有形文化財として、駅前の土地を市が買い取ることで再築できることとなった。
「歴史的に見ても、国立市民は街づくりにかかわろうという気持ちが強い。思いがひとつになって実現できたことだと思います」と国立市生活環境部の藤堂天平さんは話す。
しかし、ひと口に再築といっても簡単なことではない。駅舎はその歴史のなかで増改築を繰り返してきたが、今回の再築で目指すのは解体前ではなく竣工当時の姿。部材を綿密に調査し、資料を集めて当初の姿をリサーチするところから始まった。
「パズルを埋めていくような作業でした」とは、再築を手掛けた竹中工務店の設計担当・薬師寺浩さん。設計図にはない色味を探るべく古い壁のペンキを削ったり、当時の改札の形の参考にするため『京都鉄道博物館』まで足を運んだり。解体時にはなくなっていた屋根のドーマー窓が復活しているのも、古い写真を拡大し瓦の枚数を数えて寸法を計算するなど根気強い調査の結果成し得たものだ。
また、木材には劣化して使えない部分もあったが、宮大工が根継ぎ修復を施して可能な限り再利用。通常は3割でも御の字なところ、なんと7割近くの再利用率を誇る。「ひさしの柱には八幡製鉄所の古いレールが使われているものもありました。その刻印も読めるようにしてあるんですよ」と薬師寺さん。壁との設置面がちょっぴり傾いているひさし柱があるのだが、実はこれも元通りのズレ! 細部までとことん忠実に再現されていることに驚かされる。
駅舎としての役目を終え、公共施設として再びその歴史を刻みはじめている赤い三角屋根。再築を経て、ますます愛のこもった街の象徴として、これからの100年も国立の街を見守ってくれるはずだ。
取材・文・撮影=中村こより
『散歩の達人』2025年9月号より