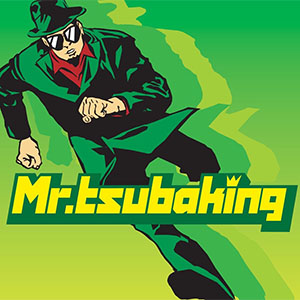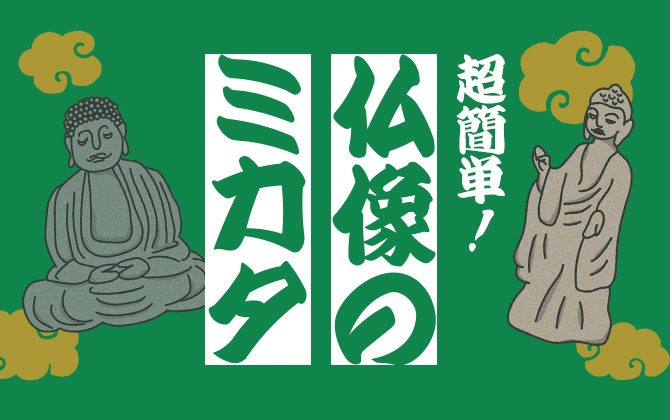そもそも鳥居ってなんのためにあるの?
まずは鳥居の起源について。
鳥のモチーフがデザインされているわけでもないのに「鳥居」という名前であることも不思議ですよね。
諸説ありますが、日本神話の「天岩戸伝説(あまのいわとでんせつ)」には次のような内容が書かれています。
ある神様の暴挙に怒ったアマテラスオオミカミという太陽神が、岩の洞窟に隠れたため世界は暗闇に包まれました。そこで各地の神々は、アマテラスを洞窟から外に誘い出すために鳥を鳴かせました。
その時に置かれた「止まり木」が鳥居の起源だとされています。
それ以来、神前には「鳥の止まり木」を置くようになり、ここから鳥居へと発展したと考えられています。
つまり鳥居は、神様のいる神聖な場所と人間の暮らす俗な世界を分ける境界線というわけです。
鳥居をくぐる際に一礼するのは、神域に出入りするためということですね。
反っているか反っていないかで見分けよう
2本の柱を立て、その上部に横に柱を通すのが、おなじみの鳥居の形です。しかし、材質や色・形まで、よく見てみるとさまざまな鳥居があることに気付かされます。
まず、形については、代表的なものは2タイプです。
もっとも古い形で、伊勢神宮などでも見られるのが「神明(しんめい)鳥居」。
2本の柱の一番上に「島木(しまき)」と呼ばれる直線的な横柱が乗っていて、その下、柱と柱の間に「貫(ぬき)」という横柱が渡してあります。
貫が、両脇に突き抜けていないのも特徴です。
もうひとつが「明神(みょうじん)鳥居」。
島木の両端が上に向かって反っているタイプです。仏教の豪華な建築が海外から入ってきたことに影響を受けて、神社の建築も豪華になっていったと考えられています。そのため、島木の上に「笠木(かさぎ)」と呼ばれる屋根のようなものが冠せられています。
なお、明神鳥居のように見えて、上の横柱のすぐ下に受け皿のような部品がついているものは「稲荷(いなり)鳥居」と言われるものです。
地域や神社の格による個別種も!
鳥居は大別すると神明・明神の2タイプですが、細かく分けるとその種類は60以上にもなります。
個別種で代表的なものとしては大分県の「宇佐神宮」。
全国に4万4千社ある八幡宮の総本宮であるこちらは「宇佐鳥居」という、ここだけのスタイルです。
パッと見は稲荷鳥居のようですが、中央の額がありません。さらに笠木と島木の反りが、明神鳥居・稲荷鳥居よりも極端であるところも特徴的です。
ここでしか見られない鳥居なので、参拝の際はお見逃しなく!
他に、東京の「靖国神社」の鳥居も、唯一無二。
タイプとしては神明鳥居ですが、神明鳥居では貫を円柱形にするのに対し、靖国鳥居は角ばったものが使われています。
小さな違いではありますが、ディテールまで見えるようになれば、神社の参拝はさらに楽しく意味深いものになりますね!
朱色に塗られているのはナゼ?
続いては「色」について。規定があるわけではないので、石や木などの材料そのままの色になっているものも多くありますが、朱色のイメージも強いですね。
朱色は古くから魔除けに用いられてきた色。根底には、太陽や血液などのようにエネルギーや脈動につながる色だという感覚があるようです。
また、現在では使用されなくなりましたが、古くは朱色を作る際には水銀を用いました。この水銀には防腐や防虫の効果があり、屋外で雨風にさらされる鳥居を長持ちさせる狙いもあったのです。
足の本数や材料が珍しい鳥居も
ここまで、一般的な鳥居の形や色についてご紹介しましたが、全国には類例に属さない珍しいタイプの鳥居も数多く存在します。
例えば、京都の「木嶋坐天照御魂(このしまにますあまてるみたま)神社」や、この連載でも何度か登場した東京の「三囲神社」にあるのは3本足の鳥居。
一般的な鳥居は、「そこから先が神域」という意味を持ちますが、 3本足の鳥居はその中心が宇宙だと考えられ、360度どこからでも参拝できるようにされているそうです。
他にも、陶器の街、佐賀県有田市の「陶山(すやま)神社」には、有田焼でできた鳥居が!
木や石でできた鳥居に見慣れた私たちには、有田焼のつやめく青と白が新鮮に目に飛び込んできます!
神社の中心はもちろん、本殿とご祭神ですが、その入り口を守る鳥居に注目してお参りに出かけると、きっと新しい楽しみが見つかるはずです!
写真・文=Mr.tsubaking