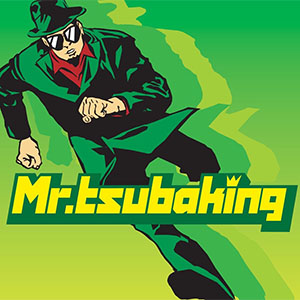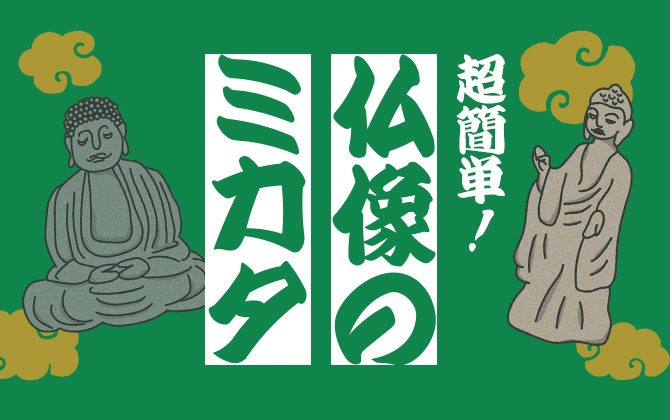「ほおづき市」のはじまりは都心の神社から
「ほおづき市」がはじまったのは、今から約250年前の江戸時代中頃。「愛宕(あたご)神社」(港区)が発祥とされています。
かつては漢方薬としても使われていたホオズキが、「愛宕神社」の境内には多く自生していました。これを飲むことで、大人は不治の病が治り、子供は腹の虫(子供の病気はお腹の虫のせいだとされていた)を退治できると考えられており、ホオズキが実る季節に境内に市が立ったのがはじまりだそう。
ちなみに「愛宕神社」のほおづき市は毎年6月下旬に開かれ、「夏越の祓(なごしのはらえ)」という神事の時期にも一致します。境内に大きな茅の輪が登場し、この輪くぐることで穢(けが)れを祓い長生きできると考えられています。「穢れを祓う」と言うとピンと来ないかもしれませんが、筆者個人的には自分の「心身のキャッシュデータクリア」をしているイメージ。新たな気持ちで下半期に向かえます!
ホオズキはご先祖さまの目印だった
こうして「愛宕神社」ではじまったほおづき市が世の中に一気に広まった背景には、「浅草寺」の存在がありました。
浅草寺のご本尊である、観音菩薩の御利益が大きくなる日を「功徳日(くどくにち)」と言い、はじめは7月10日がその日とされました。
現代でも、人気のゲーム機やスマートフォンの発売日には、前日から行列ができる光景を見かけますね。同じように江戸時代の人々も、功徳日には「早く観音様のすごい御利益を受けたい!」という思いで、境内は前日からにぎわっていたそうです。
そのため、現在では7月10日と、その前日である7月9日が功徳日となりました。この2日間は参拝者が多くやってきて、露店なども出ました。そこに、ほおづき市も立つようになったのです。
数ある露店の中でも、ホオズキが特に重宝されたのは「お盆」が近いため。ホオズキは、煌々(こうこう)と輝く提灯のような見た目から、お盆に帰ってくるご先祖様の目印になると考えられています。全国的には、8月13~16日が一般的なお盆ですが、東京では7月13~16日。そのため、お盆の直前にホオズキを購入して、各家庭の仏壇などにお供えする風習があるのです。
観音さまのパワーがとてつもなくアップする日!
さて、それでは7月9・10日の功徳日に、観音菩薩のパワーはどのくらいアップすると思いますか?
答えは、「4万6000倍」です!
正確には、「功徳日に観音菩薩にお参りすれば4万6000日分の御利益が得られる」と言われている「四万六千日(しまんろくせんにち)」の縁日。漫画『ドラゴンボール』のフリーザのセリフ「私の戦闘力は53万です」にも通じる凄みを感じますね。
4万6000日は年に換算すると約126年で、つまりは「一生」の御利益という意味。また、お米1升が4万6000粒分であることから、1升と一生をかけているという説もあります。いずれにしても、参拝に行きたくなる特別な日なんです!
夜中のお寺に参拝できる特別な日!
神道や仏教の縁日は「日」に意味があるので、平日に当たることもしばしば。「浅草寺」の2025年の「四万六千日」も平日です。
「じゃあ、仕事だし行けないや」とガッカリしている方に朗報です! 東京と地方でお盆の時期が違うのと同様、「四万六千日」も東京以外では別の日程で行われます。
その中で、筆者のオススメなのが鎌倉。8月10日(2025年は日曜日!)がその日にあたります。鎌倉最古のお寺である「杉本寺」では、8月10日がはじまる深夜0時にお寺が開き、深夜のお参りが可能なんです。
夜闇に包まれたお寺は、昼間以上に神聖で厳か。この日は、普段は秘仏となっているご本尊もご開帳され、運慶や快慶や行基といった名だたる仏師・高僧がつくった仏像を拝観できる特別な日です。
また、紫陽花で有名な「長谷寺」はこの日だけは、朝4時に開門(通常は朝8時開門)。清廉な朝の空気の中で、5mを超える大きな観音菩薩を目の前にすると、仏教徒でなくても思わず手が合わさります。そして、「長谷寺」は高台にあるため、天気が良ければ日の出を拝み、眼下に広がる相模湾が明るくなっていく様子も堪能できるのです!
夏の風物詩「ほおづき市」の背景に、観音菩薩のでっかいパワー。これを知っていれば、ほおづき市へのお出かけが一層楽しみ深くなること間違いなしですね!
写真・文=Mr.tsubaking