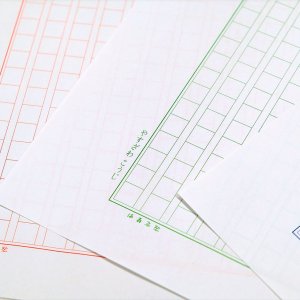温又柔(おん・ゆうじゅう)
1980年、台湾・台北生まれ。両親とも台湾人。幼少時に来日し、東京で成長する。著作に『真ん中の子どもたち』(集英社)、『空港時光』(河出書房新社)、『魯肉飯のさえずり』(中央公論新社)、『永遠年軽』(講談社)、木村友祐との往復書簡『私とあなたのあいだ いま、この国で生きるということ』(明石書店)、編著『李良枝セレクション』(白水社)など。近刊に『祝宴』(新潮社)。
小説「ぼくと母の国々」(交通新聞社刊『鉄道小説』収録)
台湾に帰ろうと思ってるの、と母は言った——。3歳で両親とともに来日した勇輝は、中学生の時に帰化して苗字が「黄」から「横山」になった。緑色一色の山手線、亡くなった父、日本語を話す祖父母。蘇る記憶の中で見つめる、日本と台湾の物語。
線路沿いを歩くのが意外と好きだと気づいた
日本に来たばかりの頃、この坂道をよく父と母と歩いた。坂道を登りきって、少し行くと鉄製の青い跨線橋があった。ぼくはそこで、線路の上を行き来する電車にいつまでも飽きずに目を凝らした。当時はまだ目新しかったステンレス車両の山手線が通ると父も母も、めずらしいのが来たね、と声を弾ませた。でも、ぼくが一番好きだったのは、緑色一色の旧車両だ。
(温又柔「ぼくと母の国々」より)
——今日は小説「ぼくと母の国々」の「ぼく」、勇輝が歩いていた山手線沿線を散歩しながらお話を伺います。温さんご自身も勇輝と同じく恵比寿で子ども時代を過ごしたとのことですが、この辺りは今も歩きますか?
温 ちょっと気分いい時に歩きます。寄り道する感覚かな。ここを通らなくても帰れるし、ここを通ったらむしろ遠回りになるんだけど、わざとね。そうやって通らなくてもいいはずの道をわざわざ歩いているとき、なんだかときめくんです。「ぼくと母の国々」に出て来るのは恵比寿ガーデンプレイスの横のアメリカ橋(恵比寿南橋)ですが、目黒と恵比寿の間のこの跨線橋もいいですよね。意識してなかったけど、あの小説を書きながら、こういう線路沿いを歩くのが私は意外と好きなんだなあと気づきました。
——このあたりの線路沿い、面白いですね。見下ろしていた山手線がいつの間にかすぐ横を走っていたり、今度は頭上を走っていたり。線路沿いの、どんなところが好きですか。
温 線路って、考えてみたら電車がある駅を出発して次の駅に停車するまでの「間」そのものなんですよね。だから線路沿いを歩いていると、常にどこかとどこかの間にいるような感じがする。この感覚が私は好きなのかもしれません。目黒から恵比寿に向かうこのあたりは坂が多くて、高低差も楽しめます。ほら、あそこに「三田丘の上公園」。ちょっと通っていきましょう! 実は以前、難航した原稿が一段落した日も、散歩していたらこの公園に辿り着いて、こっそりここのブランコに乗りました(笑)。誰もいない瞬間を見計らってね。気持ちよかったなあ。
——温さんの散歩は、何かが一段落してスッキリした時に、ということが多いのでしょうか?
温 言われてみるとそうかも! でも、原稿に手こずって、えいやっと散歩に出たら、書けなかった部分があっさり書けちゃった、みたいなこともよくありますね。
恵比寿の記憶、電車の記憶
(略)まだ、恵比寿ガーデンプレイスのある場所にサッポロのビール工場があって、山手線の車窓からは、積み上げられた瓶ビールのケースやビヤステーションの看板が見えた頃のことである。
覚えている。車両を再利用した「電車のレストラン」に行くよ、と父に言われてぼくはその日を指折り楽しみにしていた。
(温又柔「ぼくと母の国々」より)
——「ぼくと母の国々」では、恵比寿という街と山手線沿いの、1980年代からの風景の移り変わりの描写も印象的でした。
温 小説を書きながら、私の記憶の中には幼少期の頃に家族と住み始めた恵比寿の風景が結構な位置を占めてるなと。恵比寿ガーデンプレイスができてからは、台湾から親戚が来るとみんなでこのビルの上のレストランに行ってごはんを食べることもありました。ちょっと上ってみましょうか?
——すごい景色ですね。
温 ここに来ると、小さなことで悩むのやめようみたいな気持ちになれる(笑)。39 階の ロビーの窓からは、電車が行ったり来たりするのを真上からじっくり鑑賞できるのも楽しいし。高いところって気分が晴れ晴れします。もうなくなっちゃいましたが、浜松町の世界貿易センタービルの展望室もすごく好きでした。
——あらためて、今回「鉄道をテーマにした小説を」という執筆依頼を受けてどう思われましたか。
温 鉄道開業150年の節目に自分が小説を書かせてもらえることになってすぐに浮かんだのが、来日中の祖母が電車に乗り損ねて祖父とはぐれてしまったという実際にあったエピソードでした。私の祖父母は日本統治下の台湾で生まれた世代なので、日本語が話せます。なんなら私の両親よりも流暢なぐらいで。そんな祖母が、自分にとって外国であるような、外国ではないような日本で祖父を見失った時、どんな感じだったんだろうって。
(略)恵比寿からなら日比谷線を使えば乗り換えることなく銀座に行けると母は伝えたのだが、祖父はどうしても銀座線に乗ってみたいと譲らなかった。祖父は、銀座線には特別な思い入れを抱いていた。学校の先生が上野駅のプラットホームの写真を載せた新聞を見せながら日本初の地下鉄が開業した日のことを教えてくれたのをいつまでも覚えていたのだ。そのせいで、こんなことになってしまった。祖母は急に腹立たしくなってくる。そして、祖父のことは放っておいて、一人だけで先に恵比寿へ帰ろうと心に決めたのだ。銀座線で終点まで揺られた後、祖母は再び、通りすがりの親切な人に助けてもらって無事に山手線の乗り場に辿り着く。そのプラットホームで、
えびす
というひらがなを祖母は見つける。エビス、と思わず口に出してしまったと祖母は言う。それは、しぶや、という文字の左隣にやや小さめの文字で書いてあった。
(温又柔「ぼくと母の国々」より)
——小説では、台湾から日本に遊びに来ていた勇輝の祖母が銀座線で夫(祖父)とはぐれてしまい、親切な女性に助けてもらった……という記憶として描かれています。これに近い出来事が実際にあったんですね。
温 そうなんです。実際は、祖父の方が一人で電車に乗っちゃった。ホームに置き去りにされて、おろおろしていたら親切な女性に声をかけられて、そのおかげで恵比寿に戻って来られて、ホッとした途端、自分を置いてさっさと電車に乗り込んだ祖父への怒りが湧いたらしくて(笑)。実はこの時、祖母は自分に親切にしてくれた女性の連絡先を聞き出しているんです。それで母に、お礼をしときなさいね、って頼んで台湾に帰った。でも母にとって日本語で手紙を書くのはハードルが高く、結局そのままになってしまった。10年以上も経って大学生になった私がこのことを思い出した時にはもうその方の住所が記されたメモは見つからず……だから私のこの小説を、祖母を助けてくれたその方がたまたま読んでくれたらいいなと空想してしまいます。
——この記事にも書いておきます!
温 うれしいです!(笑)。実はこの小説を書くまでは、祖母が迷子になった時のことを思い出すたび、祖母の「救世主」だったその人に、うちの家族がちゃんと感謝を伝えていないことがひどく申し訳なかったのですが、考えてみたら電車や駅のホームで自分の目の前で誰かが困っていたら、ちょっと声をかけて、行き方を教えてあげるぐらいは全然負担じゃないのかもな、と。だから、その方自身は自分が台湾人の老女を助けたことすら記憶にない可能性だってあるよね、とも思ったりして。「ぼくと母の国々」を書くことではじめて、自分や家族にとって忘れ難いそのエピソードを、こんなふうに別の角度から見直せて、ああこれが小説を書く醍醐味だなあって思いました。その上でやっぱり今その方にお会いできるのなら、祖母や母が言えなかった代わりに、あの時は私のおばあちゃんに親切にしてくれてありがとう、と伝えたいですね。
ずっと、 “自分に連なる歴史”を意識している
——編集作業中、1980~90年代の恵比寿や渋谷の資料をいろいろと参考にしたのですが、ビール工場やビヤレストランの存在を確認できても、それが当時どんな存在だったのかという実感のようなものは小説だからこそ留めておける表現だなと思いました。
温 私も、自分の個人的な記憶の中に刻まれた風景が、街の歴史のまぎれもない一部であることをとても意識しました。交通新聞社さんのご協力もあって、記憶を素材とした小説の細部の裏をとるべく資料や年表と照らし合わせることで、自分や自分の分身みたいな主人公たちの存在が、今ここでだけで完結しているんじゃなくて、この今に至るまでのいろいろな可能性も含めた「歴史的存在」であることを改めて考えさせられました。私自身、これまでもずっと、今ここにいる自分とそんな自分に連なる歴史を意識しながら創作と向き合ってきたつもりではあるのですが……。
——個人的な記憶や“自分に連なる歴史”について書くようになった理由やきっかけを教えていただけますか。
温 書くことを通して、自分の記憶や体験をあらゆる角度から眺めることが面白いからなのだと思います。でも、考えてみれば私と同じことを記憶しているはずの妹や、私と似た体験をしている幼なじみもいるけど、私ほど自分の記憶や体験にこだわってはいない。どうして私ばかり、こんなに引っかかってしまうんだろうと、それを考えるために小説を書いているようなところもあります。
——温さんがご自身のエッセイ『台湾生まれ 日本語育ち』で、文学は「証明のしようのない複数の真実に光を照らすもの」と書かれていましたが、「個人的な記憶の中に刻まれた風景」は、まさにそういうものだなと思います。
温 小説だからこそ留めておける歴史、という話で思い出したのですが、ちょうど最近、平林たい子の「盲中国兵」という、ごく短い小説を読んで身震いしたんです。1946年3月に発表された作品なのですが、「昭和20年3月9日」に語り手の「私」は列車に乗ろうとして警官に止められます。その車両に高松宮がいることに「私」は気づき、新聞でよく見るその姿を拝みながら「ここに宮様がいるぞ。真物だぞ」と感動を覚えるのですが、その直後、悪臭を放ちながら次々と下車してくる盲目の中国兵たちを目にして「恐ろしさと気味悪さで思わずぶるぶるとふるえ」ながら、「まず、毒ガスの試験にでも使われたか、工場で何かの爆発にでもあったかという所だろうね」と別の乗客が囁くのを聞くという、本当にただの目の前の出来事をそのまま描写したような小説なのですが……。天皇の弟である「宮様」と、天皇陛下の国家たる大日本帝国のために犠牲にさせられた中国人たちを同時に乗せた列車があったというこの場面の生々しさに戦慄しながら、この歴史のディティールは小説だからこそより伝わってくるのかな、と思いました。後世の私たちが資料などを通して、歴史に対して、こうした小説的な想像力を働かせるにはどうしたらいいのか近頃よく考えます。
——「盲中国兵」もまさにそうですが、個人の歴史は必ず社会の歴史とつながっているので、『鉄道小説』でもそのような表現ができるといいなと考えていました。
温 ご依頼を受けた際、「大きな物語」としての鉄道150年史ではなく、どちらかといえば、名もなき人々にとってのそれぞれの記憶の中にある鉄道のある風景をゆるやかに束ねることで、日本で鉄道が走り出した150年分の豊かさを形にしたいという編集部側の意志を強く感じました。私にお声をかけてくださったのは、日本の鉄道史が日本国内だけ出来上がっているわけではないということを意識なさっているんだなあ、ということも。ちょっと教科書的に整理すると、台湾を縦貫する鉄道が開通したのは1908年。むろん、その大部分を敷いたのは日本です。私の母は子どもの頃、台湾鉄道に揺られて台北から高雄にある祖母の実家によく行ったと言います。母や祖母が北と南を行き来するために当たり前のように利用していた台湾鉄道の前身が、植民地台湾を経営していた日本の台湾総督府鉄道だったと知った時は、さすがに複雑な感慨を抱きました。でも今回、「鉄道」の小説を書かせてもらう機会をいただいてすぐに思ったのは、こうした史実を糾弾するのではなく、また擁護するのでもなく、単なる私たちの歴史の前提として小説の背景にしたいなということでした。
「ささやき声で、大事なことをコツコツ言う」のが目標
(略)山手線に揺られれば五分ほどで五反田に着く。しかしよほど忙しいときでなければ母の家に寄った日のぼくは、散歩も兼ねて歩くことが多かった。目黒方面に向かう道はいくらでもある。ぼくは線路沿いの緩やかな勾配の坂道を登り始める。この道沿いに、かつてボウリング場があった。その脇を通り過ぎるときボウリング場に併設されたカフェの一角を陣取って、あたしたちは台湾人なのよ、と蔡さんや陳さんの奥さんたちを前に激励する調子で言っていた母の様子を思い出す。
(温又柔「ぼくと母の国々」より)
——温さんは台湾と日本、ふたつの国のあいだで生きる人のことを、異なる人の目線で、繰り返し小説に書かれています。同じテーマを違う視点で描き続けるのは、どのような思いからでしょうか。
温 台湾人の自分が日本語を使って生きているという事実に思いが至るたびに私は、例え同じテーマを繰り返すことになっても、まったく別の形の小説として表現してみたい、という欲望が湧くんですよね。特にここ1、2年は、自分が40代になったのもあって、これまでの人生のありとあらゆる段階の自分を、他の人の目を通したらどう見えるんだろう、と考えるようになって。そうなってくると、また一から小説として組み立て直したくなる。
——最近の作品では、『永遠年軽』で日本人の女性の視点から、『祝宴』では台湾人の父親の視点から描かれていましたね。
温 『永遠年軽』では、もしも自分がいわゆる「普通」の日本人だったら、どういうふうにこの40年を生きてきたんだろうってことを想像したかったし、『祝宴』では、父親にとっての「ふつう」の価値観から娘を見たらどうなんだろうということを想像したかった。「ぼくと母の国々」では、自分が男の子だったら、そして日本語で発音してもヘンテコと思われない名前の持ち主だったら、みたいなことを想像してるうちに、あんな小説になりました。だから勇輝も、実は私の分身みたいな存在なんです。
——「普通/ふつう」を疑うこと。その複雑さを複雑なまま表現するために、見る角度を変えてご自身の考え方をずっと点検し続けているような感触もあります。
温 私が主張したいことは、要するに、いつも同じなんです。「日本は、日本人だけの国じゃない。日本語は、日本人だけのものではない。日本の近代史は、日本列島内だけでは語れない」。私はこれらのことを、スローガンのように声高に訴えるのではなく、あくまでも、面白い小説として表現したい。ただこれは、面白い小説さえ書けるのなら、歴史も社会も関係ない、みたいなこととでは決してないんです。何しろ、いまだに日本では小説に限らず、芸術に政治を持ち込むのは偏っている、と言いたがる人は少なくない。私からすると政治や社会や歴史と無縁でいられると思い込める時点ですごく特権的なのになって。でもだからと言って、逆に、政治的な正しさを鎧に自分は常に正しいと居直って、自己点検を怠る人たちにも欺瞞を感じる。どちらの極に振れるとしても、私が一番怖いのは自分の思考が停止することです。だからこそ小説を書くなら私は、いわゆる「マイノリティー」の立場にある人物のみが圧倒的に正しい、と理解されてしまう可能性の高い小説はなるべく書きたくないんです。
——「正しさ」を客観的に考えることは、本当に難しいと感じています。『永遠年軽』では主人公・由起子の視点から、友人で台湾人の父親をもつ美怜(メイリン)が10代・20代の頃、「自分のことで精いっぱい」になっている様子を描かれていましたね。
温 まさに美怜のように、ある時期までの私も、日本では圧倒的マジョリティである日本人たちに対して、少数派の自分の意見を頭ごなしにぶつけてばかりいたし、自分の話に聞く耳を持とうとしない大勢の人たちに批判的でした。とにかく自分のことしか頭になくて、自己点検する余裕がなかった。私はデビューが29歳なんですが、30代の十年間で書いた小説やエッセイは、10代半ばから20代前半の頃の自己観察であり、それらを書くこと自体が、この社会や歴史の一部である自分自身を把握するためにあったような気がしています。時間がかかりましたね(笑)。でも、時間を費やすだけの価値はありました。何しろ、「ぼくと母の国々」で「楽でないことは、必ずしも不幸ではない」と書いたけど、これは小説を書き始めた頃には書けなかったと思うので。
——時間がかかるけど、「時間を費やすだけの価値はある」ということには励まされます。
温 おかげで最近は、大勢の人たちに自分をわかってもらおうと闇雲にもがくのではなく、数は少なくても確実に自分の志を共有してくれる人たちの存在を信頼しながら、以前よりも粘り強くものを考えられている気がします。途方もないけど、それが唯一の道なんですよね。だから、「ささやき声で、大事なことをコツコツ言う」というのが最近の目標です。
取材・構成・撮影=渡邉 恵(交通新聞社 鉄道文芸プロジェクト事務局)
引用部分出典=平林たい子「盲中国兵」『戦後短篇小説再発見8 歴史の証言 講談社文芸文庫編』(講談社、2002年)