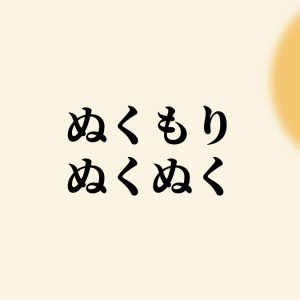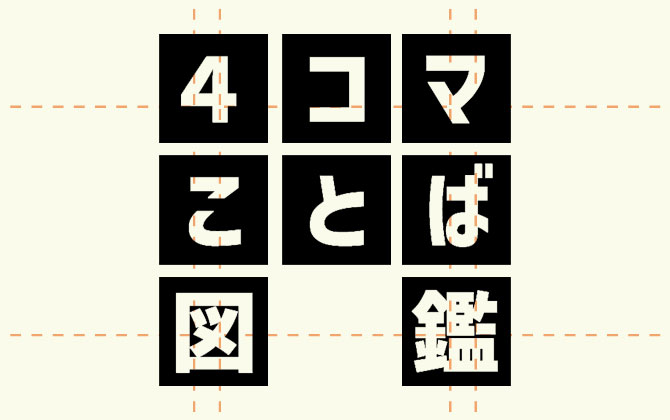「ねこ」「ニャー」に隠された意味とは?
小野先生 : 「ねこ」の語源は確かではないのですが、「寝高麗(ねこま)」という説があります。「高麗」とは朝鮮のこと。猫は大陸から朝鮮を経由して、人の手によって日本に輸入されたのかもしれません。
いずれにしても、「寝」という語源感覚はあったものと考えられます。猫は夜行性である(つまり昼間はよく寝る)ことは理解されていたのでしょう。
筆者 : 「ねこ」ということばには、少なからず「寝(る)」のイメージが含まれていると。
小野先生 : それだけではありませんよ。『源氏物語』に「『ねうねう』と、いとらうたげに鳴けば、かき撫でゝ」という一節があります。平安時代の人は、猫の鳴き声を「ねうねう」という擬音語で表現したわけです。
「ねう」は「寝よう」の意だとする説もあります。作者がそこまで明らかに意図したかわかりませんが、「ね」=「寝」という感覚はあったものと思われます。
「ねうねう」はその後、「ニョーニョー」という発音に変わっていきます。「ニャー」に近いですね。
筆者 : ひょっとして「ニャーニャー」の根本にも「寝(る)」があるのですか?
小野先生 : そうですね。普通、擬音語は、声や音をひとの言葉でまねした言葉ですから、基本的にはそこに意味は関係しません。しかし「ニャー」などは、根源にさかのぼると、昼間寝ている猫の生態が鳴き声の表現とつながっていると言えそうです。
筆者 : 猫の声を聞くと眠くなってきそうです(笑)。
猫は神秘的な存在として描かれてきた
筆者 : 現代では、キャラクターになったり、マンガに登場したりと、猫はさまざまなコンテンツに使われます。それほど、人との関わりが深い動物だと思うのですが、『源氏物語』の時代はどんな存在だったのでしょうか?
小野先生 : 「若菜上の巻」の有名なエピソードに猫が登場します。柏木という麗しい男性は、光源氏の妻となった女三の宮に恋をしています。ある宴の席で、不意に猫が飛び出し、女三の宮の御簾(みす)にからんで引き揚げてしまいます。そのとき柏木は女三の宮の姿をかいま見してしまい、恋心がかきたてられて、ついに密通に及ぶのです。
筆者 : きっと、当時の高貴な女性にとって、顔を見られるのはとても恥ずかしいことだったのでしょう? 「チラリズム」に通じるエロチックなエピーソドだと感じます。そんなシーンを演出する猫は小悪魔的というか……。
小野先生 : 平安中期の随筆『更級日記』には、とてもプライドの高い猫が登場します。作者の菅原孝標女が、亡くなった知人(侍従大納言の娘)の手紙を見返しながら、想い出にひたっていると、どこからか猫がやってきます。
姉とともにその猫を飼うことにすると、いつも自分たちのそばにばかりいて、食べ物も汚れていると顔をそむけて食べようともしません。
忙しくなり世話ができなくなると、猫は姉の夢に出てきて「自分は、侍従大納言の娘が猫の姿を借りて現れたものであり、世話をしないとは何ごとだ」と告げるのです。
筆者 : 寝ているときや、食事をねだるときの猫は本当にかわいい。反面、いたずら好きで、気位が高く、人を困らせることもあります。この二面性がネコの魅力だという意識は、古くから日本人の中にあったのですね。
小野先生 : 怪談に「化け猫」が登場するように、猫は不可思議で精神性の高い存在でした。人懐っこく従順な犬と対比されるとおり、猫は人が完全にコントロールできず、だからこそ放っておけないのですね。
取材・文=小越建典(ソルバ!)