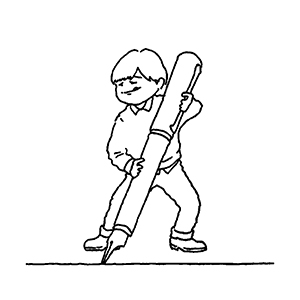故郷・串本町の気配も色濃い洋菓子店
『C’est la Saison!』があるのは、JR横浜線相模原駅と矢部駅のちょうど中間あたり。線路と並行して走る相模淵野辺線沿いに、淡いミカン色でかわいらしいフォルムの店が立っている。
店内に並ぶのは、ショーウィンドーにキラキラと輝くケーキのほか、数えきれないほどの焼き菓子やアイスクリーム。そのバラエティに驚きながらじっくり品定めしていると、和歌山県串本町という地名に目がとまった。柑橘類や梅など串本町の特産品を使ったお菓子に、地域ゆかりのグッズも置いてある。どういうことかと思っていると、オーナーシェフ・清水康生さんの肩書きに「串本ふるさと大使」とあるではないか!
「地元は海のそばで、寝ていても波の音が聞こえましたよ」と清水さん。和歌山県串本町は、この清水さんの故郷なのだ。
紀伊半島の先端に位置する串本町は、本州最南端でもあり、以前は台風接近の際の中継でもよく見かけた町の名前だ。紀伊山地と太平洋に囲まれた串本町は平野部がほとんどなく、リアス式海岸には奇岩など雄大かつ独特な自然の姿が見られる。一年を通して温暖な気候で、特産品はなんといってもキンカンやポンカンをはじめとするフルーツ。そのほか、カツオやマグロなど海の幸にも恵まれた地域だ。
大阪とは違う、東京に感じた“都会”
子供の頃はひたすら外で遊びまわっていたという清水さん。「時代も時代だし、テレビゲームもないから」と笑うが、昆虫採集をしたりハゼをエサにしてウナギを獲ったりした話を聞いていると、なんだかうらやましくなるほど楽しげな放課後だ。
中学生の頃から美術に興味が湧き、高校では美術部に所属。また、その頃からコックにも漠然と憧れを持つようになった。「いとこが和食と洋食のコックをしていたので、その影響もあったのかな。大阪の大学に進学して農学部で勉強しながら、飲食店でアルバイトをして実際どんなものかというのを体験しました」。
そうして、大学卒業後は東京・麻布台にある国際社交クラブ「東京アメリカンクラブ」に就職し、フランス料理の道へ。縁あって上京することになったわけだが、地元の同級生は進学や就職でも大阪や名古屋に出る人が多く、東京に出る人は少ないという。
「大阪にはなじみもあったし、大学進学で地元を出たときはいっぱい遊べるぞという自由な気分で、不安はありませんでした。でも、東京に出た時はちょっと孤独感がありましたね」
東北や中部から上京するのとは一味違うであろう、関西圏からの上京。関西と関東では人の距離感や会話のテンポも違うという話はよく話題になるけれど、清水さんもやはりカルチャーショックを感じたそうだ。
「大阪だとお店の人も一言多かったり、茶々入れてくれたりという雰囲気ですが、東京はみんな冷たいなって。大阪はいわば大きな村でしたが、東京はやっぱり都会だと思いましたね」
「東京アメリカンクラブ」ではデザートやパンを手掛ける機会も多く、お菓子作りに魅力を感じるようになり、葉山のレストランや神戸の洋菓子店へ。その後、葉山でお世話になった料理長に誘われて南青山『レストランKIHACHI』のオープンに携わり、「パティスリーKIHACHI」の出店を機に相模原にも訪れて、後に住まいを構えた。そうして『KIHACHI』に13年勤めた後、独立して自身の店を構えたのが40歳、2000年のことだ。
地域を見据え、産地から旬をつなぐ
自分の店を開くにあたり、悩んだのはその場所。和歌山や名古屋という選択肢もあったというが、最終的には数年前から暮らしていた相模原での開業を決めた。「自然や畑の多いところがいいなという思いもあったし、相模原は昔からの文化も残っていて伝統的な祭りもある、熟成された街だなと感じたんです。大学生も多くて、子供も増えているし、街としていいバランスだなと」。
故郷の串本町はもちろん、大阪、神戸、南青山に葉山、そして相模原。数々の街を見てきたからなのだろうか、清水さんが地域を見据える視点は深く幅広い。
『C’est la Saison!』という店名は、フランス語で「今が旬!」という意味。旬を大切にするコンセプトの土台には、農学部で得た知識や経験もある。
「料理人を目指すうえで調理師専門学校ではなく農学部に行ったのは、同じ野菜や果物を扱うにしても畑の姿を知っていた方が違う発想ができるのではないかという考えもあったんです。当時は地産地消という言葉もあまり聞かなかったけれど、『KIHACHI』では地場のものを使うことも大切にしていました」と清水さん。「あとは、自分自身もずっと旬でいられるように、という思いもあります」と話す笑顔は、あたたかく華やかなミカン色の店内の雰囲気とよく似合う。
産地に出向き、生産者と触れ合うことも大事な理念のひとつにしているという清水さん。ケーキや焼き菓子に使うフルーツは、ほとんどが農家直送のものだ。缶詰などの加工品を使うこともほぼなく、栗の渋皮煮も特注で煮てもらっているのだとか。「缶詰にするとのっぺらぼうな味になっちゃう。実のなかにも甘かったり苦かったりといろんな味があって、それがフルーツのおいしさですから」。
『C’est la Saison!』はこの相模原本店のほか、2016年には和歌山串本養春(ようしゅん)店もオープン。廃校になった旧養春小学校の校舎内に店を構えているのだが、公共機関以外でここを借りられたのは『C’est la Saison!』が初めて。それも、近隣のポンカン農家と一緒にイベントを開催していたことで実現したのだという。
「地域の文化を発するのも一つの使命だと考えていますが、さらに産地から直接発信したいと思ったのが串本養春店の理由のひとつです。今後は、農家さんや地元との関わりももっと増やしていきたいですね」
フルーツの持ち味を存分に生かしたケーキを頬張りながら、各地の風土や農家の様子に思いを馳せる。旬のおいしさがぎゅっと詰まったやさしい味がするのは、地元を含め各産地の魅力を知り、伝えたいという清水さんの思いが込められているからだろう。
取材・文・撮影=中村こより