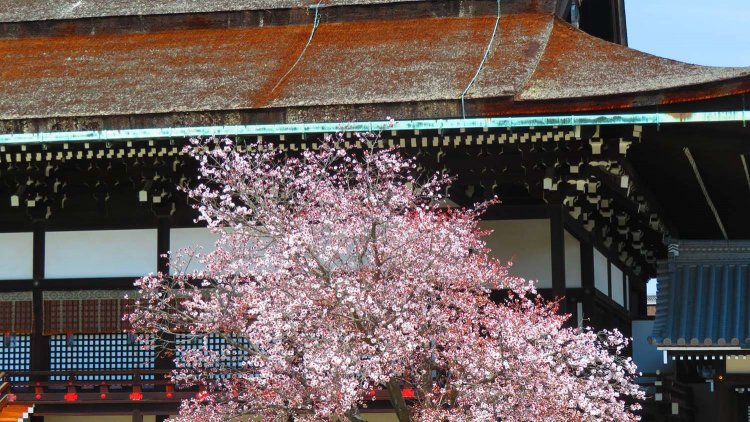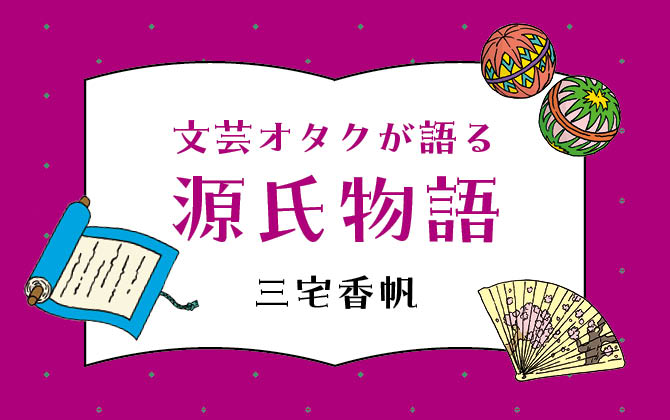ほほえましい和歌のやりとり
『源氏物語』にはいうまでもなく紫式部本人についての言及はない。だとすると、宮中に女房として上がる以前の彼女がわかるのは、『紫式部集』のみなのである。
そういう意味で、宣孝と紫式部の関係は、『紫式部集』の歌集から読み取るしかない。
〈原文〉
人の
け近くて誰も心は見えにけむことはへだてぬちぎりともがな
返し
へだてじと慣らひしほどに夏衣うすき心をまづ知られぬる
峯寒み岩間氷れる谷水のゆく末しもぞ深くなるらむ
〈訳〉
あの人(宣孝)の歌
「近づいたとき、あなたが好きだって、充分わかってもらえたでしょう? これからは隠さず近くにゆける約束をしよう」
私の返事
「私はずっと誰にも隠さずにあなたに会ってきましたよ! むしろ今の歌で、あなたが夏の服くらい薄ーい感情しか私に持ってないことがわかりましたわ」
(それに対する宣孝の返答)
「峯はまだ寒いから岩間の谷水は凍っていますが、きっとこの先、氷がとけていくでしょう……私たちだって最初は冷たくされてもどんどん仲良くなるはずですよね!」
(原文は『新編国歌大観』収録「紫式部集」より引用、訳は筆者による)
……なんだか仲が良さそうで、ほほえましい和歌のやりとりである。
このとき、紫式部は29歳、宣孝は45歳くらいと言われている。紫式部は晩婚、宣孝は何人目かの妻(すでに子供も5人いた)。円熟したふたりだった。しかしだからこそ、「へだてる」つまり「よそよそしい」感じじゃなくなるタイミングは、案外ふたりにとって難しいものだったのかもしれない。
宣孝の機転が利いた和歌の返答
実際、紫式部は宣孝のほかの妻を気にしていたのか、こんな歌を贈っている。
〈原文〉
折りて見ば近まさりせよ桃の花思ひぐまなき桜をしまじ
〈訳〉
「桃の花は遠くから眺めるより、折ってじっくり見たほうがきれいに見えますわ。だからもう、あなたを思いやってくれない遠い桜の花のことなんて、惜しく思わなくていいのですよ」
(「紫式部集」)
実は、この歌は宣孝に送られたものかどうかはっきりしていない。しかしおおむね宣孝に送られたのではないか、そして「桜」とは宣孝の他の妻のことを指すのではないだろうか……という解釈がなされている。つまり自分は桃で、宣孝の他の妻は桜、というわけである。
これに対して、宣孝(と思われる男性)はこんな歌を返している。
〈原文〉
ももといふ名もあるものを時の間に散る桜にも思ひ落とさじ
〈訳〉
「桃の花は、もも、つまり『百』という意味もあるくらいだから、百年間咲き続けるんだろう? 桜なんてすぐ散ってしまうんだから、気にもとめていないよ」
(「紫式部集」)
すごい返答力! だと思いませんか! 紫式部が出してきた「桃」という比喩に対し、「桃といえばそういえば百という意味もあるし、それに比べたら桜なんてすぐ散る儚いものの象徴だし……」と返しているのである。和歌の返答としても機転が利いているし、紫式部の「他の女のこと考えんなよ」という茶目っ気たっぷりの歌に対して、全力で「もちろんきみが一番だよ!」と返しているのも良い。
来てくれない彼氏にLINEを送るかのように
しかし実際は、宣孝はなかなか紫式部のもとへ通えなかった夜もあったらしい。紫式部はこんな歌を詠んでいる。
〈原文〉
入るかたはさやかなりける月影をうはのそらにも待ちし宵かな
〈訳〉
「月がどの方角に入るかわかるみたいに、あなたが他の女性のところに行くのはわかっていたはずなのに、昨晩は上の空で待ちわびちゃった」
(「紫式部集」)
まるで来てくれない彼氏にLINEを送るかのような和歌であるが、こんな紫式部の歌に対し、宣孝はこんなふうに返している。
〈原文〉
さして行く山の端もみなかき曇り心の空に消えし月影
〈訳〉
「いや、月もそっちの方向に行こうとしたんだけど、山の端が曇っていたから夜空に消えてしまったんだよね……昨晩はあなたの機嫌が悪そうだったからさ」
(「紫式部集」)
山の端が曇っているかのように、あなたの心も曇っていたでしょう? だから行かなくて正解だったのでは? ……と、完全に夫婦喧嘩モードの和歌。さっきの和歌はあんなに仲が良かったのに! 桃も百年続くと言っていたのに! いきなり月は向こうに行っちゃってる! とツッコミを入れたくなる『紫式部集』である。
しかし、紫式部と宣孝の夫婦生活は、長く続かなかった。そのことはおそらく『源氏物語』にも大きな影響を及ぼしている、と言われている。
藤原宣孝ゆかりの地
さて、最後に宣孝ゆかりの地を紹介して終わろう。妻も子も多く、和歌もうまかった宣孝。彼は実は、舞も得意だったらしく、長徳4年(998)の石清水臨時祭、賀茂臨時祭で舞を奉納したという記録が残っている。そう、下鴨神社で、彼は舞をつとめていたのだ。ちなみに翌年には、舞のリーダーのような存在(神楽の人長)に任命されており、舞は達者だったらしい。舞も得意で、和歌もうまい、そりゃ妻が多いのも納得だと思ってしまう。
下鴨神社に行った際は宣孝に思いを馳せてみるのも一興……かもしれない。
文=三宅香帆 写真=PhotoAC