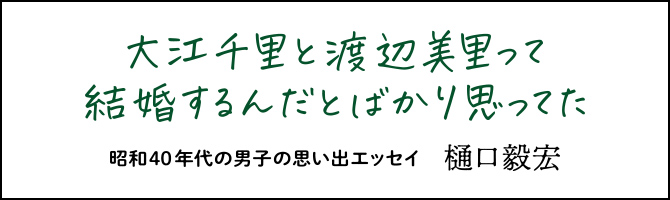プロレスに詳しくない人に説明すると、長州は46歳のときに一度引退している。「千代の富士みたいにボロボロになるまでやりたくない」と発言していたが、2年後にはあっさりと復帰した。プロレスに興味がない人からすると驚きだろうが、引退したはずのレスラーが再びリングに上がるのは珍しい話ではない。大仁田厚なんてこれまで7回引退して、その度に「今度こそホント!」なんて言ってるのだから。
失笑する人は多いだろう。でもプロレスだからいいのだ。反則が5カウントまで許されるとか、鍛え上げた選手が毒霧でのたうち回るとか、幼い頃からいいかげんな世界を見て僕は育った。そしてプロレスから色々なことを学んできた。文豪開高健はプロレスについてこう語っている。「虚の中にこそ実があり、実の中にこそ虚がある。プロレスは大人が見る芸術だ」。ということは、僕はずいぶん早くから大人の仲間入りを果たしていたのかもしれない。
閑話休題。長州は専修大学の名門アマチュアレスリング部出身で、2015年のベストセラー『真説・長州力 1951–2015』によると、長州の指導法は厳しく、練習中に用意していた竹刀がすべて叩き折られるほど激しかったという。
これはある人から聞いたが、著者の田崎健太氏がこの本のためアマレス部で長州と共に汗を流した吉田栄勝に取材をしようとしたところ栄勝さんが急逝したので、娘さんの「霊長類最強女子」こと吉田沙保里に話を聞こうとしたら、「パパをいじめた人の話なんかしません!」と断られたというが本当だろうか。
ミュンヘンオリンピックのアマレス韓国代表というフィジカルエリートにもかかわらず、新日本プロレスでデビューしてからしばらくの間パッとしなかった長州は、メキシコ遠征から帰国すると、髪形を長髪に変えた。これは当時の新日本プロレスの日本人レスラーのスタイルを破ることだった。そして年下のスター藤波辰巳(当時)に、「俺はお前の噛ませ犬じゃない!」とケンカを売った。僕を含めて多くの人がここから長州力を知るようになる。
毎週金曜夜8時、ふたりの戦いは「名勝負数え歌」(Ⓒ古舘伊知郎)と名付けられた。スピードの速い展開は「ハイスパートレスリング」と、既存の体制に正面からぶつかっていく長州は「革命戦士」と呼ばれ、瞬く間にファンの支持を得た。
猪木の事業失敗により新日本プロレスの経営が問題視されると、長州は自らの軍団とともにジャイアント馬場の全日本プロレスに移籍した。しかし184センチ(公称)100キロそこそこだった長州は線が細く、からだがデカい外国人天国の全日では明らかに見劣りしていた。数年で古巣の新日にリターンすると、参議院議員になりセミリタイアした猪木に代わり、現場監督を務めた。
それまで新日本プロレスの道場において強さの基準は「プロレスの神様」ことカール・ゴッチが作った「どのぐらい長くブリッジができるか」だった。しかし長州が道場を仕切るようになると強さの基準は、「どのくらい重いベンチプレスを上げられるか」に変わったと聞く。徐々に長州のからだは大きくなり、外国人に当たり負けしなくなった。
あれは1991年3月21日、東京ドームだった。僕は日雇いの警備員アルバイトとして、選手の花道に位置した。セミファイナルで長州が目の前を通った。背丈はそれほどでもない。しかし肩から腕の太さは、まるで空気入れで膨らませたようにパンパンに盛り上がっていた。当時長州は39歳。気力、体力ともに充実していただろう。タイガー・ジェット・シンを流血KOした長州は鬼神を思わせた。
これ以降ぐらいか、長州は強くて怖いイメージを観客に植え付けていく。95年10月9日、UWFインターとの対抗戦で安生洋二を完膚なきまでに叩き潰した。試合後の控え室でアナウンサーから「長州さん、キレましたか?」「キレてないよ」のやり取りが後に芸人長州小力の持ちネタとなる。
長州が企画した団体対抗戦は次々とヒットした。創業者アントニオ猪木が拵えた20億円以上あった借金を完済。意にそぐわない週刊プロレス編集長のターザン山本を業界から追放し、世界の覇者となった。しかしそれも長続きしなかった。1度目の引退から復帰したものの、明らかに力が落ち、権勢に陰りが見えると、長州の影響を受けた二流のパワーファイターたちがそっぽを向いた。2002年、長州は再び新日を飛び出し、新団体WJを旗揚げ。「プロレス界のど真ん中を行く」と宣言するも、興行は赤字に次ぐ赤字で、数億円の負債を抱えた。このとき一連托生だったはずのレスラーやフロントはほとんど離れていった。特に悲劇だったのは、愛弟子佐々木健介と袂を分かったことだった。長州が突き進んだど真ん中は地獄だった。
それから10数年が経った。その間長州はまたまた新日に戻り、またまた飛び出て精彩を欠いたファイトを細々と続け、離婚した奥さんと再婚して、たまにバラエティー番組で笑顔を見せた。生死流転。むかしを知る者には想像もつかなかった晩年を送っている。
それでも僕や多くのプロレスファンは、今なお長州力に大きな幻想を抱くことをやめない。僕はいまのプロレスも大好きでよく観ている。ゴールデンタイムで放送していた頃のプロレスより、いまのほうが技も豊富だし展開も飽きさせない。実によく計算されている。けれども「役者」として捉えると、長州力に並ぶ現役のレスラーはいない。残念ながら。
長州力の何がそこまで僕たちを駆り立てるのか。気性の激しさと出自か。物語のような波瀾万丈な生き様か。いや違う。それは後付けだ。長州力はただシンプルに、魂を揺さぶるような名勝負がずば抜けて多いからだ。
数年前、僕がプロレス小説『太陽がいっぱい』を上梓すると、編集からパブ企画として「長州力と対談はどうですか?」と聞かれたが、丁重にお断りした。畏れ多かった。それに長州に限らず、プロレスラーと話をしたいとは思わない。レスラーがリングに上がる。それに声援を送る。レスラーはそれに応えたファイトを見せる。それがレスラーとファンのあるべき対話だと思う。
そして2019年6月26日、長州力が再びリングを降りる日がやってきた。場所は後楽園ホール。情弱の僕はこの興行を知ったときはすでに売り切れ。あわててCSファイティングTVサムライに加入した。
長州力・越中詩郎・石井智宏vs藤波辰爾・武藤敬司・真壁刀義。実況席には辻よしなり、盟友天龍源一郎。リングコールは田中ケロ、レフリーはタイガー服部。所縁のある人たちが集まり、舞台は整った。長州は奮闘した。しかし最後は真壁のトップロープからのニードロップをまさかの4連発でリングに沈んだ。テンカウントゴングはなし。引退セレモニーに付き物の花束贈呈もなかった。長州はマイクを握る。
「私にとってプロレスとは何だったのかと振り返りますが、全ては勝っても負けてもイーブンでした。一つだけ勝てない人間がいました。きょう観に来てくれた家内の英子です」
長身のすらっとした美女がリングに上がる。対戦相手と観客を常に威圧してきた男が穏やかな微笑みを見せる。最愛の人と抱き合い、キスをかわす。ボロボロになるまで傷ついた兵士長州力は、四方に深々と頭を下げて、お腹に孫を宿した娘の待つ控え室へ、人間吉田光雄に戻っていった。こんなに美しい最終回、見たことない。
ああ、プロレスは生き様が見える、最高の芸術だ。
『散歩の達人』2019年8月号