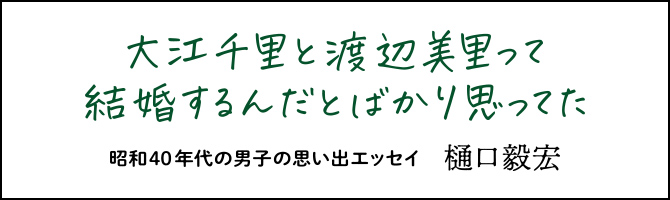あいつがいなくなってからは、クラスでつるむ相手は2週間ごとに変えた。たまに思い出したように人に親切にしたり、横暴に振る舞ったりした。大袈裟に笑い、頬を浮わつかせた。退屈という一語では言い表せない教室。つまらないのは周りではなく、俺自身なのだと認めたくなかった。
俺たちのほとんど大半には、ろくな将来などない。華奢な未来は、俺たちを必要としていない。そう思い込んでいた。今で言うスクールカーストなどない高校だった。俺の在学中に野球部は2回甲子園に行き、バレーボール部は10年連続で全国大会に出場した。体育ができる奴がいちばん偉い慣習により、不良は廊下の隅を歩いた。軽蔑に値する人間にだけ愛想を良くするよう努めた。たいして好きじゃない奴だけ家に連れてきた。そのうちのひとりとは数年後、バイト先で再会した。彼は女装していた。
体育祭の日、早引きした。担任の小井戸は他の生徒たちが見ている前で俺の頬を2回張った。舌で頬の裏側を押す。帰りに駅の横にある牛丼太郎を搔き込んだ。錆びた鉄の味がした。
土曜日は一族経営の馬鹿息子がテレビを通して役に立たない訓示を垂れ流す。あれで忍耐を学んだ。正確に言えば、忍耐の殺し方を。
「趣味は著名人の死亡記事のスクラップ」という古参の教師がある日背後から階段を突き落とされて入院した。犯人が自分でないことに軽く落胆した。
ポケットにイエーツの詩集を忍ばせて、それが露呈したら舌を噛み切ってやると思っていた。どこにでもいる少年だった。いつか大きな秘密を抱えたいと願っていた。きっと誰にも知られずにありていな秘密を道連れに死んでいくのだと、確固たる予感があった。
年が明ける前から連日の下血報道があり、陽水のCMは口パクになっていた。
1月7日がやってきた。テレビは昭和を振り返る特別番組で溢れた。大人たちは「昭和が終わる」と感慨深げだったが、俺は今すぐ世界が終わればいいと願っていた。時代の転換でも裁きの日でもない。だから感傷的になることもない。それとはまったく関係なく、あることを決めていた。あいつとともに、学校に火を放つ。あいつが退学に追い込まれた、せめて
もの復讐だった。ゴーサインを待ち続けてずいぶんになっていた。
その夜のことだ。電話の連絡網で、当分の間学校は休みだという。
「わたしさあ、爆風スランプの武道館に行くはずだったのにさー」
受話器を握りしめたまま黙っていた。
「そういえばさ、聞いちゃったよ。あんたマジで考えてるのーー」
話の途中で電話を切った。どこで聞いたのか、誰が漏らしたのか、問うまでもなかった。ポストを覗くと手紙が入っていた。長い長い手紙だった。2回読み返すと台所で燃やした。思いの外大きな紫色の炎を上げるとそれはこの世界から消滅した。
来ないものを待つ。それを仕事にしていた。裏切りなどよくあることさと言い聞かせたが虚しかった。
なぜかこの頃、家には俺ひとりしかいなかった。寄る辺なき夜をあてもなくグリーンのジャケットに深く手を差し込み、街を彷徨った。あずま通り商店街を進みニコマートの前を横切る。レンタルビデオ店のアップルに顔を出すと真夏の海岸のような盛況ぶりだった。サンシャイン通りを目指す。池袋ではマクドナルドより先にできたロッテリア。東宝はもうなかったかもしれない。いかがわしい街のいかがわしい住人も今夜ばかりは声をかけてこない。ぐるっと回って駅前に着く。全身を包帯で巻いた人が蹲って黒のゴミ袋から野菜屑を貪っていた。ダンキンドーナツの前を横切り、もう一度公園に戻る。よく見かけた浮浪者はいない。ブランコに揺られながらひとり訳ありのセンチメンタリズムを気取った。あいつとよく回ったコース。見えない影が見えてきそうな、最後の散歩だった。
夜明け前、祖母から少しずつくすねた睡眠薬を一気に飲み干した。この世のすべてに対しての抗議のつもりだった。眠りから覚めると昭和は終わっていた。新しい元号に入って数日が経過していた。ひどく頭が痛かった。
それから1日も学校に行かなかった。卒業式ぐらいは顔を出してもいいと思っていたら寝坊した。
俺はようやく悟った。誰かに期待するのは間違いだし、世界は小さな個人の思い通りになどならない。世界を変えられなければ自分を変えること。自分を変えられなければ、世界を変えなければならないことを。
俺が後者を選択したのは、それから20年後のことだった。
そして今も考える。自分はまだ、長い眠りの中にいるのではないか。決して目覚めることのない暗闇の中でずっと夢を見続けているのではないかと。
『散歩の達人』2019年3月号