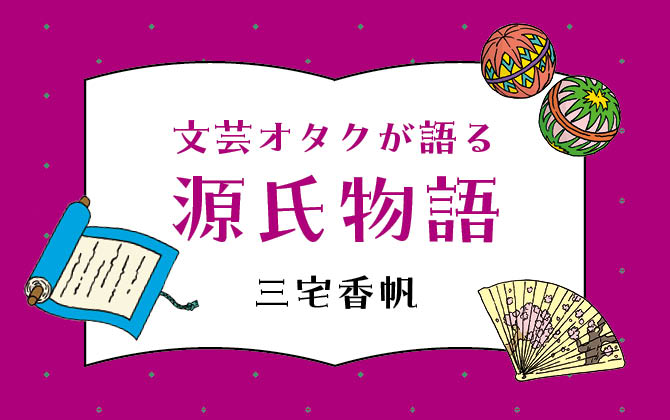「物語」に熱中する玉鬘と、「物語」を嘆く光源氏
『源氏物語』「蛍」の帖。梅雨がいつになく長くて、退屈していた玉鬘(たまかずら=頭中将と夕顔の娘。光源氏が娘代わりに引き取って面倒を見ていた)たち。そこで幼い玉鬘は、物語を毎日写して読むことに熱中していた。女房たちも玉鬘とともに物語を楽しんでくれていたのだ。
しかし玉鬘はさまざまな物語を読みながら「いやあ、私くらい変な運命をたどっているキャラはいないなあ」とひとりごちる。
〈訳〉
不思議な運命をたどる姫君たちはたくさんいる。物語に書かれていることは、実際にあったこともなかったことも綴られているのだろう。しかし、玉鬘は思った。
「私と同じような目に遭っている子はいないよねえ……」と。
〈原文〉
さまざまにめづらかなる人の上などを、真にや偽りにや、言ひ集めたるなかにも、「 わがありさまのやうなるはなかりけり」と見たまふ。
(『新編 日本古典文学全集22・源氏物語』「蛍」より原文引用、訳は筆者意訳。以下同)
読者としては、「そりゃそうだ! 玉鬘もフィクションの人物なんだから!」とツッコミを入れたのかどうか。しかし物語の登場人物にこんなことを言わせるあたり、『源氏物語』のメタ構造はすごい。実はこのメタ構造、このあとのキャラクターにも引き継がれていく。というのも玉鬘が物語ばかりに熱中している様子を見て、光源氏は「嘆かわしい! そんなに物語ばかり読んだらろくな大人になりません!」と言うのである。
〈訳〉
「ああ、嘆かわしい! 女というものは、なんでわざわざ自分から嘘にだまされようとするのだ? 物語の中に真実なんてほとんどないのに。なんで真実ではないと知りながら、こんなくだらない話に熱中するのか。こんな暑い五月雨の日に、髪の毛がべたべたと乱れるのもいとわないで、よくもまあ物語ばっかり写して……信じられない」
〈原文〉
「あな、むつかし。女こそ、ものうるさがらず、人に欺かれむと生まれたるものなれ。ここらのなかに、真はいと少なからむを、かつ知る知る、かかるすずろごとに心を移し、はかられたまひて、暑かはしき五月雨の、髪の乱るるも知らで、書きたまふよ」
(『源氏物語』「蛍」)
物語を嘆く、物語中の光源氏……! なんともメタ構造。読者としては笑いながら読んでしまう。
物語大好き少女の言葉にこめた、紫式部の想い
このあとも光源氏は「物語嫌い」を発揮する。なぜわざわざ嘘を読むのか、不自然に誇張してある場所もいっぱいあるではないか。どうせ読むなら、本当にあったこと——歴史を知るべきではないのか。
しかし物語好きの少女・玉鬘は、そんな光源氏に反撃する。彼女は「本当にあったことを、少し誇張して、書いているだけだ」と語るのだ。
〈訳〉
「たしかにこの物語には、『これは●●さんのお話ですよー』とは直接的には書いていません。
だけどきっと、この話の善悪どちらも、現実に生きている人がそのまま描かれているんです。
良いことも悪いことも、ひとりで見たり聞いたりしてるだけでは、どこか満足できない。誰かと共有したい、って思ってしまう。だからこそ物語という形になって、書き始められる。
もし善いことを書こうとすれば、少し誇張して善いことばっかり書いてしまう。読者に楽しんでもらうために。あるいは、悪いことを書こうとすると、ちょっと現実にはありえないほどの悪いことを書こうとしてしまう。
でもそれは、現実のことを書いているだけなのですわ。
人間がみんな持っている善悪どちらも描かれているのが——物語なんです」
〈原文〉
その人の上とて、ありのままに言ひ出づることこそなけれ、善きも悪しきも、世に経る人のありさまの、 見るにも飽かず、聞くにもあまることを、後の世にも言ひ伝へさせまほしき節々を、心に籠めがたくて、言ひおき始めたるなり。 善きさまに言ふとては、善きことの限り選り出でて、人に従はむとては、また悪しきさまの珍しきことを取り集めたる、皆かたがたにつけたる、この世の他のことならずかし。
(『源氏物語』「蛍」)
紫式部の想いがこもった反論である。実際、「蛍」の物語批評は、日本ではじめての「批評」ではないか、と言われている。このあとも、『うつほ物語』など、さまざまな物語についての批評がなされる。紫式部の批評眼が、玉鬘という物語大好き少女の言葉によって生まれ変わる。『源氏物語』にはそんな文芸批評のはじまりすら、綴られているのだ。
フィクションの種は「現実」。紫式部の物語観
おそらく紫式部は、『源氏物語』が評判になったことで、「嘘を書いている人」だと評されたことがあるのかもしれない、なんて私なんかは妄想してしまう。
実際、紫式部が嘘を人々に広めた罪を背負っていることになる『源氏供養』という物語が、能の世界には存在する。そう、仏教の世界においては嘘をつくことは罪であり、紫式部もその理論でいうと嘘を書いて人々をだました人になってしまうのだ。しかし、紫式部はあらかじめその理屈に反論している。ほかならない『源氏物語』という嘘の世界の中で。「嘘を書いてはいるが、実はそれは現実の写し鏡でしかないのだ」と。フィクションは現実を誇張したものであり、現実が種である。現実で見聞きしたことを、自分のなかだけでとどめておけなくて、だからこそフィクションの形に変えて世に出す。それが紫式部の物語観なのであった。
ひとつ面白いエピソードがある。『源氏物語』の作中で、玉鬘の継母になる紫の上も、物語が大好きだった。しかし平安時代の物語には、「継母が意地悪する」という話がよくあった。紫の上は「これは教育的によろしくない」と判断して、玉鬘に継母が意地悪する話は読ませずに、隠すのだった。「メタ構造がすごい……『源氏物語』」と千年後の読者としても唸ってしまう。
ちなみに、玉鬘が物語を読んでいた六条院は、現在の京都御所の近く。御所を散歩する際は、ぜひ『源氏物語』にも思いをはせてみてほしい。台風が近づいていたり、雨がやまなかったりするときは、室内で物語でも読むのが一番かもしれないけれど。
文=三宅香帆 写真=さんたつ編集部、PhotoAC