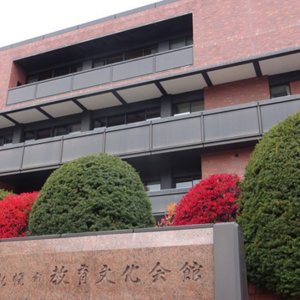私がいたチームは強豪で、札幌市の大会ではいつも上位だった。全道大会にも出場している。しかし私は補欠で、公式試合に出ることは少なかった。
強豪校の補欠は損な役回りだ。朝練も放課後の練習もレギュラーと同じだけこなしているのに、本番の試合ではベンチから声援を送るだけ。しかも私の学年はチームメイトが8人しかいなくて、私ともうひとりKちゃんが補欠だったのだが、Kちゃんは5年生になる前に辞めてしまった。それから卒業まで、私は同学年でたった1人の補欠だった。
それでもバレーボールを辞めなかった理由は、自分でもよくわからない。単純に考えればバレーボールが好きだったからなんだろうけれど、当時の私は競技に対してそこまでの熱意を持っていなかった気もする。熱意がないのにあれだけの練習量をこなしていたのも変な話だから、熱意はあったのだろうが、それを自覚していなかった。
チームメイトである友人たちもみんな、ハードな練習をこなしているものの、そこまでの熱意を持っているようには見えなかった。みんな熱意を秘めてはいたのだろうが、あまり表に出さなかったのだと思う。子供たちより顧問である先生や親たちのほうが、応援に熱が入っているように見えた。当の子供たちは、「熱血」や「青春」とはほど遠いクールさで、淡々とバレーボールをしていた。

私がバレーボールを始めたきっかけは姉だ。姉は小学生から高校生までバレー部で、うちの両親は姉の応援に入れ込んでいた。そのため、私も幼稚園児の頃から両親に連れられて姉の試合を見に行った。バレーをしている姉はかっこよくて「私も大きくなったらお姉ちゃんみたいになるんだ」と思った……なんてことはなくて、私はバレーの試合が退屈でたまらなかった。同じように連れて来られた、試合に出ている誰かの弟と、観客席で鬼ごっこをして遊んでいたのを覚えている。
小4になって、私もバレーボールチームに入団できる年齢になった。父は私にチームに入ってほしそうだったが、直接そう言われたことはない。私もバレーを始めるつもりはなかった。しかしある日、父と家の前でパスをして遊んでいたところ、「あ、けっこう楽しいな」と思った。それまでも父とバレーボールで遊ぶことはよくあったが、なんだかその日急に、バレーの楽しさがわかったのだ。それで、自分からバレーボールチームに入った。4年生になってすでに数カ月が経っていたので、同学年の子より少し遅れての入団だ。
うちのチームは姉の代から変わらず強豪で、練習も多かった。月曜は近くの別の小学校に行って合同練習、水曜は放課後、土曜は一日中練習がある。朝練も週3回くらいあった。日曜はほぼ大会か練習試合だ。今思えば、それだけバレーボールをやって学校の授業も受けて、ピアノも習って友達とも遊んで、よくそんなに時間と体力を捻出できたなと思う。
私は運動会の徒競走ではいつも1位だったので、自分ではまあまあ運動神経がいいと思っていたが、やってみるとバレーボールはど下手だった。最大の欠点は、ボールが飛んでくるのが怖いことだ。強いサーブやアタックは怖くて、レシーブするときに目をつぶってしまう。また、身長は中くらいだが力がなくて、アタックもサーブも威力が弱い。小学生バレーはポジション固定制なのだが、私はレシーブもアタックもできないので、消去法でセッターになった。
私たちが4年生のとき、5年生はひとりもいなかった。小学生にとっての2歳差は大きい。6年生の先輩方は私たちを子供扱いし、かわいがってくれた。
私たちは休みのたびに試合に同行し、6年生の応援をした。バレー部は伝統的に、うちわを叩きながら応援する。ある日、応援しているとチームメイトのひとりがうちわを叩く仕草を指して「これ、うなぎ焼いてるみたいじゃない?」と言い出した。そして、4年生全員でやいやい言いながら「うなぎ!(3拍手)焼き鳥!(4拍手)オー!」という応援を編み出した。試合中にそんなことをしていたら、試合を終えた先輩方が笑いながら「さっきやってた応援何? やってみせて!」と言ってきて、恥ずかしかった。
同学年のチームメイトは、最初は8人、Kちゃんが辞めてからは7人で、みんな仲がよかった。バレーボールの強豪チームなんていかにも負けん気が強そうだが、7人ともわりとおっとりしていて大人びているので平和だ。練習がない日も、よく誰かの家に集まって遊んだ。お別れ会やクリスマス会では合奏や寸劇を披露したが、みんなで集まって練習するのがとても楽しかった。

5年生になると先輩が卒業し、私たちは最高学年になった。他のチームは6年生が中心だが、私たちは5年生ながら市内でかなり強いほうだった。4年生の後輩も入ってきた。
顧問の先生は、たぶん当時30代半ばだったと思う。明るくてひょうきんなので生徒から人気があるが、やや感情的になりやすい男性教諭だった。練習中、先生が怒って職員室に行ってしまい、みんなで謝りに行ったことが何度もある。先生からすると、おとなしくて声が小さい私たちはやる気がないように見えたのだろう。先生のことは大人げないと思っていたが、嫌いではなかった。
私は相変わらず補欠のセッターで、正セッターの美奈ちゃん(仮名)は市でも1、2を争うほどの名セッターだった。父はよく「サキちゃんも他のチームならレギュラーになれる実力があるのに、うちのチームには美奈ちゃんがいるからなぁ」と嘆いた。
試合のときは後輩たちとベンチから応援するが、たまにピンチサーバーとして出してもらうことがあった。私はフロントサーブ(正面から打つサーブ)がネットに届かないため横打ち専門だったが、コントロールはわりと安定している。なので、サーブが不調の人がいると代わりに出場しサーブを打った。
ただ、私はメンタルが弱く、負けそうな局面になると明らかに苦しげな表情になってしまう。先生からはよく「気持ちで負けるな!」と怒られた。正直、正念場では私ではなく美奈ちゃんを使ったほうがいい、と思っていた。

5年生からは、夏休みに他の学校と合同で行われる合宿に参加した。合宿所は深川にある。深川市は旭川市の隣の市で、私が住んでいた札幌市からは車で1時間以上かかった。
学校に集合して、保護者の車に分乗して深川へ向かう(休みのたびに道内のあちこちに送迎してくれた保護者には頭が上がらない)。車の中では、みんなでしょうもない話をしてゲラゲラ笑った。
そういえば、大人になってから、キャプテンだっためぐみ(仮名)に「バレーの試合で栗山町に行ったとき、『栗山のいちごは栗山一!』って書かれた看板があってみんなで笑ったよね」と言われたことがある。私はまったく覚えていないが、そういうことはありそうだ。あの頃は箸が転げてもおかしかった。
深川の合宿所は公共の施設で、体育館に宿舎が併設されている。長い廊下に居室が並ぶ様子は、少し病院に似ていた。ガラス張りの大きな食堂や浴場などもあった。
部屋はチームごとに使うことになっていて、一部屋に2段ベッドが4つあった。私は上の段で寝ることになったのだが、自宅じゃないからかなかなか寝つけず、下の段の人に気を使いながら何度も寝返りを打った。
合宿はたしか2泊3日で、1日目は練習、2日目がトーナメント戦だったと思う。ゲストとして元バレーボール選手が来てくれた気もするが、それはまた別の機会だったかもしれない。
夕食と入浴のあとは体育館でレクリエーションが行われ、各チームが出し物を披露することになった。出し物を用意してこいとは言われていないので、みんなアドリブで何かしらを披露する。芸達者なメンバーがいるチームはいいが、うちのチームは全員シャイだったので、小さな声でもじもじと岡本真夜の『TOMORROW』を歌った。当然だが、まったく盛り上がらなかった。
みんな人見知りなので他校との交流はほぼなかったが、月曜に一緒に練習している隣の小学校の子たちとは少し喋った。その中に、幼稚園で同じクラスだった子がいた(向こうは私のことを覚えていないっぽい)。彼女は他のチームの先生のことを「かっこいい!」とキャーキャー噂していて、先生をかっこいいと思う発想がなかった私はたいそう驚いたのを覚えている。

中学生では演劇部に入ったので、バレーは辞めてしまった。バレーを辞めてからは、登山以外の運動は一切していない。今は登山もしていないし、家で原稿を書いているだけなので完全に運動不足だ。
すっかりバレーボールから縁遠くなってしまった私だが、ライターになってから、「人生のうちで強豪校の補欠を経験しておいてよかったな」と思うことが多い。望む評価をされなくても腐らずコツコツと努力を続けた経験は、私にとって大きな財産となっている。
また、みんなで集まってバレーをしたいなと思う。日課だった100回パス、今なら30回も続かないかもしれない。
文=吉玉サキ(@saki_yoshidama)