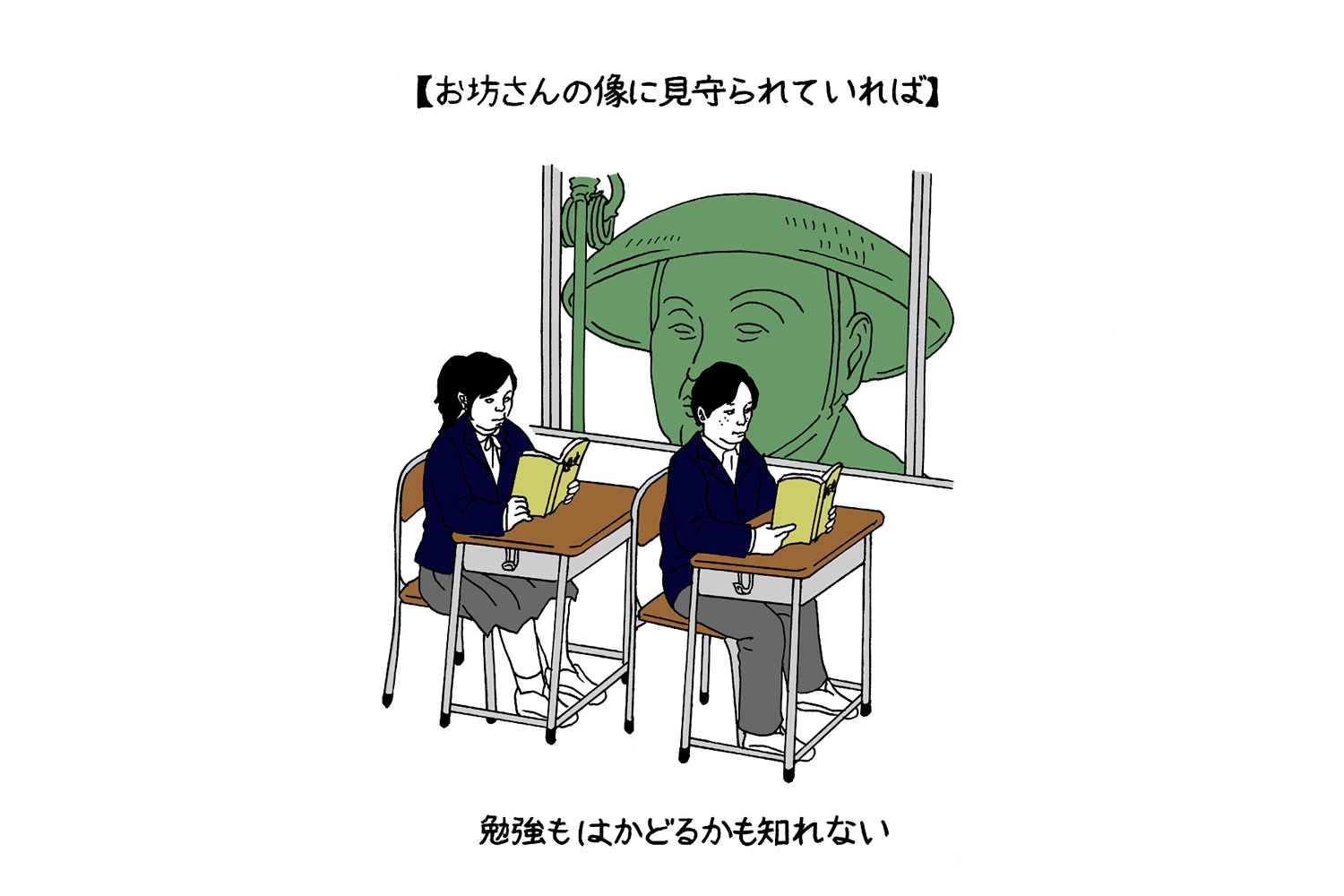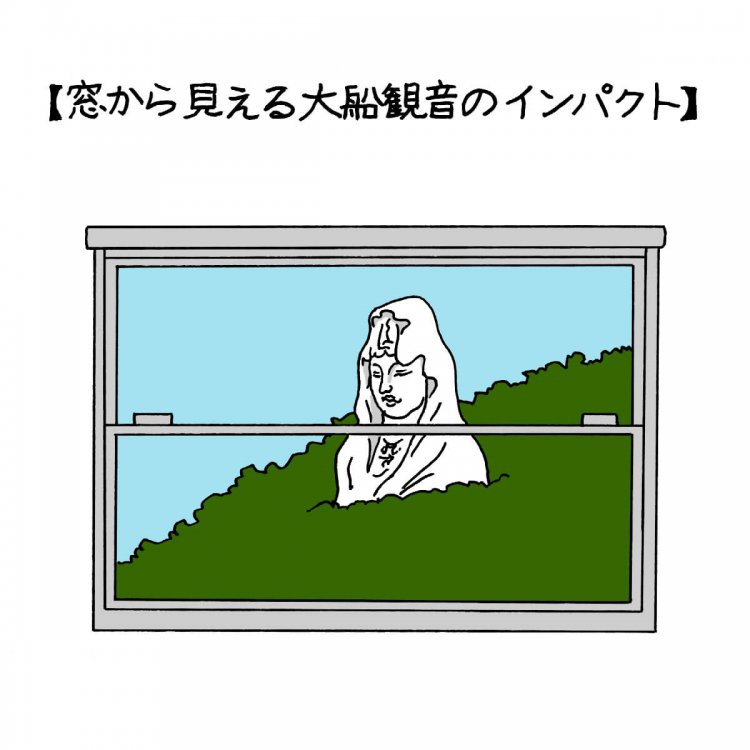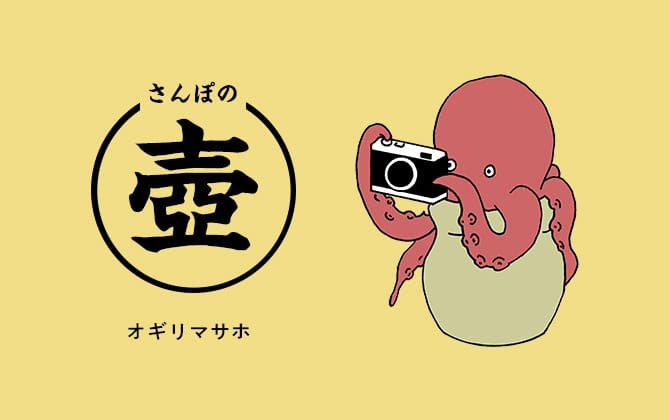子供たちに、お坊さんに興味を持ってもらう方法
6世紀に仏教が伝来してから、日本では時代ごとに名のある僧が活躍し、その功績は中学校の歴史の教科書にも記載されている。しかし中学生にとってみれば、浄土宗だろうが禅宗だろうが、特にどうでもいい事柄と思われる。そんな中学生たちに、お坊さんに興味を持ってもらえる方法はないだろうかと思っているとき、ふとある存在を思い出した。各宗派の寺院境内にある、開祖の像である。
開祖の像は、堂内に安置されているものもあるが、屋外に設置されているものは多くの人の目を引きやすい。こうした像を見ることで、単なる歴史上の人物であったお坊さんたちに、親近感が湧いてくるのではないだろうか。
今回は、中学校の歴史教科書で「新しい仏教」を伝えた存在として挙げられている平安時代の最澄・空海について見ていこう。
最澄・空海に会いに行こう
まずは、唐に渡った後に日本において天台宗を広めた最澄について。総本山である比叡山延暦寺をはじめ、天台宗の寺院には伝教大師(最澄の没後に贈られた称号)の像が見られる。天平年間に行基が開いたと伝えられる稲城の常楽寺にも、台座に「瞻仰崇信」(せんぎょうすうしん)と刻まれた最澄像がある。
常楽寺の境内には、幼少時の最澄をモチーフとした童子像もあり、最澄自身が敬いの対象になっていることが分かる。
きっと中学生たちも、この最澄像を見て共感を得られるに違いない。
最澄像よりも多い印象なのが、真言宗を広めた空海(弘法大師)像である。空海は布教のかたわら、全国を行脚し困窮者を救済したとされ、日本の各地に空海の伝説が残っている。そのためか、全国の寺院で弘法大師像を見ることができるのだ。
中には二宮金次郎像と並び建立されている弘法大師もあり、中学生たちもこの像を見て勉学に励んでほしいものである。
新潟の巨大弘法大師像
ところで、数ある弘法大師像の中で、ひときわ強烈な印象を放つ像を新潟の街中で発見した。
高さ20m近く(実際の像の高さは9mほどだそうだが、建物の上に設置されているため思った以上に大きく見える)はあろうかという真っ白い弘法大師像は、異様な威圧感をもって我々を見下ろしている。新潟の中学生たちは、この巨大弘法大師像が、歴史の教科書に出てくる「真言宗を広めた空海」と同一人物だと気が付いているだろうか。
鎌倉時代に入ると、いわゆる「鎌倉新仏教」と呼ばれる新しい仏教の流れが起こり、各宗派の開祖たちが活躍する時代になる。次はこの鎌倉時代のお坊さんたちの像を追っていきたいと思う(次回に続く)。
イラスト・文・写真=オギリマサホ