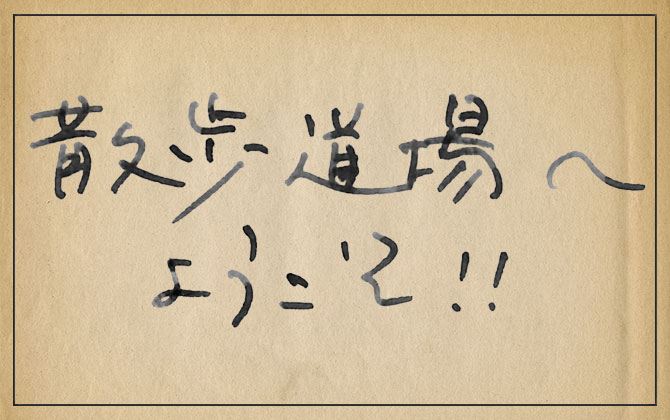給水塔は団地のシンボル
高い場所に水を貯め、水圧をつけて広い区域の隅々まで効率よく水を送り届けるための施設、それが「給水塔」だ。
UCさんは、「日本給水党」党首を名乗り、長年に渡って各地の給水塔を記録し続けている。
「小学校5年生の頃、福島から大阪へ引っ越してきた時、近所の団地にあった給水塔に目が留まりました。私が『とっくり型』と呼んでいる、とっくり状の形をした給水塔です。『なんだか変なものがあるな』と、ずっと記憶に刻まれていたものの、団地の建て替えで、気づいたらその給水塔はなくなってしまいました。
その後2008年の4月に、偶然通勤電車の窓から給水塔が見えたんです。今度こそ見に行ってみようと、迷わず電車を降りて近くへ行ってみたら、子供の頃に見たものと同じ『とっくり型』の給水塔が佇んでおり、その存在感に圧倒されました。
途端に興味がわき、団地の給水塔のことを調べてみようと思い立ったものの、当時は情報が一覧でまとまったサイトや本などは見当たりませんでした。こんなにユニークな存在が、さして記録もされず、人知れず解体されていっていることを知り、だったら自分で調べてみようと記録を始めることにしました」
給水塔は、浄水場や工場といった広い区域への給水が必要な場所に設置されている。中でもUCさんが注目するのは、団地の給水塔だ。
「最初に気になったのが団地の給水塔だということや、団地自体が好きという理由もありますが、団地の給水塔ならではの良さがあります。
たとえば団地の給水塔は、団地という広いエリアの中で配置まで考慮されており、団地のランドマークにしようという意図が感じられるところが魅力です。団地によっては、団地内の集会所やお店などがある中心エリアに給水塔を設置しているところもあります。
特に高度経済成長期のあたりに作られた団地には、地方から地縁のない東京や大阪などの大都市へと、人が多く集まりました。地縁や血縁でつながっていない人たちの交流を育むため、団地内に集会所や公園などを集約させ、団地のシンボルとして給水塔が設置されることもありました。
工場などの給水塔は基本的に従業員以外は近づけませんが、団地の給水塔は地域に開かれた身近な存在というところも魅力です。団地という日常空間の中に、給水塔がどんとそびえ立つことで醸し出される非日常感も、どこかおもしろいと感じています」
とっくり型に円盤型 バリエーション豊かなデザイン
現在全国に残っている給水塔は、800〜900基ほど。その中でUCさんは、これまでなんと730基もの給水塔を巡り歩いた。
「土地勘のない場所の場合は、まずUR(独立行政法人都市再生機構)や公営住宅のサイトで片っ端から団地の住所を調べます。そこから航空写真をチェックし、給水塔らしきものが写っているかどうかを確認します。今だとGoogleのストリートビューを使うこともありますが、活動開始当初は対象エリアが限られており、航空写真も今のように解像度が高くありませんでした。
いざ見に行ってみると、思っていたのと違う形だったり、既に解体されてしまっていたりしたこともありました。
そうやってあらゆる団地を見て回るうちに、最初に見た『とっくり型』以外にも、様々な形の給水塔があることが分かってきました」
ひとくちに団地の給水塔といっても、外観のデザインは様々だ。2018年に出版した著書『団地の給水塔大図鑑』(シカク出版)の中では、給水塔の形状を12タイプに分けて紹介している。
「団地自体は基本的に四角い形状ですが、給水塔は、水圧をつけるという役目を果たせば外観は割と自由なので、形状や塗装に凝ったものが結構見られます。
最も数が多いのは『ボックス型』ですね」
「関東では『円盤型』がよく見られるものの、大阪ではほとんどなく、『ボックス型』や『とっくり型』が多いなど、地域や団地の供給元によって多少の傾向が見られます」
「どのタイプも平等に愛でていますが、中でも『とっくり型』は、最初に気になった給水塔のデザインだったこともあり、特に思い入れがありますね。おそらくシルエットが特徴的なためか、漫画など絵に登場する給水塔も、『とっくり型』が多いように思います」
晴れた日の元気な姿を写真に収める
UCさんは給水塔を撮影するとき、晴天の日に順光で撮ることにこだわっている。そのため給水塔を訪れる際は、事前の情報収集や行程の計画を綿密に行う。
「曇り空で撮ると影がなくなる良さはありますが、やはりちょっと寂しい雰囲気になってしまいます。次にまた行こうと思っていても、給水塔がなくなってしまう場合もあります。最後に撮る写真になるかもしれないので、かつてその団地に人が溢れて活気があった頃の印象になるよう、なるべく晴天で撮ることにこだわっています。
そのために週間予報で逐一天気をチェックし、太陽の高さや角度が分かるアプリを使って、給水塔の正面から光が当たる時間を確認しています。特に遠方の給水塔を見に行く際は、公共交通機関の時間だけでなく、太陽の角度なども考えながら、回るルートを綿密に計画しています」
撮影時は、給水塔そのものだけでなく、団地全体の中で給水塔がどこに配置されているかも記録するようにしている。
「給水塔の位置が記された案内板も撮っています。地図を見ながら、その給水塔が団地の中心的な存在なのか、水道管との関係で配置が決められたのか、といったことを想像するのも楽しいですね」
給水塔そのものの形状だけでなく、給水塔を構成するパーツも見逃せない。中でも目が離せないのがはしごだ。
「給水塔によっては、上のタンクへ点検に行くためのはしごがついています。タンクに絡みつくように付いていたり、針金細工のように細かったり。はしごがついていると自分が登っていくスケールで見てしまうので、より給水塔の大きさを実感しますね」
前述の著書の中では、実際に給水塔の中に設置されたはしごを登る様子がコラムとして紹介されている。ぜひお読みいただき、給水塔の巨大さを体感していただきたい。
給水塔は年々減り続けている
SNSや書籍、ブログ等での発信を通し、給水塔を愛でる人たちの輪は少しずつ広がっている。しかしポンプの性能向上にともない、水圧をつけるためにわざわざ高い場所に水を貯める必要がなくなったこともあり、年々給水塔の数は減り続けている。
「団地の給水塔が作られたのは、主に昭和30年〜50年代。建物の寿命もあり、東日本大震災などの大きな災害や、東京五輪のようなイベントを契機に、待ったなしで解体が進んでいます。
引き続き、現存する給水塔は記録し続けていきたいですね。いま行ってみたいのは、福島です。団地のような構造をしたライオンズマンションの中に円盤型の給水塔があるんです。子供の頃に住んでいた場所の近くだったんですが、子供の行動範囲は狭いので、近くにあっても気づいてはいませんでした。
一方、自分だけで全ての給水塔を巡るのには限界がありますし、一度行った給水塔の最新状況は地元の方のほうがキャッチできます。自分の地元にある給水塔を気にかける方が増えると、おのずと各地の給水塔の最新状況がわかるので、うれしいですね」
これまで主に団地の給水塔を記録してきたUCさんだが、最近は街中のビルに設置された給水タンクや受水槽にも観察対象が広がっているそうだ。
「ここ数年は、コロナ禍で遠出が難しいのもあり、建物の屋上の給水タンクや、建物脇にある受水槽も見て歩くようになりました。見ていくと、メーカーごとにパネルのデザインが違ったり、既に製造から撤退したメーカーのものが街中で見られたりと、意外な発見もあるんです。
給水塔の近接ジャンルでもあるので、その視点で見てみると、また給水塔の新たな一面が見えてくるかもしれません」
団地をシンボリックに彩る給水塔は、生活に欠かせないインフラでありながら、建物そのものも魅力的だ。UCさんが撮り収める数々の給水塔は、日本の生活風景や高度経済成長期の一側面を表す、貴重な記録になりそうだ。
取材・構成=村田あやこ 参考文献=『団地の給水塔大図鑑』(小山祐之(日本給水党党首 UC)、シカク出版)、『街角図鑑 街と境界編』(三土たつお編著・実業之日本社)
※記事内の写真はすべてUCさん提供