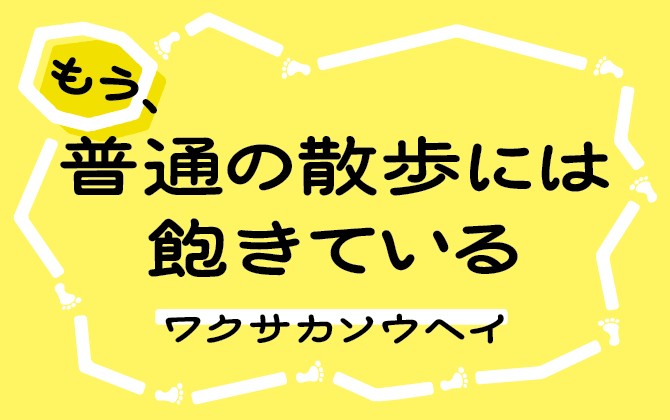草木も眠る丑三つ時、がらんとした街。吹いているのは、不気味な風。おそるおそる歩を進めていくと、突然、路地の隙間から千鳥足でよろめく者が現れる。酔っ払いである。一週間の労働を終え、解放感と疲労感、そしてアルコールをごちゃ混ぜにした状態で路上へと放たれた酩酊(めいてい)者。そのフラフラと歩く姿は闇夜の景色と相まって、まるで魂をどこかに置き忘れてしまった「怪異」のようである。
街灯に照らされ、頭(こうべ)を垂れて、ゆっくりとこちらへ近づいてくる酒気帯びのゾンビは、我々の深夜散歩にホラーテイストな演出を与えてくれる。死んだように静まり返った住宅街。そこにいるのは我々と、正体をなくした徘徊者だけである。世界はもう、終わってしまったのではないか。そんな空想が、妙なリアリティを纏(まと)って浮かぶ。
ウォーキング・デッドの夜
昼間であれば、銀杏並木の下を高級車が滑るように走り、テラス席で住民たちが優雅にランチを楽しんでいるようなエリア。しかし、深夜の2時ともなると、そこには不穏な景色だけが広がっている。
「……生き残ったのは、我々だけなのかもしれないな」
友人が、小声で呟(つぶや)く。彼のセリフを受けて、私は小さく頷(うなず)く。そんな小芝居を挟むことで、深夜散歩に「ウォーキング・デッド」の色付けをしていく。
「ああ、通信も不安定だ……。シロカネシティは、もう全滅だ……」
通信が不安定なのは、格安SIMに月末の低速がかかっているからである。しかし、そんな無粋な真実は不要だ。我々はいま、パニック映画の世界を散歩しているのである。
そこでは、数々のゾンビとの遭遇があった。公園のベンチでぐったりとしている「休眠型」。大声を上げ続けている「威嚇型」。 コンビニの袋を振り回し、泣きながら笑顔で歌っている「支離滅裂型」。普段は立派な社会人であろう彼らは、金曜の夜にアルコールというウイルスに感染し、そして理性と終電を失い、得体の知れない者へと変貌する。一体、何を求めて歩いているのか。まさか、新鮮な肉か? そんなことを想像して、我々は身震いをするが、 実際に彼らが求めているのは「締めのラーメン」か「温かい布団」だと思われる。しかし、それを口にするのも、また無粋である。
さらに歩を進めると、交差点でたむろする酩酊者グループと遭遇した。若い男女が、缶酎ハイを片手に肩を組み、奇声を上げている。単体ならまだしも、集団は厄介だ。絡まれたら最後、ゲームオーバーである。我々はとっさに横の路地へと逃げ込んだ。ああ、この散歩、なかなかにスリリングである。
ふと見上げると、高級マンションの窓には明かりがひとつもない。誰もが、睡眠という名の気絶をしているのだ。すでに奇妙な連帯感を築いていた我々は「生き延びようぜ……」と顔を見合わせ、静まり返った街をさらに歩き続けていく。
空が白み始め、カラスが鳴く頃、我々は白金台から恵比寿を抜けて、渋谷へとたどり着いた。気づけば、ゾンビの姿はどこにもない。それぞれの巣へと戻ったのか、あるいは駅のベンチで元来の姿を取り戻すべく休息しているのか。
朝日に溶けるようにして、パニック映画の世界は霧散した。残ったのは、泥のような疲労感と、「生還した」という虛構の達成感だけである。コンビニで買った温かいお茶を飲みながら、平和な朝の景色の中でようやく人心地つく。
ふと横を見ると、友人も缶で何かを飲んでいる。ウーロン茶だろうか。いや、あのラベルは、もしかして缶酎ハイ……? 歩き疲れか、それともアルコールのせいか。彼の瞳はどこか濁っていて、「あっちの世界」に片足を踏み入れてしまったような色を漂わせている。話しかけても、反応は鈍い。そして「イエニ、カエル……」とひと言こぼすと、彼は地下鉄の駅の中へと消えていった。私は、その背中をただ静かに見送った。自分一人だけがこの世界に取り残されてしまったような寂寥(せきりょう)感に、押し潰されそうになりながら。
こうして金曜日の深夜散歩は、バッドエンド風味で幕を閉じたのである。
文・写真=ワクサカソウヘイ
『散歩の達人』2026年1月号より