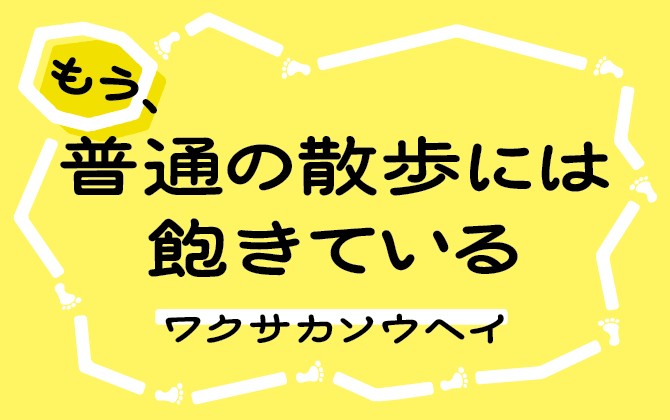近所の風景は、基本的には大きく変わることがない。ならば、自分の心象風景を大きく変えてみよう。そうすれば、散歩の次元はきっとアップデートされるはずだ。
私のマインドは、庶民としての色に染まっている。冷蔵庫の中に期限切れの豆腐を発見しては鉛色のため息を吐き、雨音がしたら急いで洗濯物を取り込んで、半額シールの貼られた刺し身を目指して夕方にスーパーへと足を向ける。そのような日々の繰り返しの中で構築された、小規模な生活者としての心象風景が、この胸の中には横たわっている。
で、庶民の反語は、VIPである。
そうだ、VIPになった気分で近所を散歩してみれば、違った世界を見ることができるのでないか。庶民マインドをVIPマインドに上書きしてみようではないか。
しかし、VIPのマインドとは、どのように構築すればいいのだろう。しばし思案した結果、このような答えが導き出された。
「サングラスをかけ、帽子を深くかぶり、正体がバレないようにこそこそと歩けば、完全なるVIPである」
サングラス越しに見えたセレブの景色
黒いサングラス、黒いキャップ、黒いマスク。この三点セットを装着して、鏡で姿を確認すると、そこに立っていたのは曇りなき芸能人である。
颯爽(さっそう)と、外へ飛び出す。「自分は有名人である」という前提で、凛と背筋を伸ばし、近所を散歩する。横断歩道を渡る時も、気取らず、しかし堂々と。目線は少し遠くへ。「あの人、もしかして普段からランウェイを歩いている……?」と他の通行人たちに思ってもらうためである。VIPはプライベートの場面においても、VIPの意識を絶やさないものなのだ。
途中、コンビニでコーヒーを買い求める。それを片手に歩けば、映画撮影の合間に、麻布でも白金台でもない景色を、物珍しさと共に楽しむトップスター俳優の気分が現れる。そうか、これが放置自転車というやつか。そうか、これが雑草と呼ばれるものなのか。「ここでは私の知らないリアリティが息をしている……」などと、VIPならではの特権的なインスピレーションを湧き起こしたりする。本来的にはまったく湧き起こす必要のないインスピレーションである。
季節は冬。サングラスをかけているのは私だけだ。悪目立ちをしているのだろう、すれ違う人々は、こちらにチラっと訝(いぶか)しげな目線を送ってくる。その警戒のまなざしを「ああ、これが有名税ってやつか」と強引に解釈して、意気揚々と散歩を続ける。
歩を進めるたび、私の中のVIP濃度は上がっていった。信号待ちをしている最中、他者の視線を背後から勝手に受け取り、「プライベートですので……」といった感じで足早にその場から逃れる。スマホを取り出す人を見かけたら、「撮られたかも……?」と疑心暗鬼になる。向こうからやって来る中学生たちの笑い声を聞き、「きっと私の噂話だ……」と思ったりもする。
自意識が上昇し、まるで世界の重要人物になったような高揚感に襲われていく。私はもはや、誰よりも私を見ているファンとなっていた。
行き交う人々が、サングラスとキャップとマスクを装着した自分のことを、遠慮がちに注目している。そんな錯覚の頂点で、私は私の中にある「無名」を見失った。有名人として歩く近所の道は、レッドカーペットそのものだった。見るものすべてが、鮮やかに輝いていた。
夜が近づいてくる。そうだ、夕食のことを考えなければ。スーパーにでも寄っていこう。
自動ドアのガラスに映る自分の姿を見て、静かにサングラスを外す。キャップも脱ぐ。そして20%引きシールの貼られた鶏肉をカゴに入れる。豆腐も買う。今夜は水炊きだな、なんて考えながら、カサカサと音を立てるレジ袋を抱えて、家へと足を向ける。
そうやって、私は名前も高揚感もない道をたどりながら、庶民へと帰還していった。
文・写真=ワクサカソウヘイ
『散歩の達人』2025年12月号より