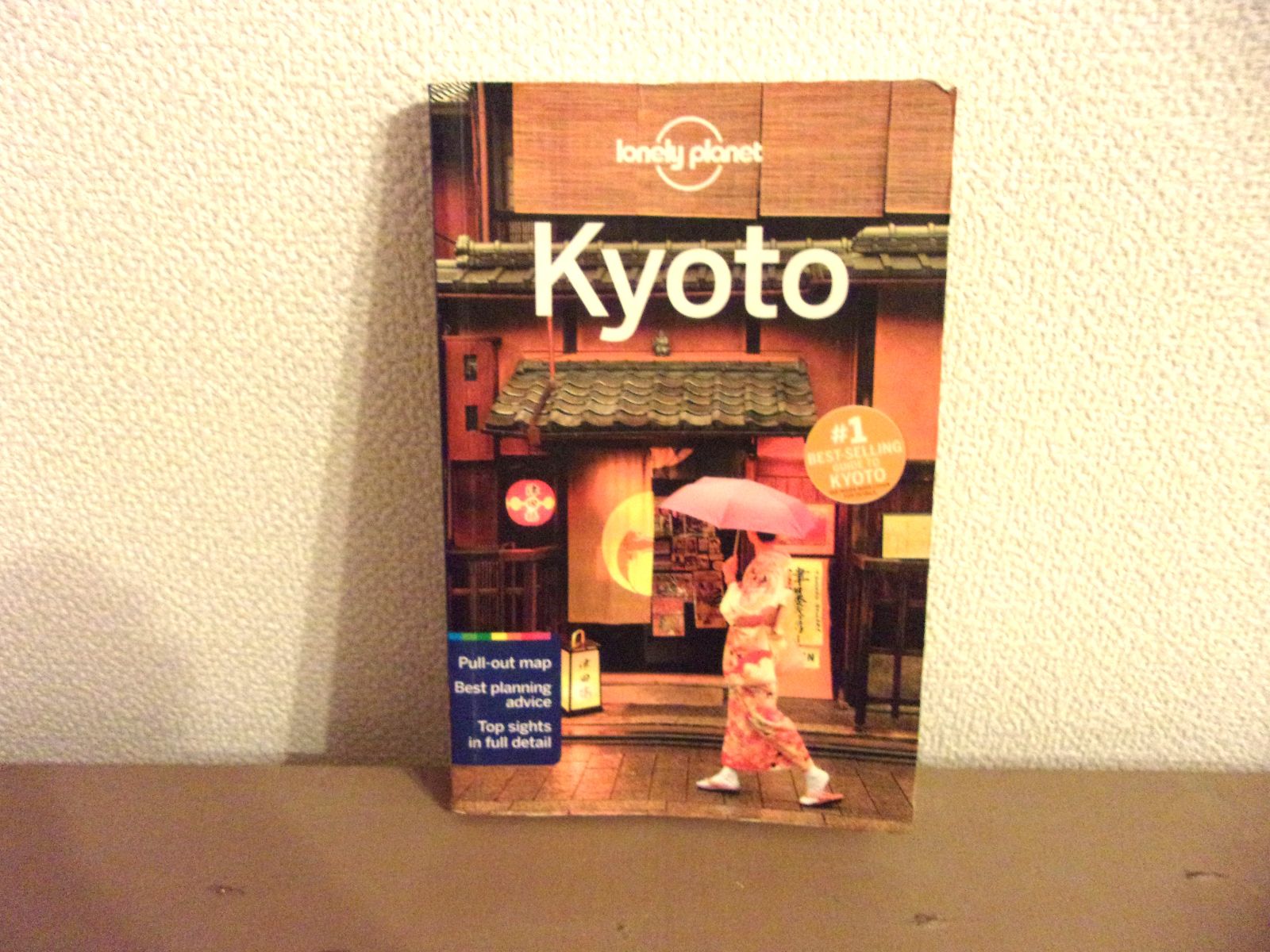『神奈川宿歴史の道』の途中には、神奈川宿のころの茶屋を想起させるような料亭が、今も残されています。
こちらの料亭『滝川』は、昭和になってから建てられたそうですが、宿場町らしい風情を感じる建物です。
通り沿いの壁には、十返舎一九作『東海道中膝栗毛』と安藤(歌川)広重作『東海道五拾三次之内 神奈川 台之景』のコラボ案内板が取り付けられていました。
今も坂の急さ加減は、この浮世絵の状態のままのように思えます。
『東海道五十三次 神奈川 台之景』で『さくらや』と書かれているのが、次にご紹介する割烹料亭『田中家』の前身だそうです。
『田中家』は、坂本龍馬の妻だったお龍(りょう)さんが龍馬が亡くなった後に働いていた場所として知られていて、前から気になっていました。
以前、司馬遼太郎さんの『龍馬がゆく』を一気読みした後、高知の桂浜と『坂本龍馬記念館』、京都の『寺田屋』と『京都霊山護國神社』を訪れるほどハマりました。
ちなみに、『寺田屋』は、風呂に入っていたお龍さんが2階までダッシュしたおかげで、龍馬の暗殺が防がれた場所として知られています。
『京都霊山護國神社』は、一緒に暗殺された中岡慎太郎の墓と龍馬の墓が並んで建っている場所で、目の前が開けていて、眺めがよかった印象があります。
龍馬ゆかりの場所を結構訪れていたのですが、灯台下暗しというか、一番近い場所にまだ行っていませんでした。
お龍さんのお墓は、龍馬とは別で(再婚したこともあり)、横須賀市の信楽寺にあるようです。こちらも行ったことはないです。
『田中家』の前の立て看板には、明治7年(1874年)に勝海舟の紹介で働き始めたと書かれています。
米国総領事ハリスや伊藤博文、西郷隆盛、高杉晋作などが、このお店で倒幕の計画を立てていたこともあったそうです。
お店の横の階段を下り、下から『田中家』を見上げて撮影してみました。
『東海道五拾三次之内 神奈川 台之景』だと、このお店の前は海になっているので、このあたりは埋め立てられたことがわかります。
高島町の名前の由来となった高島嘉右衛門が、埋め立て事業を請け負ったそうです(現在は高島山トンネルになっている場所の上にあった自宅から、進捗をチェックしていたといわれています)。
横浜の市立小学校に通ったので、高島嘉右衛門のことは、『吉田新田』の吉田勘兵衛と共に社会科の授業で習ったような記憶がうっすらあります。
話は変わりますが、江戸時代、神奈川宿では浦島太郎伝説にちなんだ『亀の甲せんべい』が名物だったそうです。
『反町公園』の近くには、浦島太郎が竜宮城から持ち帰ったとされる『浦島観音像』がまつられる『慶雲寺』もあります。
『亀の甲せんべい』は『若菜屋』というお店で生まれましたが、今はこの周辺では作られていないようです。
『若菜屋』の名前でピンと来なかったのですが、資料を調べたところ、『若菜屋』を継がずに家を出た方が、関内にある老舗鰻屋さん『わかな』を明治5年(1872年)に始めたのだそうです。
横浜にいたころ、母と2人で1度だけお店に食べに行った記憶を懐かしく思い出しました。
参考資料:
・「神奈川新聞」2001年1月11日(木) 「ある東海道名物-亀の甲せんべい物語」
・「資料が語る 坂本龍馬の妻 お龍」
・Web版 有鄰 第434号 [座談会]横浜駅物語 「みなとみらい線」開業にちなんで
・『割烹 料亭 田中家』公式サイト