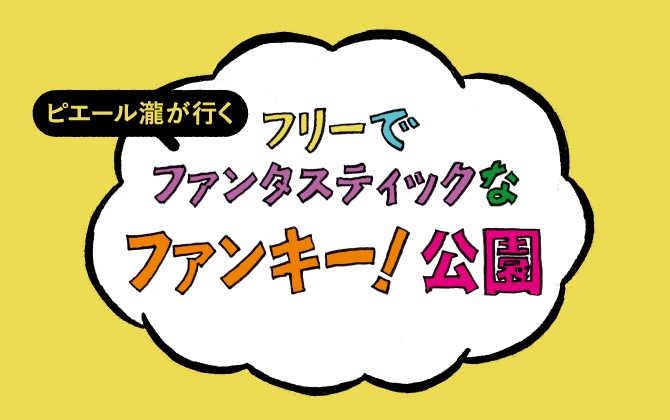国分寺で最も歴史あるイタリアンは、変わらぬ味と価格
1988年開店。国分寺で最も古いイタリアンがここ、『メランツァーネ』である。
国分寺駅南口から徒歩1分。商店街に面したビルの入り口には、歴史を感じるイタリアンシェフの看板が掲げられている。一瞬足を運ぶのに躊躇しそうな、細い路地の奥に構える店。少しドキドキしながら訪れる。
恐る恐る扉を開けると、視界に広がる景色。
明るいクリーム色を基調としたインテリアと、随所に絵画が点在する温かみのある雰囲気だ。
まるで海外の食堂に一歩足を踏み入れたかのよう。
店主である若林龍一さんは、20歳から原宿で料理人として働いていた。都会の中心ではイタリアンがちょっと特別な料理として広がり始めていた頃だ。
「都下であるここ国分寺にも『イタリアン』を」と店を始めたのは、若林さんが30歳の時だった。それから時は昭和、平成、令和と過ぎ、今では国分寺にイタリアンがひしめくほど定着している。
時代が変わり、街の様子が変わっても、若林さんはオープン以来手作りにこだわり、変わることのない味と価格で提供している。
「いつでも美味しくてホッとできるマンマの味を食べて欲しいんですよね」
愛情のこもったメニューの数々は、注文をうけてから手作り
『メランツァーネ』といえばパスタ。何せ30種類以上もあるというのだから、どれにしようか迷ってしまう。若林さんのおすすめは、店名であり、看板メニューであるメランツァーネ(なすとアンチョビ)だ。
しっかりグリルしたナスにたっぷりのオイルとアンチョビが絡むパスタは、ちょうどよいアルデンテ。クセがなくスルッと食べれてしまう味わいだ。
オリーブオイル系のメニューに始まり、和風、トマト、クリームソースと揃うので、訪れるたびに自分好みの味を探すことができる。
パスタ以外にも一品料理や肉・魚料理が彩り豊かに揃う。
前菜には国産野菜を贅沢に使い、旬の野菜も取り入れた季節メニューで変化を生み出す。
ここにもナスの料理がお目見え。イタリアンで最もポピュラーな野菜であるナスは、前菜に始まり一品料理、パスタとそれぞれに取り入れている。
「同じナスでも調理方法が全然違うんですよ。グリルしたり、あげたり、煮込んだりと。それぞれに味わい深さが違うので食べ比べてみてほしいですね」
続いて肉料理もいただく。牛肉のビール煮込みは1日がかりで煮込んだ一品。添えられているニョッキひとつひとつもしっかり手間をかけている。
「うちのニョッキは、ジャガイモと里芋のハーフなんです。普通じゃがいもだけでしょう? 里芋が加わると優しい味わいなんです。丁寧にすりつぶして、ひとつひとつ丸めて作っていますよ」
いつでも帰って来たくなる場所がここにある
取材に訪れたのはランチタイムでもなく、ディナータイムでもない、いわゆるアイドルタイムの時間。そんな時間でもふらっと訪れる客がしっかり食事メニューを食べていく。店では昼夜変わらず同じメニューがいつでも食べることができるからだ。
「ランチタイムが終わってもいつも店は閉めないんです。常連客も多くて、混雑しない時間を狙ってくる人もいるのでね。そういう時にいつでも食べたいメニューが食べれるようにしています」
『メランツアーネ』を訪れる客は地元客だけではない。30年以上も店を続けていると、子供が大人となり国分寺を旅立っていく。こうして全国各地に旅立った客が、懐かしの味を求めて再び各地から訪れてくる。
「地球の裏側から店に来てくれる人もいるんです。もちろん帰国した時にですよ(笑)」
訪れる人にとって変わらぬ味があることはホッとするひととき。いくつになっても帰る場所がここ国分寺にはある。
取材・文・撮影=永見 薫